- 公開日:2025年09月09日
サーキュラーエコノミー(循環経済)とは?3Rとの違いや企業の取り組み事例を解説

近年、持続可能な社会の実現に向けて「サーキュラーエコノミー」への関心が高まっています。これは、資源の使い捨てを前提とする従来の経済システムから脱却し、製品や資源を可能な限り循環させる新しい経済モデルのことです。SDGsへの意識が高まるなか、興味はあっても具体的な内容やビジネスへのメリットを把握できていない方も少なくありません。
そこで本記事では、サーキュラーエコノミーの基本的な考え方や注目される背景、3Rとの違い、実際に取り組んでいる企業事例、さらに今後の展望についてわかりやすく解説します。
サーキュラーエコノミーとは?
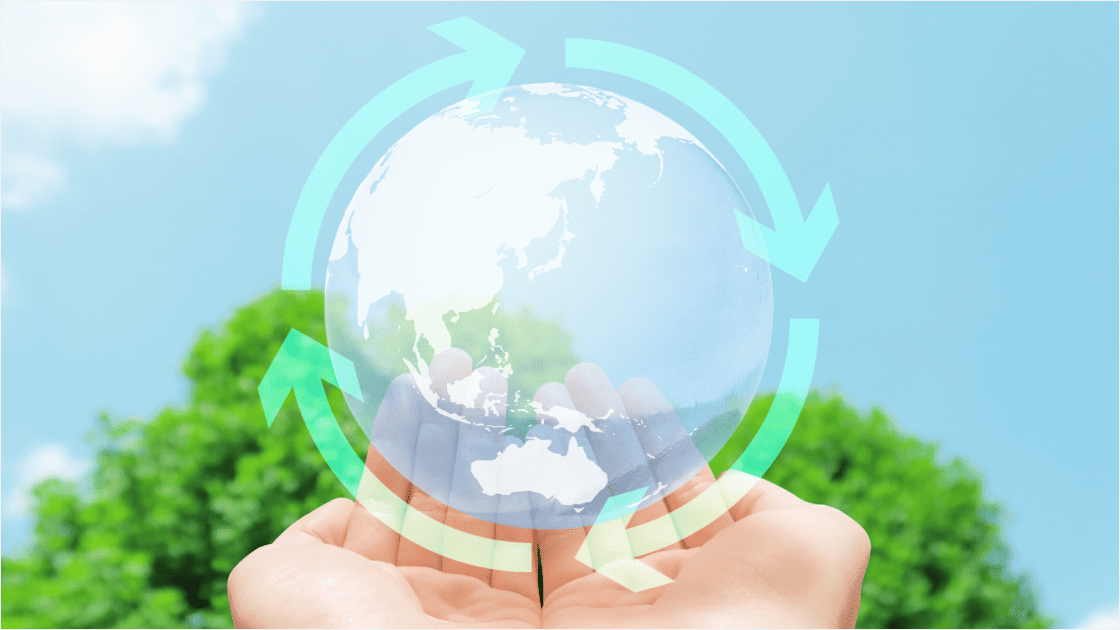
サーキュラーエコノミー(Circular Economy)は、日本語で「循環経済/循環型経済」を意味します。製品を長く使い続けられるように設計したり、再利用・再製造あるいはシェアや別の用途に転用したりすることで、資源の廃棄を最小限に抑える考え方です。また、使用済み製品の素材を「マテリアルリサイクル✳︎1」や「ケミカルリサイクル✳︎2」によって再加工するなど、資源の循環を何重にも重ねていきます。
さらに、バージン素材の使用を減らし、再生資源やバイオ素材への転換を進めることも、サーキュラーエコノミーの重要な要素です。バージン素材とは、天然資源をもとに作られる未使用の素材のこと。石油から作られたプラスチック樹脂や、木材から作られたパルプなどが代表例として挙げられます。
✳︎1:マテリアルリサイクルとは、廃棄物を新たな製品の原材料として再利用すること
✳︎2:ケミカルリサイクルとは、化学合成によって廃プラスチックを他の物質に変え、新たに製品の原材料として再利用すること
サーキュラーエコノミーが注目される背景
これまでの経済活動は、原材料を使って製品を作り、使い終わったら廃棄する直線型経済「リニアエコノミー」が主流でした。しかし、資源の枯渇や地球環境への負荷が深刻化するなか、この仕組みの持続可能性に疑問が投げかけられるようになっています。
こうした背景から、EUを中心に世界ではサーキュラーエコノミーへの移行が進められており、日本でも脱炭素や資源価格の高騰への対策として注目が集まっています。経済産業省は「循環経済ビジョン2020」を発表し、企業活動のなかに循環型の視点を組み込むことを推進しています。社会全体での構造転換が進みつつある今、企業も対応が求められているのです。
リサイクリングエコノミー(3R)との違い
日本ではこれまで、「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rを軸としたリサイクリングエコノミーに力を入れてきました。これは、製品や資源を無駄にせず、再利用・再資源化することを目的としていますが、完全な廃棄ゼロの実現は容易ではありません。すべての素材が再資源化に適しているわけではなく、回収・分別の過程でエネルギーやコストがかかるため、現実的には一定量の廃棄が避けられないのが現実です。
一方、従来のリサイクルの枠を超えているのがサーキュラーエコノミーです。製品の設計段階から循環を意識し、将来的な資源の投入自体を減らすという視点を持っています。さらに、廃棄物に新たな価値を持たせる仕組みを構築し、経済と環境の両立を図ることが可能です。つまり、3Rよりも広範で包括的な枠組みがサーキュラーエコノミーだといえるでしょう。
企業がサーキュラーエコノミーに取り組むメリット
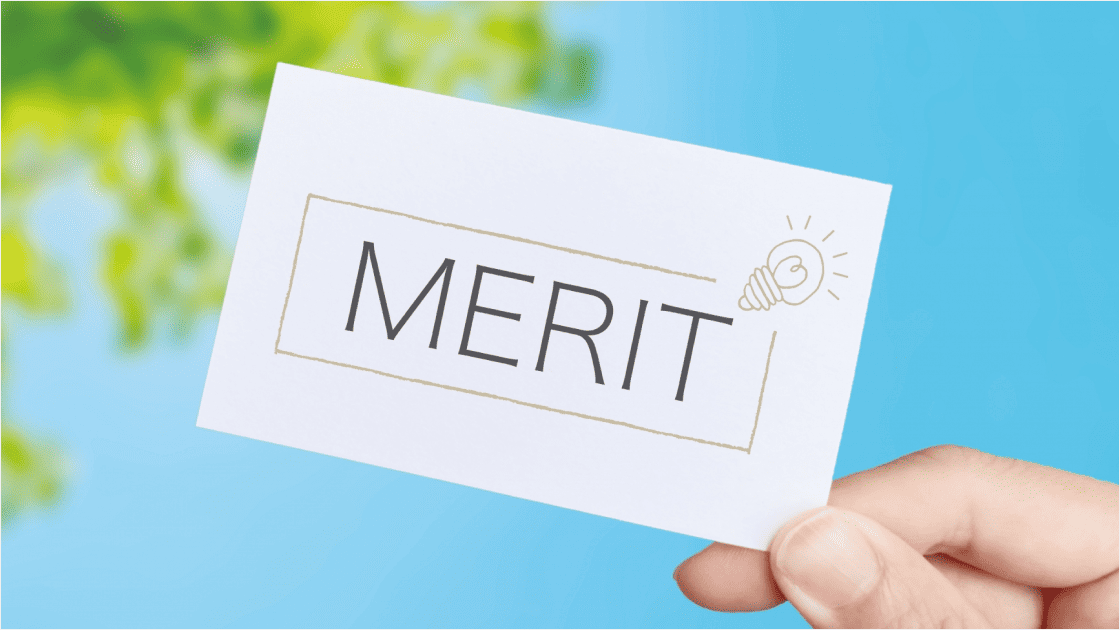
サーキュラーエコノミーへの対応は、環境保全だけでなく企業にとってはビジネス上でも数多くのメリットがあります。企業イメージの向上、コスト削減、環境規制への先行対応など、持続可能な経営戦略として注目されています。
以下では、企業がサーキュラーエコノミーに取り組む具体的なメリットを見ていきましょう。
企業イメージ・ブランド力の向上
環境問題への取り組みは、顧客や取引先、地域社会との信頼関係を築くうえで重要な要素です。サステナブルな企業として認識されることで、企業イメージが向上し、新たなビジネスチャンスの創出や環境意識の高い人材の採用にもつながります。
例えば、IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の調査「24卒就活生のSDGsに関する意識調査」では、就職活動中の学生の5人に1人がSDGsへの取り組みを重視していることが報告されています。また、インテージが公開したSDGsに関する調査では、消費者の約半数が「SDGsに取り組む企業を応援したい」と考えており、購入行動にも影響を与えていることが読み取れます。社会的責任を果たす姿勢は、企業の競争力を高める要因にもなり得るでしょう。
出典:インテージ 「知るギャラリー」2024年2月20日公開記事
コスト削減につながる
サーキュラーエコノミーでは、製品の再利用や素材の再生を前提とした設計が基本となるため、調達コストや廃棄コストの削減につながる可能性があります。例えば、再生可能素材の活用により資源価格の変動リスクを抑えられるほか、再利用の促進・製品寿命の延長によって、買い替え頻度の抑制や調達コストの削減が期待されます。
もちろん、回収や再利用にかかる初期コストは発生しますが、製造工程の効率化や在庫ロスの削減など、長期的に見れば経済的メリットは十分見込めます。サーキュラーエコノミーは、持続可能性とコスト最適化を同時に実現する仕組みともいえるでしょう。
将来的な環境規制への先行対応が可能
世界的に脱炭素社会への移行が加速するなか、将来的には企業に対しても環境配慮が法的に義務づけられる場面が増えると予想されます。例えば、EUでは製品の持続可能性を高めるための「エコデザイン規則(ESPR)」が導入され、OECD✳︎3が提唱する「拡大生産者責任(EPR)✳︎4」に基づく法規制も各国で進められています。これらの動きは日本企業にも少なからず影響を及ぼす可能性があります。
こうした流れに先んじて、製品設計や素材選定の段階から資源循環を前提にした仕組みを構築するなど、サーキュラーエコノミーの考え方を事業へ落とし込むことで、将来の施行が予想される法規制に対して、先行した対応がとれるでしょう。また、取り組みのなかで得られたノウハウを活かして新たなビジネス展開や製品開発に役立てることで、競争優位性を築けるかもしれません。
✳︎3OECD(経済協力開発機構)とは、経済や環境政策などに関する提言を行う先進国中心の国際機関のこと
✳︎4拡大生産者責任(EPR)とは、製品の使用後も含めたライフサイクル全体において、生産者が廃棄やリサイクルの責任を負うという考え方
サーキュラーエコノミーに取り組む国内外の企業事例
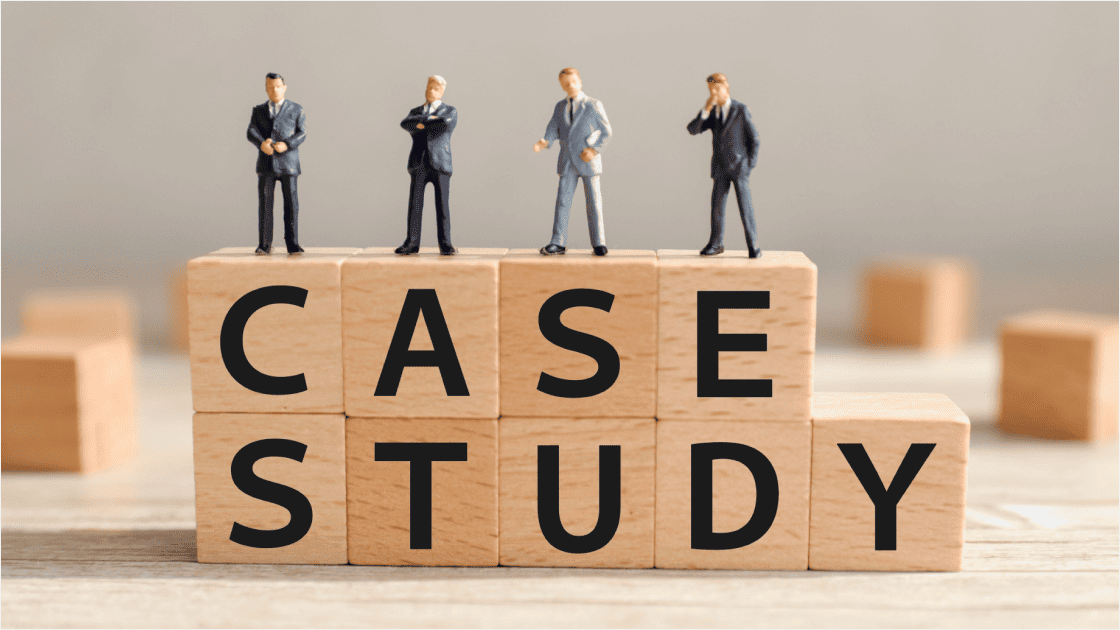
実際にサーキュラーエコノミーを導入し、成果を上げている企業も増えています。ここでは、業界や国を問わず先進的な取り組みを行っている3社の事例を紹介します。
【日本】大手衣料品メーカー
日本を代表する大手衣料品メーカーでは、使用済みの自社製品を回収し、再加工して販売するプロジェクトを展開しています。店頭での回収体制を整え、回収品の素材を分別・再加工。再製品化した商品を再び店頭に並べるというサイクルを確立しています。従来のリサイクルのように廃棄される資源を再利用するだけでなく、回収を前提とした設計・販売を行って資源を何度も循環利用する点は、サーキュラーエコノミーの代表例と言えるでしょう。
この取り組みにより、同社は廃棄される衣料の削減と再生資源の活用を同時に実現しており、循環型社会の構築に貢献。また、サステナブルな取り組みとして企業イメージの向上にも寄与しています。
【フランス】大手タイヤメーカー
フランスの大手タイヤメーカーでは、「2050年までに自社製品を100%持続可能な素材で製造する」という目標を掲げています。その一環として、廃棄されるポリスチレンからスチレンを再生したり、ペットボトルや木材チップなどを再利用したりと、革新的な素材技術の開発に取り組んでいます。
さらに、使用済みタイヤからスチールやガスを回収する独自の特許技術も保有しています。従来の販売型モデルに代わり、走行距離に応じたリース型の新たなビジネスモデルの導入も検討されており、循環型経済への本格的な移行を進めています。
【アメリカ】スポーツ用品メーカー
アメリカの大手スポーツ用品メーカーでは、2030年までに炭素排出量30%の削減や、廃棄物の99%を再活用することなどを目標として掲げています。すでに75%以上の製品に再生素材が使用されており、シューズや衣類にもサステナブルな素材が積極的に取り入れられています。
また、製造過程で出る残布や古着を回収・再利用するプログラムを展開し、持続可能な製品開発を推進しています。ブランドとしての社会的責任を果たしつつ、循環型ビジネスの先駆けとして取り組みを進めています。
企業が今から考えておきたい"サーキュラーエコノミーの今後"
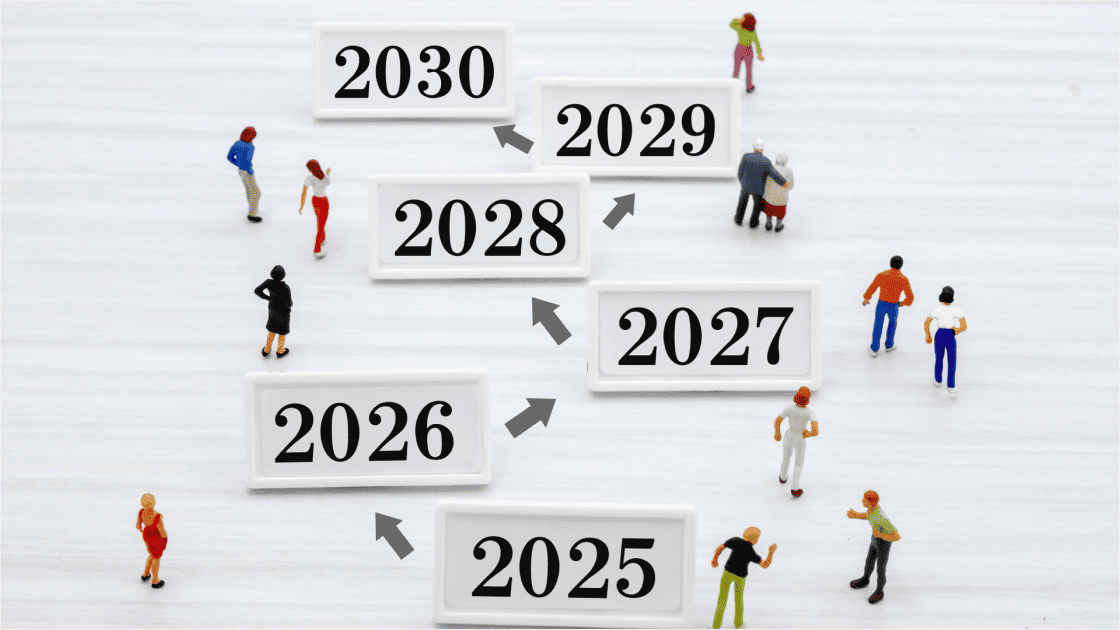
サーキュラーエコノミーは今後、AIやIoTの技術と連携しながらさらなる進化を遂げると予測されます。例えば、資源の流通や使用状況をリアルタイムで追跡できるトレーサビリティが進化することで、無駄の削減や再利用ルートの最適化がより容易になるでしょう。
また、再生可能素材やリサイクル技術の進化によって、従来は難しかった分野でも循環型設計が可能になることが考えられます。製品単体ではなく、部品・流通・回収までを含めた「サプライチェーン全体での循環設計」が求められる未来がやってくるのは、そう遠くありません。
中小企業にとっても、自社の技術や特性を活かしてニッチ市場に参入するチャンスが広がっています。サーキュラーエコノミーは、今後の企業戦略における重要なキーワードとなるでしょう。
サーキュラーエコノミーで企業の成長機会が広がる

サーキュラーエコノミーは、もはや一部の先進企業だけが取り組むものではありません。資源制約や環境問題に直面する今、企業規模や業種を問わず、全ての企業にとって重要な経営課題となりつつあります。
資源を有効活用しながらコストを抑え、社会的信用力やブランド価値を高める。そして、未来の環境規制にも柔軟に対応できる。サーキュラーエコノミーへの取り組みは、企業の持続的成長を支える有力な戦略のひとつとなるでしょう。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。



