- 公開日:2025年10月23日
DCIとは?データセンター間接続の基本概念や導入メリット、活用事例を解説

企業の事業拠点拡大やクラウド活用の進展により、単一のデータセンターでは災害や設備障害、容量不足などのリスクに対応しきれないケースが増えています。こうした課題の解決策として注目されているのが、データセンター間接続(DCI)です。
DCIは複数のデータセンターを高速かつ安全に結び、分散拠点を一体的に運用することで、事業継続性の確保やネットワークの最適化、災害対策を実現します。本記事では、DCIの基本概念や導入メリット・注意点、実際の導入事例について紹介します。
DCI(データセンター間接続)とは
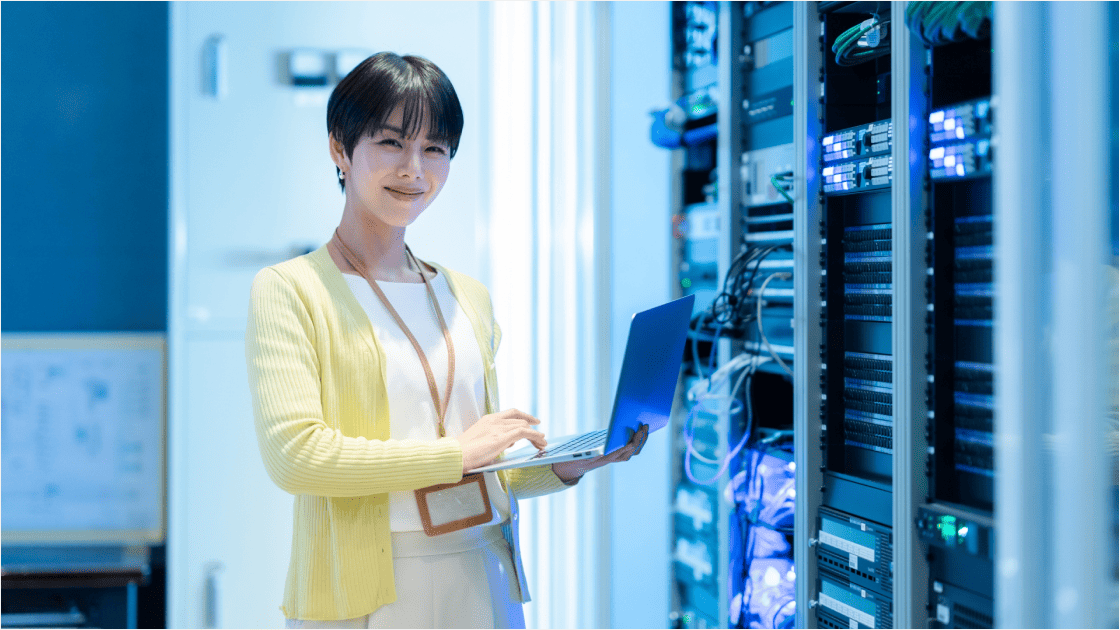
DCI(Data Center Interconnect)は複数のデータセンターを結んで通信データやストレージを共有し、分散拠点を一体として運用する技術です。専用の光回線を使用してデータセンター同士を直接接続することで、インターネットの混雑や障害の影響を受けにくい、安定した通信環境を構築します。
DCIの導入は、安定した通信とバックアップ体制により、拠点間のデータ共有の遅延、災害時の事業継続リスク、クラウド接続の不安定さなど企業の抱える課題に対応し、より信頼性の高いシステム運用を実現します。
DCIの分類
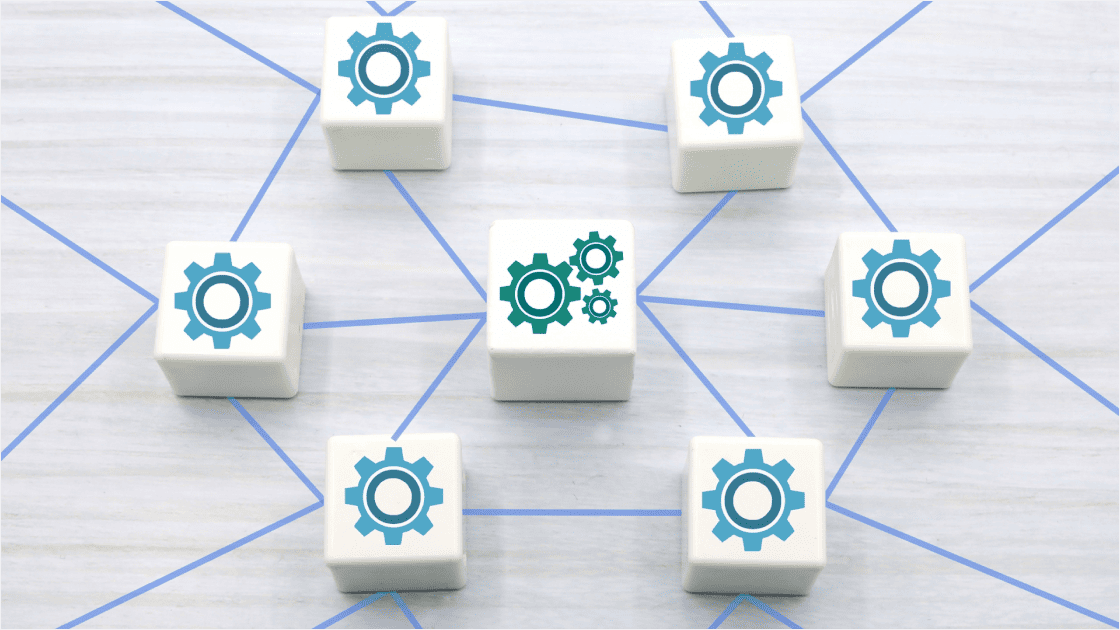
DCIは、大きく「通信事業者が提供するサービスを利用する方法」と「自社で独自に構築する方法」の2つに分けることができます。
それぞれの方法に異なる特徴があり、事業者の規模、技術力、コスト要件、運用体制などを総合的に考慮して選択する必要があります。以下で、これら2つの分類について紹介します。
通信事業者が提供するDCI
通信事業者が提供するDCIは、専用線等のWANサービスを利用したデータセンター間接続サービスです。通信事業者が事前に光ファイバーや回線収容システムを整備しているため、短納期でサービスを利用することが可能で、運用・保守も通信事業者に委託することもできます。
一方、通信会社以外が提供するDCIサービスもあり、複数の通信事業者が提供するサービスの中から選択可能であるため、場合によってコストを抑えられることがあります。
自社で構築するDCI
動画配信サービスやECサービスなど大容量のデータ通信が必要な事業者などでは、自社でDCIを構築する動きもあります。DCIを自社で構築する場合、ダークファイバー(未使用で稼働していない光ファイバー)を利用し、独自に伝送装置を設置してデータセンター間の接続を行います。
通信事業者が提供するDCIが比較的高額になる傾向があるため、コスト削減を目的として、自社で構築するケースが多く見られます。これらの事業者は、自社で冗長化構成を組みデータセンター間を接続することで、通信事業者が提供する障害対策機能に依存せず運用でき、その分コストを抑えられる傾向にあります。ただし、回線の品質管理や障害発生時の復旧作業等、すべて自社で賄う必要があり、相応の技術力と運用体制が求められます。
DCIが必要とされる背景

企業が持続的に成長するには、変化する事業環境に柔軟に対応できるIT基盤の構築が必要です。ここでは、DCIが必要とされる背景について紹介します。
サービス多様化によるデータ通信量の増大
サービス多様化に伴い、動画配信やオンラインゲーム、IoTサービスなど大容量データを扱うサービスが普及し、企業が処理すべきデータ量とサーバ需要は急激に増加しています。
しかし、単一のデータセンターで対応できる容量には限界があり、電力供給や冷却設備、設置スペースなどの制約で既存拠点の増強は難しくなっています。結果として、サービス需要の拡大やクラウド利用の進展に合わせて新たな拠点を設置する企業も増えています。
一方で、複数データセンターを個別に運用すると拠点間通信の遅延や管理の複雑化が課題となります。こうした課題を解決する手段としてDCIを導入し、複数のデータセンターを高速ネットワークで結ぶことで、負荷分散や災害対策を含む統合されたIT基盤としての運用を実現できます。
災害・障害リスクへの備え
単一のデータセンターに依存していると、地震や洪水などの自然災害に加え、火災や設備故障といったトラブルが発生した際に、事業継続に深刻な影響が及ぶ可能性があります。
地理的に離れた複数のデータセンターを相互接続することで、リアルタイムのデータ同期やバックアップが可能になるため、リスク分散と冗長化を実現できます。一方の拠点で障害が発生しても、他方が稼働を継続し、サービス停止を最小限に抑えることが可能となるため、BCP(事業継続計画)の観点からも有効な対策となります。
グローバル展開による通信遅延
海外のサービスやアプリケーションを利用する際、物理的な距離が長いほど通信の応答時間(レイテンシ)が増え、通信遅延が課題となります。例えば、日本からアメリカのサービスを利用すると、データの往復に時間がかかり、Webサイトの表示速度低下、動画ストリーミングの品質劣化、オンラインゲームでの操作遅延などが発生します。
こうした課題に対し、海外のサービス事業者が日本国内にデータセンターを設置し、DCIで本国サーバと専用線や専用ネットワークで接続するケースが増えています。インターネット経由のように経路が分散せず、データセンター同士を直接結ぶため、遅延を最小化でき、通信の安定性も向上します。同様に、日本企業が海外のデータセンターとDCIで直接接続するケースでも、グローバル展開における快適なサービス提供を実現できます。
DCI導入で期待できるメリット

DCI導入の効果は通信インフラの強化にとどまらず、企業の収益性向上と競争力強化につながる可能性があります。ここでは、DCI導入によって期待できる主要なメリットを詳しく解説します。
事業継続性の向上
自然災害やシステム障害は予測不可能で、単一のデータセンターに依存していると事業停止リスクが高まります。DCIを活用し、数十キロ離れた複数拠点に同一データを保存することで、一方に障害が発生しても他方が稼働を継続でき、サービス停止を最小限に抑えられます。例えば、東京と大阪のデータセンター間をDCIで接続することで、首都直下地震のような広域災害時でも事業継続体制の構築が期待できます。
ネットワーク性能の向上
複数のデータセンターを相互に接続することは、災害時のバックアップだけでなく、処理の負荷分散やネットワーク性能の向上にもつながります。
単一のデータセンターのみで運用している場合、アクセス数の急増やデータ処理量の増大時にシステムが重くなる問題が発生します。しかし、DCIにより複数拠点を連携させることで、負荷が高いときでも自動的に処理を振り分けられます。
例えば、東京のデータセンターが混雑している場合、大阪のデータセンターに一部の処理を回すことで、全体の処理速度を維持できます。その結果、Webサイトの表示速度や業務システムの応答時間が改善され、従業員の作業効率向上や顧客満足度の向上につながります。
セキュリティの強化
DCIでは企業専用の閉域ネットワーク環境を構築し、認証されたユーザーのみがアクセス可能です。インターネットから分離されたネットワークを利用することで、外部からの不正侵入を抑制し、機密データの漏えいリスクを大きく抑えることができます。
DCI導入の注意点

DCI導入は多くのメリットをもたらす一方で、事前に把握しておくべき課題もあります。ここでは、DCI導入時に注意すべき点をご紹介します。
導入・運用コストの負担
DCI導入には高額な初期費用が発生するため、大きな負担となり得ます。光伝送装置やルーターなどの専用機器の購入費、ダークファイバーの契約料、システムの設計・構築費用などが必要になります。
さらに、高額な初期投資に対する明確な投資効果を算出することは容易ではありません。将来的なトラフィックの増加や事業成長の見通しを正確に予測することは難しく、結果として投資判断を複雑化させる要因となります。
専門人材の確保
DCI導入により、従来の単一データセンター運用から、複数拠点にまたがる複雑なネットワーク管理が必要となります。複数拠点間でのリソースの適切な割り当てや、障害発生時の迅速な原因特定・対応など、運用業務の難易度は大幅に増加し、より高度な技術スキルが求められます。
このような高度な技術要件に対応できる専門人材の確保が困難となるケースも考えられます。運用サポートが充実した通信事業者を選定する、または既存人材への段階的な教育投資など、人材育成の取り組みも重要です。
DCIの導入事例
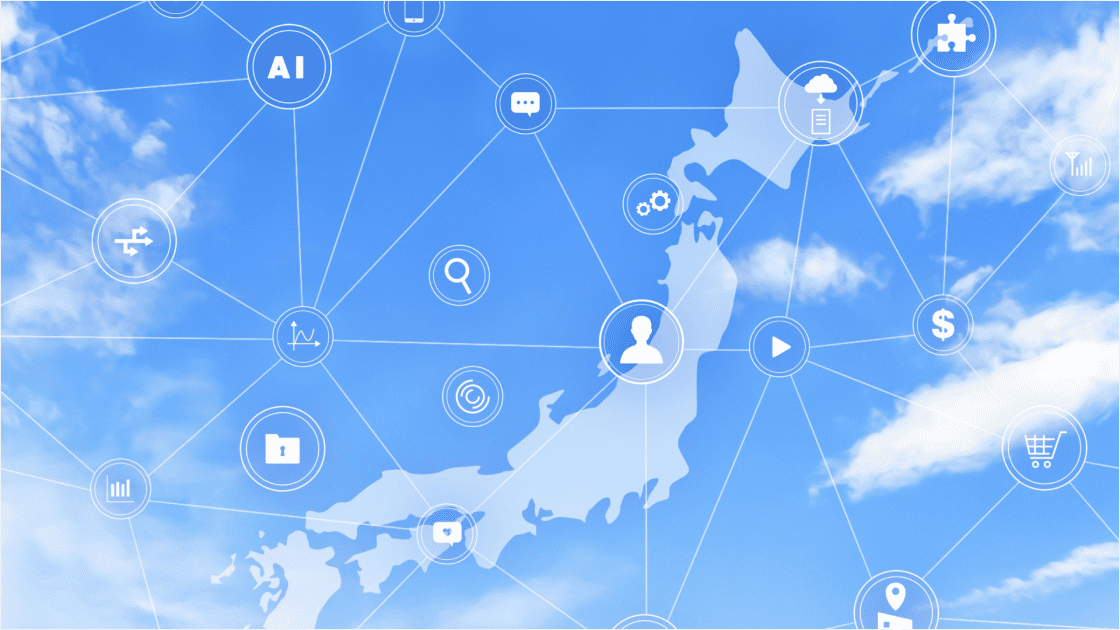
DCIは、さまざまな業種において、企業の事業特性に応じた形で導入が進められています。ここでは、DCI導入によって具体的な成果を上げた企業の実例をご紹介します。
ゲーム企業の通信容量の拡大における活用事例
SNSやスマートフォン向けゲームを展開する企業では、都市部の電力供給不足やスペースの制約を解消するため、郊外エリアに新しいデータセンターを設置しました。しかし、既存の都市部拠点との接続において、通信容量不足が課題となりました。
従来の都市部データセンター間の接続と比較して、郊外との接続では距離が大幅に延びたため、数百Gbps規模の高速・大容量通信が求められました。
解決策として、DCIを活用し、その結果、必要だった大容量通信を実現するとともに、データを光ファイバー内で暗号化する仕組みにより、高いセキュリティ環境でサービスを提供できるようになりました。
大手IT企業による顧客サービス向上事例
大手IT企業2社は、顧客サービスの向上と運用効率化を目的として、それぞれが保有するデータセンター同士をDCIで相互接続しました。従来は両社が個別にクラウド接続やネットワーク構築を行う必要がありましたが、データセンター間を閉域ネットワークで結ぶことで、両社の顧客は相互のサービスを安全かつ手軽に利用できるようになりました。
DCIによる相互接続により、顧客の需要や拡張計画に合わせて両者のデータセンターを相互に活用でき、事業拡大時の柔軟な対応が可能です。さらに導入効果として、クラウド接続の短納期化、セキュリティレベルの向上、バックアップ環境の強化が実現し、顧客全体に対して安定的かつ拡張性の高いIT基盤を提供できるようになりました。
地域IT企業によるBCP強化事例
新潟県と富山県に本社を置く2社のITサービス企業は、約200キロメートル離れた両社のデータセンターをDCIで接続し、広域災害対策サービスを開始しました。
両社は地域のリーディング企業として、公共機関、医療機関、民間企業などにITサービスを提供しており、東日本大震災以降、顧客からの津波や広域災害に備えたいという要望が高まり、サービス開始の契機となりました。
DCIにより異なる電力会社エリアと通信事業者エリアにまたがる拠点連携を実現したことで、一方のデータセンターで障害が発生しても、他方が自動的に処理を引き継ぎ、サービス停止を最小限に抑えることが可能です。
導入効果として、災害発生時の迅速な復旧や安定したサービス継続が実現し、顧客はより高度なBCP対策を低コストで導入できる環境を利用できるようになりました。
まとめ
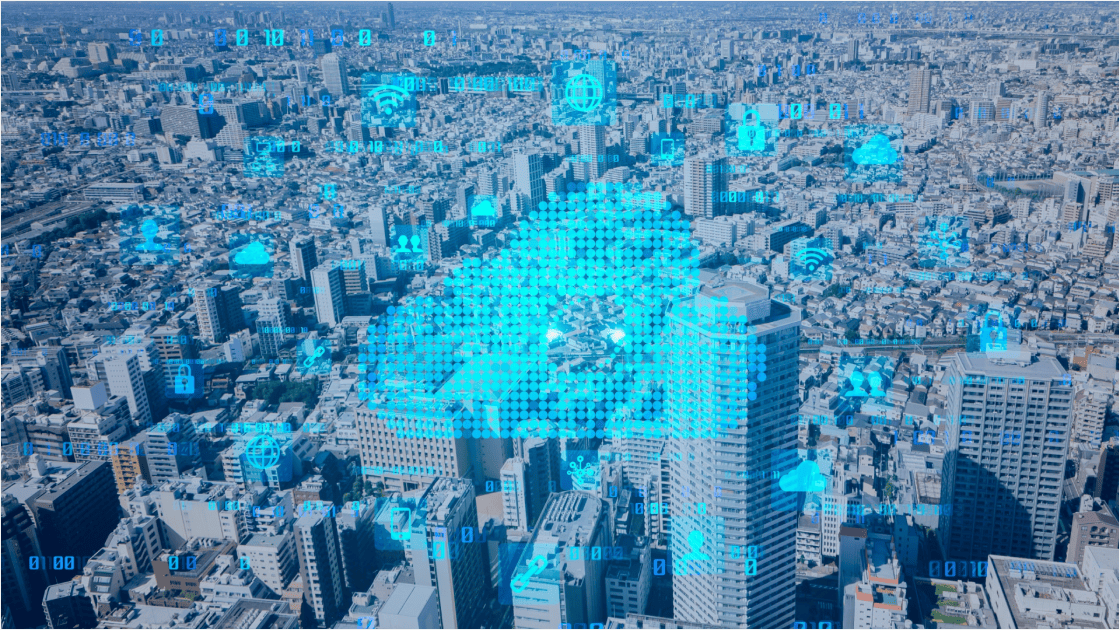
DCIは、複数のデータセンターを高速かつ安全に結び、分散した拠点を統合的に運用し、安定したネットワーク基盤を実現する仕組みです。データ量の急激な増加、災害時の事業継続リスク、海外展開時の通信遅延など、現代企業が直面する課題の解決に貢献し、システムの安定性向上、処理性能の改善、セキュリティの強化を実現します。
オプテージの国内データセンター間接続サービス 「OPTAGE Data Center Interconnection」は、高帯域・低遅延の専用回線により、データの高速通信や災害対策、システムの冗長化を可能にします。大阪市内を中心に関西圏内の各エリアや首都圏まで幅広く提供し、企業の多様なネットワーク需要に対応しています。
さらに2028年度からは国際海底ケーブルを活用した大阪・曽根崎データセンター(OC1)-首都圏-シンガポール間のグローバルDCIサービスを開始し、AIやクラウドサービスの普及により急増する国際間データ通信需要にお応えします。
詳しくは、OPTAGE、大阪・曽根崎データセンター(OC1)のコネクティビティを強化 海底ケーブルを利用した日本-シンガポール間・国際通信事業に参入|プレスリリースをご覧ください。
DCI導入についてお悩みの点がありましたら、オプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




