- 公開日:2025年03月10日
フォレンジック(デジタルフォレンジック)とは?調査内容や注意点を解説
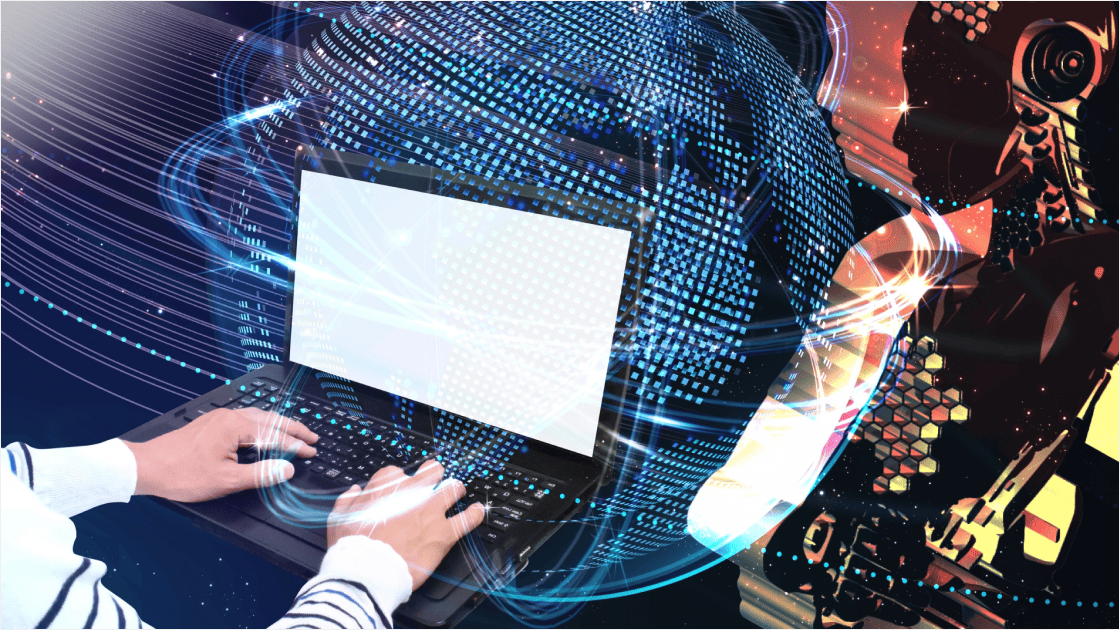
近年、ウイルス感染や不正アクセスといった外部からの攻撃をはじめ、横領やデータ改ざんなどの社内不正が多発しています。
こうしたインシデント発生時の有効な対策として、「フォレンジック調査(デジタルフォレンジック)」に注目が集まっていることをご存知でしょうか。フォレンジックとは、犯罪や事件に関するデジタル証拠の収集から分析・報告までを行う調査手法のことで、真相究明や再発防止に役立てられます。
今回はフォレンジックが注目される背景をはじめ、調査の内容や流れ、注意点などについて、詳しく見ていきましょう。
フォレンジック(デジタルフォレンジック)とは?

「フォレンジック(forensic)」は、もともと法廷や法的な状況に関連する意味合いを持つ英単語であり、犯罪の捜査・分析を行う際によく使われる用語です。
IT業界においては「デジタルフォレンジック」とも呼ばれ、サイバー攻撃や企業内不正の法的証拠を明らかにするために行われます。具体的には、パソコンをはじめとするデバイスやネットワーク、外部メモリーなどのデータを解析し、犯罪捜査に必要となる法的証拠の究明が主な取り組みです。
フォレンジックの重要度が高まる理由
フォレンジックへの関心が高まっている背景には、外部要因と内部要因の2つが挙げられます。
外部要因として挙げられるのは、マルウェアやランサムウェアといったサイバー攻撃です。例えば、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)によると、2024年に観測されたサイバー攻撃関連のパケットは、約6,862億にのぼります。1IPアドレスあたりに換算すると、NICTの観測開始以降最も多い約242万パケットにのぼり、2023年から約16万パケット増加しています(出典:国立研究開発法人情報通信研究機構 NICTER 観測レポート 2024)。
このように外部からの攻撃は年々深刻化しており、対策をしても間に合わないというケースも少なくないのです。
次に、内部要因としては、企業内での不正取引や情報漏えいの増加が挙げられます。例えば、東京商工リサーチが2024年1月に公開した「2023年 全上場企業『不適切な会計・経理の開示企業』調査」によると、2023年に不適切な会計・経理を開示した上場企業は前年比9%増の60社となり、件数も12.7%増の62件に達し、企業数・件数ともに前年を上回る結果となりました。
今やデジタル化された環境で業務を行う企業は少なくありませんが、それに伴いセキュリティインシデントや内部不正が発生しやすくなっています。このようなリスクの防止や万が一の問題が発生した場合の対策として、フォレンジック調査の重要性が高まっているのです。
フォレンジックの意義
フォレンジックは、近年深刻化するサイバー脅威に対する有効な手段のひとつになります。例えば、社内で不正が発覚した場合や、不正アクセスなどの被害に遭った場合、フォレンジック調査を行うことで事態の全貌を捉え、適切な対策を講じることが可能です。また、インシデントへの対応だけでなく再発防止策の公表ができれば、取引先・顧客からの信頼回復にもつながるでしょう。
このほか、フォレンジック導入を社内に周知すれば、不正行為の抑止効果も期待できます。企業が監視体制を整えていることを社員に認識させることで、横領やデータ改ざんといったリスクを未然に防げるでしょう。
フォレンジックの調査内容
IT業界におけるフォレンジックは、さまざまなデジタルデータの解析によって事件やインシデントの全貌を明らかにする調査手法です。どのような調査が行われるのか、主な調査内容を以下にまとめました。
- ログデータの解析
- 違法操作の特定
- 不正プログラムの特定
- サイバー攻撃の発信元の特定
- Webサイトへのアクセス履歴の調査
- 情報漏えい経路の追跡
- 削除されたファイルの復元
- メッセージやメールの復元
このほか、企業の業務環境や事件の内容によっては、タイムスタンプの改ざんやデータベースを調査したり、ネットワークトラフィックや暗号化データの解析を行ったりすることもあります。
フォレンジックの種類
フォレンジックは調査対象によって呼称が異なります。「コンピュータフォレンジック」と「モバイルフォレンジック」「ネットワークフォレンジック」の3種類があるため、それぞれの概要を把握しておきましょう。
【コンピュータフォレンジック】
パソコンやサーバなど、コンピュータ機器を対象とした調査手法がコンピュータフォレンジックです。HDDやSSDといった記録媒体を対象にしている場合は「ディスクフォレンジック」、稼働中のコンピュータのメモリーデータを対象にしている場合は「メモリフォレンジック」と呼ばれます。
削除されたデータの復元や外部メモリーに接続した痕跡を調べ、不正アクセスや情報漏えいの法的証拠を収集します。
【モバイルフォレンジック】
スマートフォンやタブレットなど、モバイルデバイスを対象に行う調査がモバイルフォレンジックです。端末に保存されている写真・動画や連絡先などのデータはもちろん、アプリの利用履歴や通信ログなども調査の対象となります。
不正なデータのやり取りやGPSの位置情報を解析することで、犯罪行為の証拠や行動の履歴の特定が可能です。また、意図的に削除されたデータも復元できる可能性が高く、犯罪捜査やトラブル解決に役立てられます。
【ネットワークフォレンジック】
ネットワーク上の通信データを対象にした調査手法がネットワークフォレンジックです。パケットキャプチャやログファイル、プロキシサーバのアクセスログなどを解析することで、マルウェア感染や不正アクセスなどの経路や被害範囲を特定します。また、ネットワークフォレンジックの調査結果は、捜査だけでなく再発防止策の策定にも役立てることが可能です。
フォレンジックの流れ
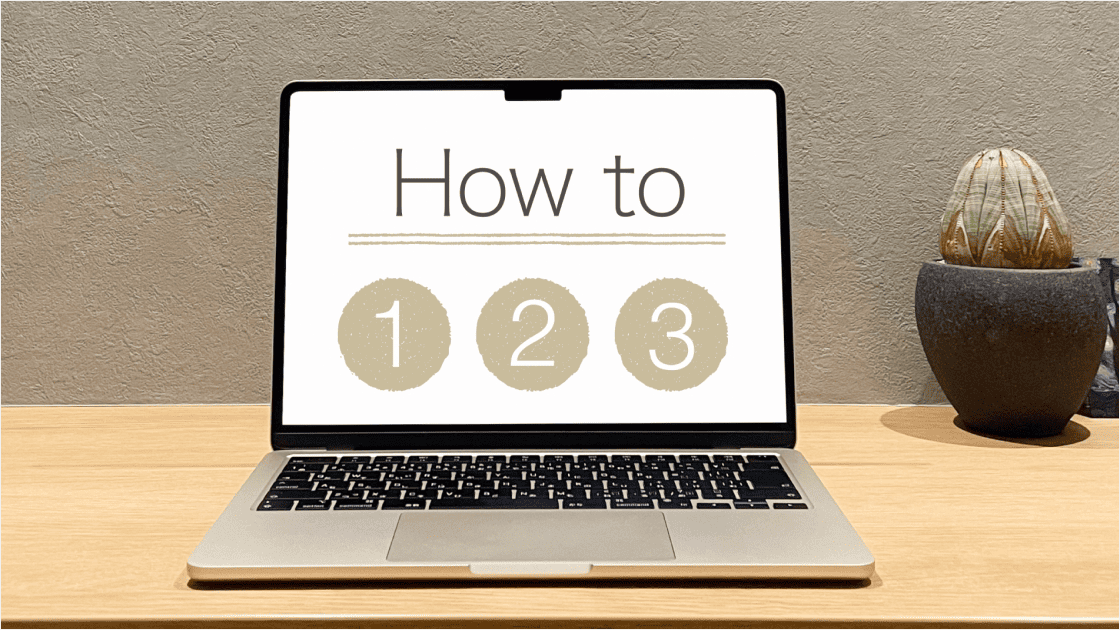
フォレンジックにはいくつか種類がありますが、調査の流れとしては「収集・保全」から始まり、「復元・解析」「証拠資料の作成・活用」の順に進められます。
各プロセスでどのようなことが行われるのか、詳しく見ていきましょう。
1.収集・保全
フォレンジックはいきなり調査を行うのではなく、証拠の保全やデータの収集から着手します。被害状況によっては、パソコンやモバイル端末などが調査対象となることも珍しくありません。
また、フォレンジック調査でのデータ保全は、現存データはもちろん削除データや未使用領域などもコピーし、完全に同一の形式でコピーすることが重要です。複製データに対して調査を行うことでオリジナルデータを保全でき、法的証拠能力が認められやすくなります。
2.復元・解析
サイバー攻撃や情報漏えいなどのインシデントが発生した場合、証拠となるデータが削除・暗号化されているケースも少なくありません。そのため、フォレンジックでは削除されたデータを復元したり、暗号化されたデータを解読したりする必要があります。
また、サーバログやメールの送受信履歴など、保全したデータから証拠となりうる情報を分析し、犯罪行為につながる情報やパターンを見つけ出します。
なお、自社でフォレンジック調査を行う場合は、専用のツールを用いることをおすすめします。データの収集・保全から、解析やレポート作成まで対応しているものもあり、専門知識がなくとも調査が可能です。ただ、フォレンジックツールは数多くあるため、コンピュータの鑑識やデータの取得・復旧、痕跡調査など、企業に必要な機能が備わっているかどうかよく確認しましょう。
3.証拠資料の作成・活用
フォレンジック調査によって収集・解析したデータをもとに、証拠資料を作成します。仮に外部からのサイバー攻撃や従業員による情報漏えいなどがあった場合、レポートが法廷での証拠として活用できるため、調査手法や解析結果を正確かつ客観的にまとめることが重要です。
また、作成したレポートは取引先や顧客などに説明する際に役立つほか、社内のセキュリティを強化するための参考資料としても活用できます。
フォレンジックの注意点

フォレンジックはサイバー攻撃や社内不正などのリスクを軽減するための重要な取り組みです。しかし、自社で行う場合、調査資料が法的証拠として認められなかったり、真相究明までに長い期間を要したりする可能性があります。
最後にフォレンジックに関する注意点を2つ解説します。それぞれ確認しておきましょう。
専門知識が求められる
フォレンジック調査には、デジタル技術や法律に関する高度な知識が求められます。仮に専門知識がないまま自社で調査を進めると、証拠資料としての正確性・信頼性が損なわれ、法的に認められない可能性もあるでしょう。
そのため、フォレンジック調査を内製化する場合は、専門知識を有する人材の採用・育成や、専用ツールの導入などが必要です。ただ、人材の育成には時間とコストがかかるため、自社で対応可能な範囲を見極め、必要に応じて外部に依頼することも検討しましょう。
調査に時間がかかる
フォレンジックはデータの保全や解析といった多くの工程を経る必要があるため、調査に時間がかかってしまいます。通常は1〜2週間ほどといわれていますが、インシデントの発生原因や影響範囲が不明確な場合は、調査に1カ月以上かかる可能性もあるでしょう。
調査を迅速に行うために、必要最低限のデータを抽出・コピー・解析する「ファストフォレンジック」を初期対応として実施したり、あらかじめ対応マニュアルを作成しておいたりするのも一つの手です。また、端末の怪しい挙動を検知・対処するセキュリティサービスを導入し、平常時のセキュリティ対策を向上させておくことも検討してみてください。
まとめ

フォレンジック調査は、企業がサイバー攻撃や内部不正といったリスクに対応するために把握しておきたい手法のひとつです。証拠となるデータの収集からレポート作成まで、調査を適切に進めることで、真相究明だけでなく、再発防止策の策定や外部からの信頼回復にもつながります。
ただし、フォレンジック調査には専門知識が求められ、調査期間が長くなることも珍しくありません。トラブル発生時の対応を用意しておくことは重要ですが、セキュリティ対策を強化してインシデント発生を未然に防ぐことも留意しておきたいポイントです。
オプテージでは、お客さまのセキュリティ対策に役立つサービスを数多く展開しています。自社のセキュリティが心配な方は、無料のセキュリティ診断「サイバーセキュリティ自己診断」でセキュリティレベルや必要な対策について確認してみてください。
また、端末の怪しい挙動があれば検知・通達する「EDR」や、外部へのアクセスを安全・快適に行うための「SWG」など、お客さまのセキュリティ課題に応じたソリューションをご提案させていただきます。詳しいサービス内容については、「ゼロトラスト・セキュリティ対策」をご確認ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





