- 公開日:2024年02月28日
- 更新日:2025年08月21日
ナレッジマネジメントとは?業務効率・組織力を高めるメリットと導入方法を紹介

業務の属人化や情報の分断が課題となるなか、ナレッジマネジメントは社内の知識を共有・活用し、生産性や組織力を高める経営手法として注目されています。
本記事では、ナレッジマネジメントの基本的な考え方や代表的な手法、導入ステップについて紹介します。
ナレッジマネジメントとは
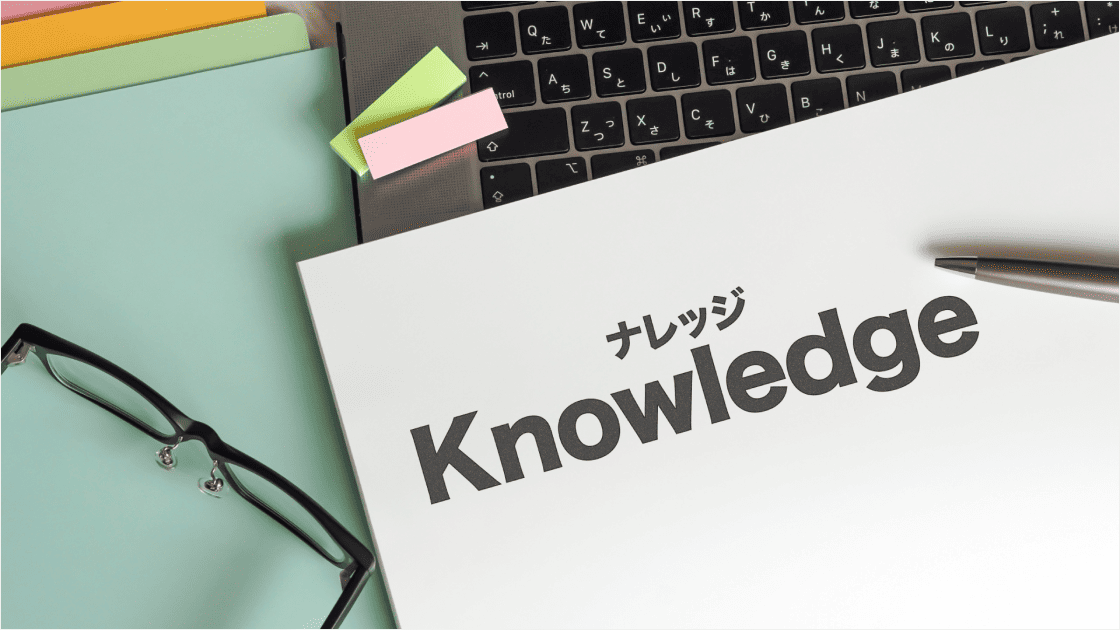
ナレッジマネジメントとは、社員一人ひとりが持つ知識やノウハウを企業全体で共有・活用し、業務効率や生産性の向上、企業価値の強化を図る経営手法です。「知識管理」「知識経営」とも呼ばれ、KM(KnowledgeManagement)の略称でも知られています。
経営学者・野中郁次郎氏の知識創造理論に端を発した理論で 、知識を資産と捉えた活用によって、企業の競争力や継続的成長を支える重要な施策とされています。
ナレッジマネジメントを支える考え方

ナレッジマネジメントを効果的に進めるには、知識の種類や共有の仕組みを正しく理解することが重要です。ここでは、形式知・暗黙知、SECIモデル、知識が生まれる「場」、知識資産という4つの視点からナレッジマネジメントの基盤となる考え方について紹介します。
形式知・暗黙知
形式知とは、個人の知識や経験を言語や図、マニュアルなどにまとめ、他者と共有しやすい形にした情報のことです。一方、暗黙知とは、勘や直感、身体で覚えた技術など、言葉化が容易ではなく共有が難しい知識を指します。
両者は相互に補完し合う関係にあり、暗黙知を形式知へと変換していくことで、組織全体での知識共有や活用が促進され、生産性向上や人材育成、業務の属人化防止にも貢献します。
SECI(セキ)モデル
SECI(セキ)モデルは、ナレッジマネジメントにおいて、暗黙知と形式知を相互に変換しながら、新たな知識を創造・共有するためのフレームワークです。各フェーズの頭文字から取ったもので、以下の4つのステップで構成されています。
| ステップ | フェーズ | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 共同化(Socialization) | 体験を共有して暗黙知を他者に移転 |
| 2 | 表出化(Externalization) | 暗黙知を言語化し形式知に変換 |
| 3 | 結合化(Combination) | 形式知同士を結びつけて新たな知識を創出 |
| 4 | 内面化(Internalization) | 新たな知識を体得し、再び暗黙知に変化 |
これらを螺旋的に繰り返すことで、組織内の知識は進化・拡充され、全体での共有や定着につながります。SECIモデルを活用することにより、ナレッジの循環が生まれ、企業の競争力強化に貢献します。
場の整備
ナレッジマネジメントにおける「場」とは、暗黙知や形式知が創造・共有・活用される空間や環境を意味します。SECIモデルを実践するうえで、「場」の整備は非常に重要です。以下の4種類の場を社内に用意することで、知識の流通や蓄積がスムーズに進み、組織の知見活用が促進されます。
| 名称 | 事例 |
|---|---|
| 創発場 | 気軽な場での会話からの知識交換 |
| 対話場 | 本格的なディスカッションを通じた知識の共有 |
| システム場 | ナレッジツールでマニュアルやノウハウを整理・共有 |
| 実践場 | 実務で試行錯誤しながら知識を身につける |
これらの場を意識して設計・運用することで、ナレッジが自然と循環し、学習する組織風土の醸成や業務の属人化防止にもつなげることができるようになります。
知識資産
知識資産とは、社員一人ひとりが持つ業務知識やノウハウ、成功・失敗の経験などの無形資産を指します。これは企業にとって非常に貴重な財産であり、目に見える設備や商品とは異なり、社員が退職や異動すると簡単に失われるリスクがあります。
特に暗黙知は、形式知へと変換し、ナレッジとして全社で共有・継承することで、生産性向上や業務の属人化防止、競争力の強化につながります。
ナレッジマネジメント導入のメリット

ナレッジマネジメントを導入することで、知識の属人化を防ぎ、業務の標準化やミスの削減、教育コストの削減といった多くのメリットが期待できます。ここでは、導入によって得られる具体的な効果について紹介します。
属人化の解消
ナレッジマネジメントの導入は、業務の属人化を解消するうえで非常に有効な施策です。熟練社員が持つ暗黙知を形式知に変換し、社内で共有・蓄積することで、特定の社員に依存する業務や意思決定を減らすことができます。
その結果、業務の改善点や新たなアイデアが生まれやすくなり、担当者が不在の際もスムーズな引き継ぎが可能となるため、組織全体の生産性や継続性の向上に大きく貢献します。
ベストプラクティスの共有
ナレッジマネジメントを導入し、ベストプラクティスを共有することによって業務の標準化が進む点も大きなメリットのひとつです。誰でも一定の品質で作業を遂行できるようになるだけでなく、過去の失敗事例やトラブル対応の情報を蓄積・共有により、同じミスの再発防止や業務品質の向上につながります。
さらに、情報の可視化とアクセス性の向上により、必要なナレッジを迅速に取得でき、意思決定のスピードも向上させることができます。
人材育成コストの削減
ナレッジマネジメントを導入することで、社内に蓄積された知識やノウハウを整理・共有でき、人材育成にかかるコストの削減が可能です。OJTや集合研修だけに頼らず、必要な情報を社員自身が迅速に取得できる環境を整えられれば、教育にかかる時間や講師費用を抑えられ、育成効率向上にも寄与できます。
さらに、新人教育の負担を現場に集中させずに済むため、既存社員の工数を削減し、教育専任者を置く必要もありません。結果として、継続的な人材育成にかかる総コストの抑制につなげることが可能になります。
ナレッジマネジメントの代表的な手法

ナレッジマネジメントには目的や活用シーンに応じて複数の手法が存在します。ここでは、代表的な4つの手法について紹介します。
経営資本・戦略策定型
経営資本・戦略策定型とは、個人や組織が持つ知識を分析し、経営戦略に役立てる手法です。知識の分析結果をもとに戦略的な判断が可能になり、競合との差別化にも貢献します。
また、業務プロセスを見直すうえでも有効で、改善点の発見につながる点も大きな特徴です。
顧客知識共有型
顧客知識共有型とは、顧客からのクレームや対応履歴などをデータベース化し、組織内で共有する手法です。対応情報を見える化することで、業務の属人化を防ぎつつ、顧客満足度と業務効率の両方を高める効果が期待できます。
あわせて、顧客との一連のやりとりをテキスト化できる「音声テキスト化」を活用することで、現場のナレッジ蓄積も容易になります。
ベストプラクティス共有型
ベストプラクティス共有型は、優秀な社員の知識やノウハウ、思考法を組織全体で共有する手法です。属人化を防ぐと同時に、全社員のスキルを均質化することで、教育コストや研修工数の削減が見込めます。
さらに、成功事例やノウハウをヒアリングし、電子マニュアルや社内Wikiとして体系化することにより、継続的な業務改善や人材育成への活用も可能となります。
専門知識型
専門知識型とは、組織に蓄積された専門的な知識や業務ノウハウをデータベース化し、ネットワークを通じて誰でも簡単に検索・活用できるようにする手法です。問い合わせが多い内容をFAQとして整理し、AIチャットと連携すれば、迅速かつ正確な対応が可能となります。
これにより、業務効率や対応品質の向上、従業員の負担軽減、ひいては顧客満足度の向上につなげることが可能になります。
ナレッジマネジメントの導入から実践までの5ステップ

ナレッジマネジメントを実践するには、段階的な導入が欠かせません。ここでは、導入時の目的設定から評価・改善までを5つのステップに分けて紹介します。
目的の明確化
ナレッジマネジメントを導入する際は、まず目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは施策がぶれやすくなり、効果的な運用につながりません。
コールセンター業務の効率化を目指すのであれば、属人化を防ぐためにFAQを整備するなど、実際の業務課題に応じた目標を設定しましょう。明確な目的と目標を立てることで、実践に向けた準備につなげられます。
必要な情報の洗い出し
ナレッジマネジメントの目的にあわせて、ナレッジとして集積する情報を洗い出します。例えばコールセンター業務でFAQを整備するなら、問い合わせへの対応事例やトラブル対処法、優れたオペレーターの対応ノウハウなどを集約するなどといったことが挙げられます。
このように、目的に沿って必要な情報を的確に洗い出すことで、ナレッジの有効活用と定着につながる基盤を整備できます。
手法と運用方法の決定
続いて、ナレッジマネジメントの手法と運用方法を選定します。先に紹介した「経営資本・戦略策定型」や「顧客知識共有型」などのなかから、最も適した方法を選択します。
あわせて、データベース型ファイルサーバや社内SNS、オフィスソフトなどのツールのなかから、業務との親和性や運用負荷を考慮し、最適なものを選ぶとよいでしょう。業務に無理なく組み込める仕組みを整えることで、継続的な活用と成果の最大化が見込まれます。
社内活用と定着の推進
その後、決定したナレッジマネジメントの手法を社内で活用・定着させるフェーズに入ります。業務プロセスへのスムーズな組み込みには、社員の理解と協力が欠かせません。
そのためには、ナレッジ共有の目的やメリットを周知し、ツールの使い方や運用ルールを丁寧に教育・サポートする体制が必要です。使いやすく継続的に利用できる仕組みを整えることで、ナレッジの浸透が進み、組織全体の情報活用力を高められます。
継続的な評価と見直し
ナレッジマネジメント導入後は、継続的な評価と見直しが求められます。導入自体が目的化すると、知識やノウハウが業務に活かされず形骸化する恐れがあります。
定期的なアンケートやITツールの刷新を通じて運用状況を把握し、課題を洗い出して改善につなげることが重要です。こうした継続的な改善により、ナレッジ活用の意識が高まり、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。
まとめ

本記事では、ナレッジマネジメントの基本的な考え方や代表的な手法、導入ステップについて紹介しました。
ナレッジマネジメントは、知識を社内で共有・活用し、生産性や人材育成の向上を図る経営手法です。業務の属人化を防ぎ、組織全体の学習力を高める効果も期待できます。この取り組みをより効果的に進めるには、AIを活用した仕組みの導入も有効です。
オプテージでは、AIを活用したチャットボットサービス「Enour AI ChatSupport(AIチャット)」を提供しています。このサービスを利用すると、お客様からの様々な問い合わせ内容を自動的に記録・保存することができます。
さらに、蓄積された問い合わせデータから、よくある質問への対応をナレッジ化したり、問い合わせ内容の傾向を分析したりすることが可能となります。
ナレッジマネジメントの導入にお悩みの方は、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





