
- 公開日:2024年03月22日
- 更新日:2025年10月23日
SSO(シングルサインオン)とは?仕組みと導入メリット・デメリットを解説

クラウドサービスの普及やテレワークの拡大を背景に、SSO(シングルサインオン)への関心が高まっています。複数のIDやパスワードを管理する負担を減らし、利便性とセキュリティを両立できる仕組みとして導入が広がりつつありますが、コストやリスクも伴うため慎重な検討が欠かせません。
本記事では、SSOの仕組みや方式ごとの特徴、導入メリットとデメリット、選定・運用時に押さえるべきポイントを解説します。
SSO(シングルサインオン)とは?
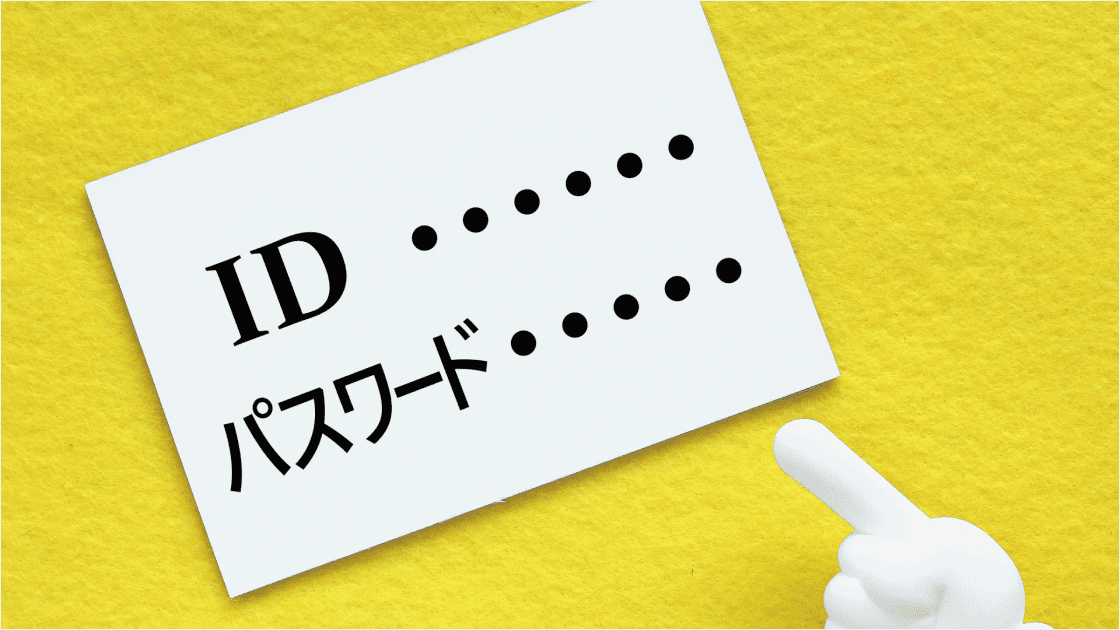
SSO(シングルサインオン)とは、一度のログイン認証で、複数のシステムやクラウドサービスにアクセスできる仕組みです。
従来はサービスごとに異なるIDやパスワードを管理する必要があり、ユーザーにとって大きな負担となっていました。
SSOを導入すると、複数サービスへのログイン時に入力を省略できるため利便性が大幅に向上します。さらに、管理すべき認証情報の数が減ることで、アカウント管理やパスワード再発行対応といったシステム管理者の運用負担も軽減されます。
近年はクラウド化やテレワーク拡大により利用するアプリケーションが増加し、管理の煩雑さが問題となるなか、SSOはセキュリティ強化と業務効率化を同時に実現できる手段として注目を集めています。企業や行政サービスなど幅広い分野で導入が進んでおり、今後もさらに普及の加速が見込まれます。
SSOの仕組み

SSOでは、実際にどのような認証が行われているのでしょうか。ここでは、認証の流れや従来方式との違いに加えて、ログイン状態を維持するための仕組みについて解説します。
SSOの認証フロー
SSOの認証フローでは、ユーザーが一度ログインすると、その情報を認証サーバ(IdP)が確認し、「本人である」と証明を発行します。この証明が各サービスに共有されることで、以降はパスワードを入力し直すことなく、スムーズに利用でき、ユーザーは複数のシステムを切り替えても途切れることなく作業を続けられます。
システム管理者にとっても、アクセス権限をまとめて管理できるため、セキュリティの強化や運用効率の向上につながります。さらに、パスワード忘れや入力ミスによるトラブルを減らせる点も大きなメリットです。
従来の認証方式との違い
従来の認証方式では、サービスごとに個別のIDとパスワードを設定し、毎回ログインする必要がありました。そのためパスワード管理の負担が大きく、パスワードを忘れたり、複数のサービスで同じパスワードを使い回したりすることにより、セキュリティリスクも高まっていました。
一方、SSOは認証情報をまとめて管理する仕組みです。一度のログインで複数のサービスにアクセスできるため、「サービスごとに入力する方式」から「一度の認証で利用可能な方式」へと進化しました。
これにより、ユーザーは利便性を実感でき、システム管理者はセキュリティと運用効率を両立できるようになります。
セッション情報やトークンの管理について
SSOでは、一度ログインした状態を維持しながら複数のサービスを利用できる点が特徴です。その裏側では「ログイン済みであること」を確認するための仕組みが動いており、これを支えるのがセッション情報やトークンと呼ばれるデータです。
例えばブラウザーに保存されるセッションCookieや、認証サーバから渡されるIDトークンが代表例で、これらがあることで追加のパスワード入力を省略できます。ただしセッションが有効な間は誰でもアクセスできてしまうため、一定時間で切れる仕組み(セッションタイムアウト)や、多要素認証と組み合わせることが安全な運用には欠かせません。
SSOの主な方式と特徴

SSOにはいくつかの実現方式があり、それぞれ仕組みや得意とする分野が異なります。ここでは代表的なSAML認証方式、OIDC方式、リバースプロキシ方式の特徴を紹介します。
SAML(Security Assertion Markup Language)認証方式
SAML認証方式は、異なるサービス間で安全に認証情報をやり取りできる標準規格です。ユーザーが一度ログインすると、認証サーバ(IdP)が「この人は本人である」という証明を発行し、それを各サービス提供者(SP)に渡すことで利用が可能になります。XMLをベースとした仕組みのため、クラウドサービスや企業間システムのように複数ドメインにまたがる環境でも活用しやすい点が特徴です。
また、SAMLではユーザーの「部署」「役職」「権限」といった属性情報も扱えるため、サービスごとにアクセス範囲を細かく制御できます。この柔軟性が評価され、Google WorkspaceやMicrosoft 365など多くのSaaSで採用されています。
OIDC(OpenID Connect)認証方式
OIDC(OpenID Connect)認証方式は、OAuth 2.0を拡張して「誰がログインしているのか」を確認できるようにした認証の仕組みです。OAuth 2.0自体は利用権限を与えるための仕組みであり、本人確認はできません。しかしOIDCを用いることで一度のログインで複数の関連サービスを安全に利用できるようになります。代表的な例としては、「Googleでログイン」や「Facebookでログイン」のボタンをクリックして、自分のアカウント情報をもとに外部サービスへアクセスできるケースがあります。
OIDCでは「IDトークン」と呼ばれるデータが発行され、署名によって改ざんを防止します。暗号化は必須ではないものの、機密性を高めたい場合にはオプションとして利用することが可能です。この仕組みにより、ユーザーは複数のパスワードを持つ必要がなくなり、利便性の向上とパスワード管理リスクの軽減を同時に実現できます。
リバースプロキシ方式
リバースプロキシ方式は、ユーザーとアプリケーションの間に「中継役」となるサーバを置き、そのサーバが通信を制御・認証する仕組みです。ユーザーがサービスにアクセスすると、まずリバースプロキシが認証情報を確認し、問題がなければ「認証済み」を示すセッションCookie等を発行します。以降はそのCookieを利用することで、追加の認証を求められずにサービスを利用できます。
この方式はプロキシ配下のアプリにSSOを付与でき、アプリ側の大きな改修を伴わないケースが多いとされています。一方で、全ての通信がこのサーバを経由するため、ネットワーク環境の整備が前提となります。
SSO導入のメリット
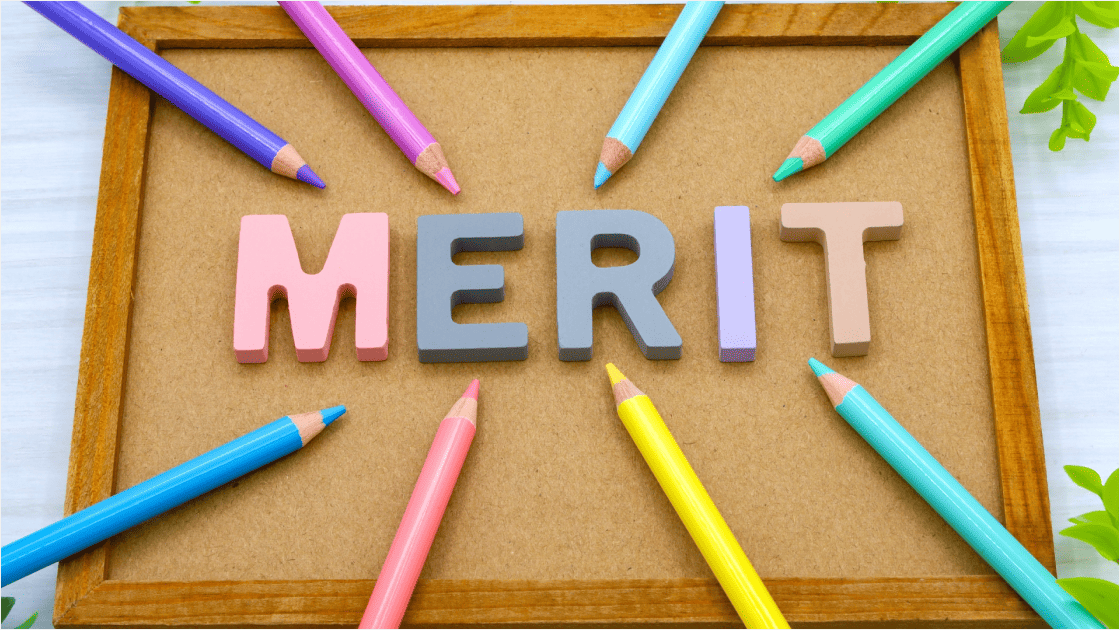
SSOの導入によって、ユーザーとシステム管理者の双方に多くの利点をもたらすことができます。ここでは、パスワード管理の負担軽減、セキュリティ強化、そしてIT運用効率の向上という三つの観点からメリットを紹介します。
パスワード管理の簡素化
SSOを導入する最大の利点の一つが、パスワード管理の負担を大幅に軽減できることです。従来はサービスごとに異なるIDとパスワードを記憶する必要があり、忘失や使い回しによるリスクも避けられませんでした。
SSOでは一度のログインで複数サービスを利用できるため、ユーザーは複雑なパスワードをいくつも記憶する必要がなくなります。その結果、パスワードに起因するトラブルが減少し、ユーザー自身のストレスや業務の中断を防ぐ効果も期待できます。
また、システム管理者にとってもユーザーごとのパスワード発行や定期的な更新対応が簡素化され、システム全体の管理性が向上する点も大きなメリットです。
セキュリティの強化
SSOを導入することで、セキュリティ面でも大きな効果が得られます。従来はサービスごとにIDやパスワードを作成・管理する必要があり、その結果としてパスワードの使い回しや紙・メモでの管理が発生し、情報漏えいのリスクを高めていました。
SSOでは一つのIDとパスワードだけで複数のサービスを利用できるため、ユーザーが複雑で強固なパスワードを設定したとしても、負担の軽減につながります。また、認証情報をやり取りする経路が減ることで、不正アクセスや漏えいのリスクをさらに抑えることが可能です。
利便性と同時に、認証基盤全体のセキュリティ強化につながる点も大きな魅力となっています。
IT運用効率の改善
SSOの導入により、アカウント管理そのものの効率化を大きく高められる点も見逃せません。従来はアプリケーションごとに利用者を追加・削除する必要があり、人事異動や組織変更のたびに複数のシステムを個別に更新しなければならず、手間とリスクが伴っていました。
SSOを利用すればアカウント情報を一元的に管理できるため、追加・削除や権限変更を一度の操作で全体に反映できます。ユーザーにとってはアクセス権限の反映が迅速になり、組織変更、異動直後から業務をスムーズに始められるという利点があります。
一方でシステム管理者にとっては、アカウント棚卸しの自動化や権限管理の透明化が進み、不正利用や権限の放置を防ぎやすくなります。これにより日常的な負荷を抑えつつ、システム全体の健全性を維持できます。
SSO導入のデメリット
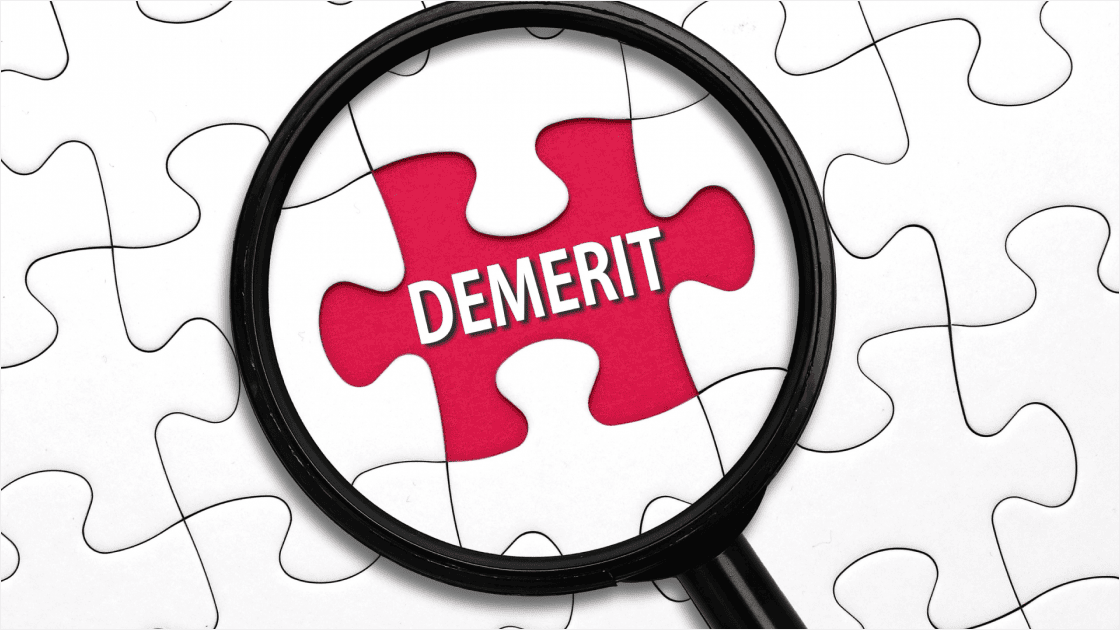
SSOは利便性やセキュリティ強化に役立つ一方で、導入にはいくつかのデメリットやリスクも伴います。ここでは、障害発生時の影響や認証情報漏えいの危険性、さらにコスト面や対応範囲の制約といった、導入に伴う注意点を紹介します。
障害発生時の影響
SSOは利便性の高い仕組みですが、全てを一元化するがゆえのリスクも存在します。特定の認証システムに障害が発生すると、その仕組みに依存する全てのサービスやアプリケーションにアクセスできなくなり、業務が大きく滞る可能性があります。特に経営に直結する基幹システムや取引システムが利用不可となれば、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。
そのため、導入時には全システムを完全にSSOに依存しない設計が重要です。例えば重要システムは個別の認証を残す、バックアップの仕組みを用意するなど、障害時の影響を最小化するための備えが求められます。
認証情報漏えいのリスク
SSOは便利な仕組みですが、使い方を誤ると大きなリスクを招く可能性があります。特に注意すべきは認証情報の漏えいです。IDやパスワードが流出すると、連携している複数のシステムやサービスに一度に不正アクセスされるおそれがあり、被害の規模は従来方式よりも大きくなりがちです。
このようなリスクを軽減するには、IDやパスワードを適切に管理するだけでなく、多要素認証や二段階認証と組み合わせて利用することが重要です。あわせて定期的な見直しなどを行うことで、より安全な運用が可能になります。
導入・運用コスト
SSOを導入する際には、利便性やセキュリティ強化といったメリットの裏で、コスト面の課題も考慮する必要があります。システムを導入するには初期費用やライセンス料がかかり、クラウド型かオンプレミス型かによって価格帯に大きな差が生じます。また、運用を続けるための保守費用や管理体制の整備も欠かせません。利便性ばかりを優先して検討すると、想定以上のコスト負担につながる恐れがあります。
そのため、導入前には自社の利用規模や求める機能を整理し、サービス内容と費用のバランスを見極めることが重要です。長期的な運用コストも含めた総合的な判断が求められます。
対応範囲の制約
SSOの導入時は、適用範囲に限界がある点を理解しなければなりません。特に既存の業務システムや古いアプリケーションはSSOに対応していないことが多く、対応させるには追加の開発やコストが発生することがあります。さらに、一部のクラウドサービスでもSSOが利用できないケースがあり、その場合は従来通り個別のログインが必要となります。
そのため、全てのシステムを一度に統合しようとするのではなく、優先度を考慮しながら段階的に導入を進めることが重要です。どうしてもSSOが使えないサービスについては、ID・パスワード管理ツールを併用するなど、認証負担を軽減する工夫を取り入れるとよいでしょう。
SSOと類似サービスの違い・使い分け
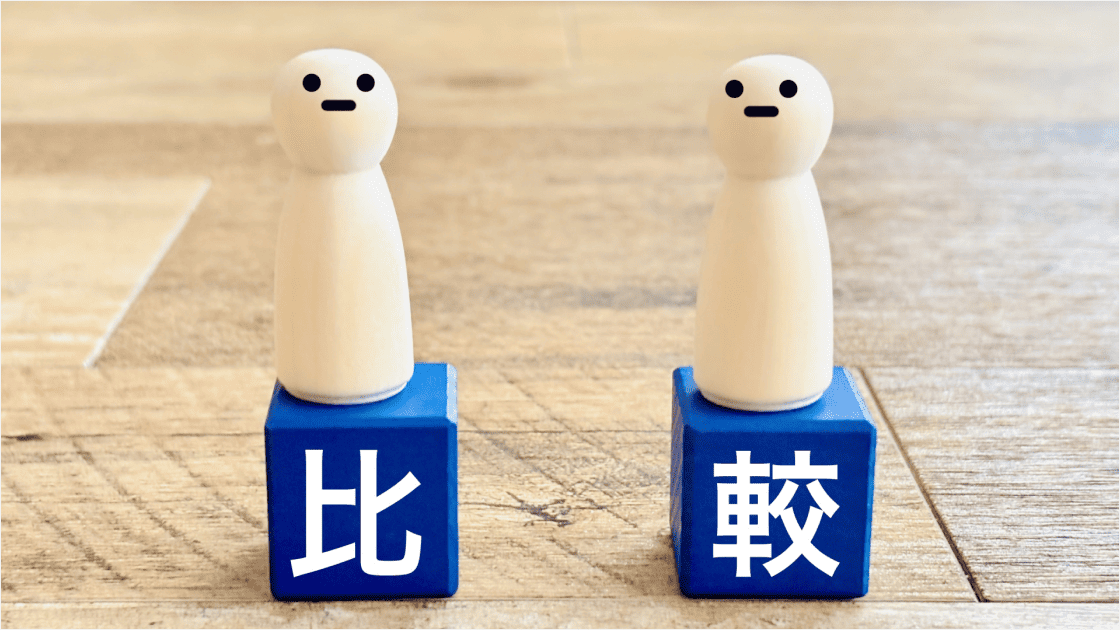
SSOに関連する仕組みとして、IDaaSやフェデレーション、MFA、パスワードレス認証などがあります。ここではその一つひとつの特徴や違いを紹介します。
IDaaS(Identity as a Service)
IDaaS(Identity as a Service)は、クラウド上でID管理と認証を提供するサービスで、SSOをはじめ、多要素認証やアクセス制御など幅広い機能を備えています。SSOが「一度のログインで複数のサービスを利用できる仕組み」であるのに対し、IDaaSはユーザーのIDライフサイクル管理や権限付与・削除といった運用全般を包括的に扱う点が特徴です。
例えば、人事異動に伴うアカウント作成や削除を自動化できるため、管理負担やセキュリティリスクを大幅に軽減できます。代表的なサービスとしては、世界的に利用されているOktaやOneLoginなどがあります。
フェデレーション(federated identity)
フェデレーション(federated Identity)は、異なる組織やドメイン間で認証や権限を共有できる仕組みです。例えば、グループ会社や取引先のシステムを利用する際に、自社のアカウントでそのままログインできるのは、フェデレーションによる認証連携の一例です。
この仕組みは、SAMLやOIDCといったプロトコルを利用して信頼関係を構築する点が特徴です。
SSOが「同じ組織内で複数サービスをまとめて利用する仕組み」であるのに対し、フェデレーションは「組織をまたいで認証を連携する仕組み」である点が大きな違いです。
多要素認証(MFA)
多要素認証(MFA)は、従来のIDとパスワードに加えて別の要素を組み合わせ、本人確認を強化する仕組みです。追加要素には、スマートフォンに送られるワンタイムパスコードや、指紋・顔認証といった生体情報などが用いられます。
SSOは一度のログインで複数のサービスを利用できる便利な仕組みですが、単一の認証基盤に依存するため、不正侵入が成功した際の影響が大きいという課題があります。そこで、SSOとMFAを併用することで、利便性を維持しつつセキュリティを一段と高めることが可能になります。
実際の運用においても、この組み合わせはよく利用されており、安全性確保のベストプラクティスの一つとされています。
パスワードレス認証
パスワードレス認証は、その名のとおり従来のパスワード入力を不要とする認証方式です。代わりに指紋や顔認証といった生体認証、もしくは物理的なセキュリティキーを用いて本人確認を行います。SSOが「一度パスワードを入力すれば複数のサービスを利用できる」仕組みであるのに対し、パスワードレスは「そもそもパスワードを使わない」点が大きな特徴です。これにより、パスワード忘れや使い回しによるリスクを根本から解消できます。
近年では、SSO基盤にパスワードレス認証を組み込み、利便性とセキュリティを両立させる導入事例も増えています。
SSOの導入ステップと選定ポイント

SSOを導入するには、事前の要件定義や方式選定に加え、段階的な導入プロセスと継続的な運用・保守が欠かせません。ここでは導入ステップと検討すべきポイントを解説します。
要件の整理
SSOを導入する際は、まず自社の業務環境や利用状況を整理します。Google WorkspaceやMicrosoft 365、Salesforceなどのクラウドサービスに加え、オンプレミスの業務システムも含めて対象アプリケーションを洗い出し、適用範囲を明確にします。
あわせて、利用ユーザーの規模によって必要な認証基盤の性能やライセンス費用が大きく変わるため、数十人単位か数千人規模かを把握することも重要です。また、セキュリティ要件についても事前に整理しておく必要があり、多要素認証(MFA)の導入要否や、ゼロトラスト環境への対応可否などを確認しておくことで、後のトラブルや追加コストを防ぐことができます。
認証方式の選定
自社の業務環境や利用状況を把握したら、それをもとに最適な認証方式を選びます。方式の優劣だけでなく、自社システムの構成や利用するアプリケーションとの相性を重視することが成功の鍵となります。
例えば、SAMLはSalesforceをはじめとしたクラウド型の業務アプリケーションで広く使われており、安定性を求めるエンタープライズ利用に適しています。これに対し、OIDCはGoogle系サービスやモバイルアプリとの親和性が高く、近年有力な選択肢となっています。また、リバースプロキシ方式は、既存の社内システムやSSO非対応アプリが多い場合に導入しやすいのが特徴です。
選定の際は、利用アプリケーションの対応状況、クラウド中心かオンプレミス中心かといった環境、求めるセキュリティ要件、さらにはコストや拡張性といった観点を整理し、総合的に検討することが推奨されます。
SSO導入プロセス
つづいて実際のシステム導入フェーズに進みます。最初のステップはPoC(概念実証)で、主要アプリケーションを対象に小規模でテスト導入を行い、実際の動作や利用体験を確認します。その後、全社展開に先立ち部門単位で段階的に導入し、ユーザーの操作感や運用負荷を検証します。
こうした準備を経て問題がなければ、本番導入として全ユーザーに展開し、既存のID管理システム(Active DirectoryやLDAPなど)と統合します。段階を踏むことでリスクを最小化し、スムーズな定着を図ることが可能となります。
運用・保守
SSOの導入は完了して終わりではなく、安定した運用と継続的な保守が不可欠です。
新しいアプリケーションを追加する際には迅速に連携設定を行い、既存システムとの整合性を保つ必要があります。また、利用状況をモニタリングし、ログイン動作や不審なアクセスを把握できる仕組みを整えることが重要です。特に不正アクセスの防止や法令・規制への準拠の観点から、監査ログを適切に取得・保存し、定期的に確認する体制が求められます。
さらに、障害発生時には迅速に対応できるサポート体制を確立することで、業務への影響を最小限に抑えられます。こうした運用・保守の仕組みを整備することが、長期的に安全で信頼できるSSO活用につながります。
まとめ

SSOは利便性やセキュリティ強化、運用効率の向上に大きく貢献する仕組みですが、導入にはリスクやコストも伴うため、十分な検討と準備が欠かせません。自社の業務環境やセキュリティ要件に合った方式を選び、段階的に導入しながら継続的に保守を行うことが成功のポイントです。
オプテージでは、AWSやAzureをはじめとするクラウドサービスや社内システムに対応した、シンプルかつスピーディーなSSOを提供する「GMOトラスト・ログイン」を展開しています。システムの利用状況に応じて3つの方式から選択でき、導入によりセキュリティと利便性の両立が可能です。
SSOに関してお困りのことがありましたら、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





