- 公開日:2020年02月12日
- 更新日:2025年09月24日
「ひとり情シス化」とは?その原因と課題、今すぐできる対策まで徹底解説

企業のIT環境を支える「ひとり情シス」が、いま多くの中小企業で常態化しています。IT人材不足やコスト制約が進むなか、業務の属人化やセキュリティリスク、対応遅延などの問題も深刻化しつつあります。
本記事では、ひとり情シス化が進む背景とその課題、対策を紹介します。
「ひとり情シス」とは?加速するIT人材不足の実態

「ひとり情シス」とは、企業の情報システム部門において、ネットワーク管理やクラウド運用、PC対応、トラブル対応などの業務を実質的に1人で担う担当者、あるいはその体制を指す言葉です。
特に中小企業では、IT人材の採用難や人件費の抑制といったリソース上の制約から、やむを得ずひとり情シス体制を取らざるを得ないケースが増えています。その結果、1人の担当者に過剰な業務負担が集中し、運用の安定性やセキュリティ面でのリスクも高まりやすくなっています。
このような状況は近年ますます常態化しており、IT人材不足の加速とあわせて、多くの企業で「ひとり情シス」は避けられない課題として認識されつつあります。
なぜ中小企業で「ひとり情シス化」が進んでしまうのか
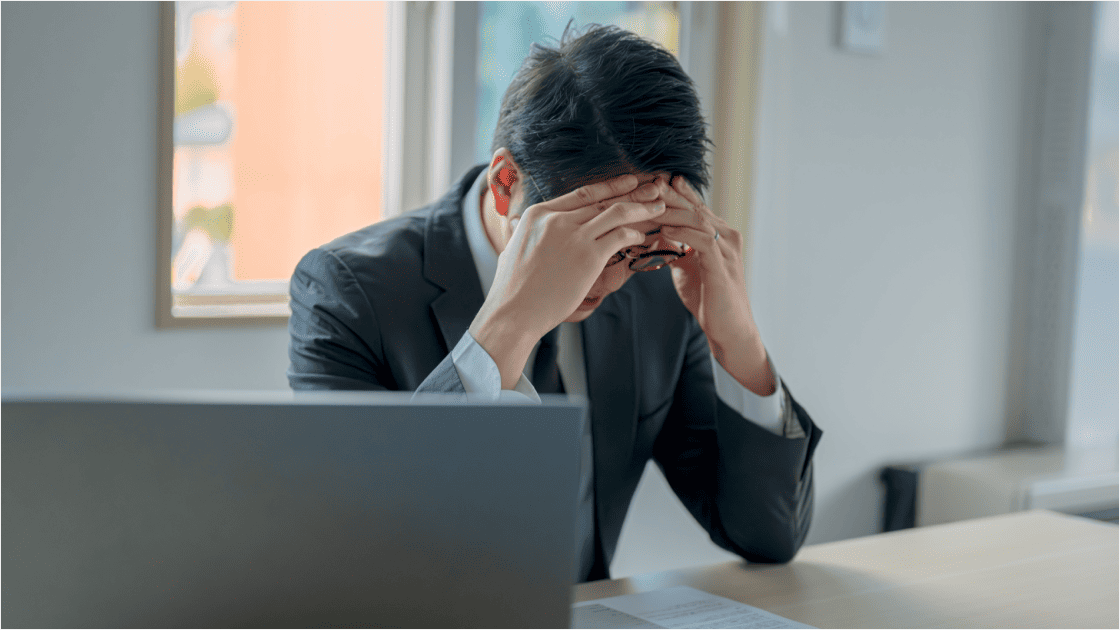
中小企業における「ひとり情シス化」の背景には、IT人材の確保や育成の難しさ、外注化の進展、クラウド活用による業務の見えにくさ、経営層がIT部門をコスト要因と見なす傾向にあるなど、複数の要因が複雑に絡み合っています。
ここでは、主な4つの要因を取り上げ、それぞれが「ひとり情シス化」を招く構造を整理します。
IT人材の確保・育成の難しさ
企業規模によって採用環境には差があり、中小企業では専任の情報システム担当者を十分に確保するのが難しいケースも少なくありません。さらに、ひとり情シス体制では、たとえ優れたスキルを持つ担当者であっても、ネットワーク管理・ヘルプデスク対応・クラウド運用など幅広い業務に日々追われ、自らの専門性を高めるための時間や余力を確保しにくいのが実情です。
その結果、担当者がスキルを活かしきれず、将来のキャリアや業務の持続可能性に不安を感じ、より良い労働環境や支援体制を求めて転職を検討する動きが出てきます。企業側としても、新たな人材の採用が難しいなかで業務継続のリスクが増し、慢性的な人材不足が原因で担当者の業務負担が増大し、それがさらに人材の離職を招くという悪循環に陥りやすくなっています。
IT人材不足について以下の記事でくわしく解説しています。
関連記事:IT人材不足の深刻化にどう立ち向かう?企業が直面する課題と解決策
情報システム業務の外注化によって進むノウハウの空洞化
人材確保が難しいなかで、中小企業では情報システム業務を外部ベンダーに委託する「外注化」が進んでいます。外注により日常的な運用負担は軽減されるものの、社内に専任担当者を置かなくなることで、緊急時の即応力が低下したり、業務ノウハウが社内に蓄積されにくくなったりする副作用も生じます。
外注先に頼りきりの運用が続けば、業務の背景や手順が社内で共有されず、ITナレッジが組織に根付かない「ノウハウの空洞化」が進行する恐れがあります。その結果、社内の情報システム業務は一部の担当者の兼務でまかなわれるようになり、1人または極少人数による運用の常態化につながる恐れがあります。こうした構造が、ひとり情シス化をさらに後押ししてしまうのです。
クラウドサービス活用の普及と"専任不要"という誤解
近年、クラウドサービスやパッケージソフトの普及により、企業のITシステム導入や運用は大幅に容易になってきました。従来は社内でシステムをスクラッチ開発し、多くの技術者で管理していた作業も、今ではクラウドサービスによって自動化・簡略化されています。
例えば、サーバ管理やバックアップ作業がクラウド上で完結することで、社内の情シス担当者が手を動かす場面は減少傾向にあります。その結果、情シスの業務が"目に見えにくく"なり、「ひとりでも対応できている」「専任を置かなくても支障はない」といった誤った認識が社内に広まりやすくなります。
この見た目上の安定が、兼任体制やひとり情シス体制を放置してしまう要因になっているのです。
IT部門が"コスト部門"と見なされる構造的課題
システムのオープン化やクラウド化によって、目立ったトラブルが発生しにくくなると、IT部門の活動は「問題がない」ものと見なされ、経営層から注目されにくくなります。その結果、「現状維持で十分」と判断されやすくなり、人員や予算の増強が後回しにされやすくなります。
加えて、情報システム部門の業務は売上への直接的な貢献が見えづらく、成果も定量化しにくいため、他部門に比べてコスト削減の対象となりやすいという構造的な課題もあります。こうした状況が続くと、IT体制の強化や人材育成への投資が停滞し、結果としてひとり情シス体制が固定化してしまうリスクが高まるのです。
「ひとり情シス化」が企業にもたらす問題点

ひとり情シス体制が常態化すると、業務の属人化や対応遅延、セキュリティリスクの高まりなど、企業全体に深刻な影響を及ぼしかねません。ここでは代表的な5つの課題を取り上げ、それぞれのリスクと背景を解説します。
業務過多と属人化
担当者が1人でネットワーク管理やトラブル対応、資産管理など多岐にわたる業務を抱える状況では、常に業務過多になりがちです。その結果、作業ミスや対応の遅延、業務品質の低下に加え、精神的な負担が重くのしかかります。
さらに、業務知識やノウハウが特定の担当者に集中すると、引き継ぎが難しくなり、担当者の不在時には業務が停滞しやすくなります。こうした属人化のリスクが高まることで、業務の継続性や組織全体の安定性に悪影響を及ぼす可能性があります。
緊急時の対応が困難になる
システム障害やネットワークダウンなど、迅速な対応が求められる場面では、対応可能な人材が1人しかいないことが大きな障壁となります。担当者が離席中、または別の作業中の場合、初動が遅れ、被害が拡大するおそれがあります。
こうした初期対応の遅れは、取引先や顧客の信用失墜、業務停止による損失といった深刻な影響につながりかねません。
セキュリティ対応の限界
日々の業務に追われるなか、セキュリティ対策の優先順位が後回しになってしまうのも大きな課題です。例えば、パッチ適用の遅れ、アクセス権限の見直し不足、ログ監視の不徹底などが発生しやすくなります。
加えて、1人では最新のセキュリティ動向や脅威への対応スキルを継続的に学ぶ時間も限られ、ゼロデイ攻撃のような未知の手口に対応しきれないケースも。結果的に、情報漏えいや外部との取引停止といった重大な影響を企業全体にもたらす可能性があります。
ワークライフバランスの崩壊
担当業務に日々追われるなかで、障害対応や緊急トラブルへの対応までを1人で担う体制は、担当者に過度な負担を強いることになります。こうした環境では、長時間労働や休日・夜間対応が常態化しやすく、慢性的な疲労や心身の不調を引き起こす要因にもなります。
さらに、十分な休暇が取れず私生活との両立が難しくなることで、モチベーションの低下や離職リスクが高まり、結果としてIT部門全体の機能不全や組織全体への悪影響につながる可能性があります。
情シス担当者が抱える孤立と成長停滞
孤立感も、ひとり情シスの大きな課題のひとつです。業務判断や改善提案を常に1人で行わなければならない環境では、精神的な負荷が高まり、周囲との協働機会が乏しいことで自己流の対応が定着しがちです。
また、外部との交流や最新技術に触れる機会も限られ、技術的なスキルアップやキャリア形成の面でも停滞しやすくなります。加えて、日々の努力や成果が見えづらい職種であることから、周囲からの理解や評価も得にくく、担当者の意欲低下を招く原因にもなります。
こうした状況が長く続けば、将来への不安やキャリアの限界を感じた優秀な人材ほど、より良い環境を求めて転職を検討する可能性が高まるでしょう。
ひとり情シス問題の対策とは
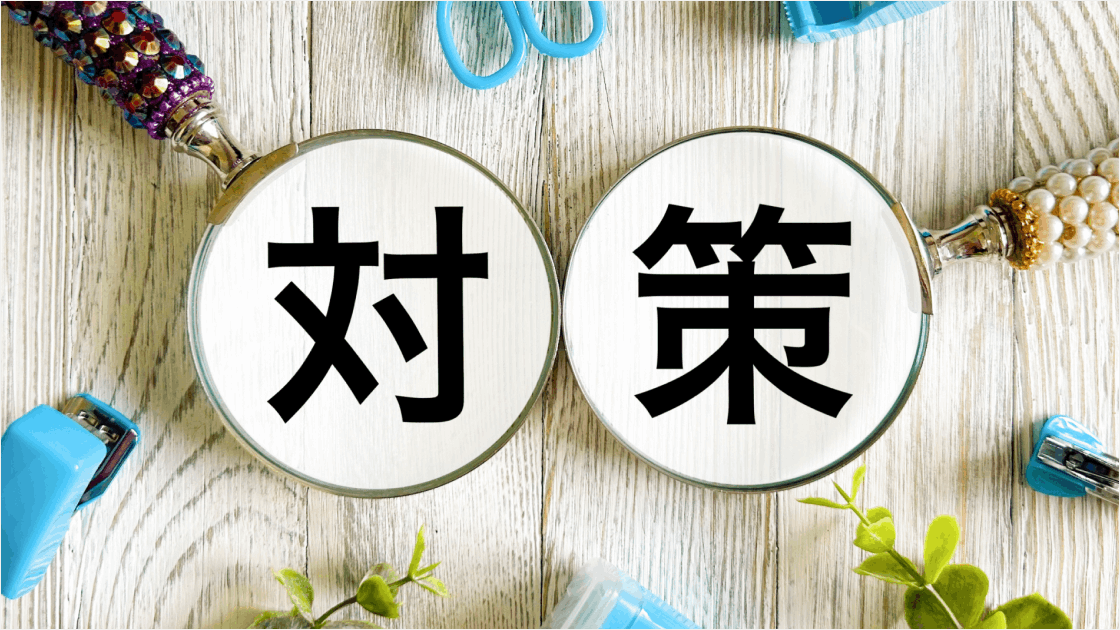
ひとり情シスによる業務の集中や属人化を防ぐには、業務負荷の軽減と体制そのものの見直しが欠かせません。ここでは、定型業務の自動化や作業実績の可視化、経営層との連携、複数人体制の構築、外部サービスの活用といった対策を紹介します。
定型業務の自動化
ひとり情シス体制の負担を軽減するには、定型業務の自動化が効果的です。RPAやVBAといった自動化ツールを活用することで、日々のルーティン業務にかかる時間と手間を大幅に削減できます。また、Slackなどの業務チャットと連携することで、他部門との情報共有もスムーズになります。
さらに、クラウドサービスを導入すれば、インフラ構築や保守作業の一部を自動化・簡素化できるため、比較的簡易な操作で効率的に業務を進めやすくなります。これにより、限られたリソースでも一定の品質を保ちながら運用を継続しやすくなります。
日々の作業実績の記録
情シス担当者の業務には、ユーザーからの問い合わせ対応や突発的なトラブル対応など、目に見えにくいタスクが数多く存在します。こうした日々の対応内容や所要時間を記録し、定期的に上司や関係者へ報告することで、実際の業務量や負荷を客観的に伝えることができます。
このような業務の"見える化"が進めば、作業の棚卸しや優先度の見直し、人員配置の改善といった施策が検討しやすくなります。また、担当者の努力や貢献が正しく理解されることで、評価や支援の体制づくりにもつながります。
経営層の理解と支援
情報システム部門の業務は日々の安定運用が中心となるため、成果が目に見えにくく、経営層が業務の実態を把握しにくいという課題があります。
そのため、情シス担当者が対応実績や課題を定期的に整理・共有し、業務の重要性を「見える化」することが有効です。具体的には、問い合わせ件数やトラブル対応に要した時間、改善提案の内容に加え、それによって得られた成果を報告することで、経営層の理解を促し、支援体制の強化や予算確保につなげることができます。
従業員のITリテラシー強化および育成
情シス担当者の業務負担には、従業員側のITリテラシー不足も大きく影響している可能性があります。たとえば、社内システムのパスワード再設定や簡単な操作トラブルなど、本来は従業員自身で解決できる問題まで情シスに依頼してしまうケースでは、担当者が本来注力すべき業務に割ける時間が奪われてしまいます。
このような状況を是正するためには、会社全体でのITリテラシー強化が有効です。研修や勉強会の定期開催、ナレッジ共有の仕組みづくり、さらにはIT活用を評価に組み込む人事制度などを通じて、従業員一人ひとりが「自分ごと」としてITを扱える環境を整えることが求められます。
加えて、将来を見据えて情シス担当者の育成と増員を進めることも、持続可能な体制づくりには重要です。教育機会やキャリアパスを明確にすることで担当者が専門性を高めやすくなり、結果的に企業全体のIT基盤を持続可能な形で発展させることにつながります。
外部の専門業者と連携した業務分散
外注化にはリスクもありますが、適切に外部の専門業者と連携すれば情シスの負担軽減につながります。
IT人材の確保が難しいなか、社内だけで情報システム業務をすべて担うのは現実的ではありません。そこで、マネージドサービスなど外部ベンダーへの外注によって定型的な運用・監視・保守を委託することで、社内担当者は新規システム導入やIT戦略立案など、企業成長に直結するコアな業務に集中できるようになります。
内製すべき業務と外注した方が良い業務を切り分けることによって、担当者の業務負荷を上げずに、ノウハウを社内に蓄積することが可能となります。
ひとり情シス問題の解決に成功した事例
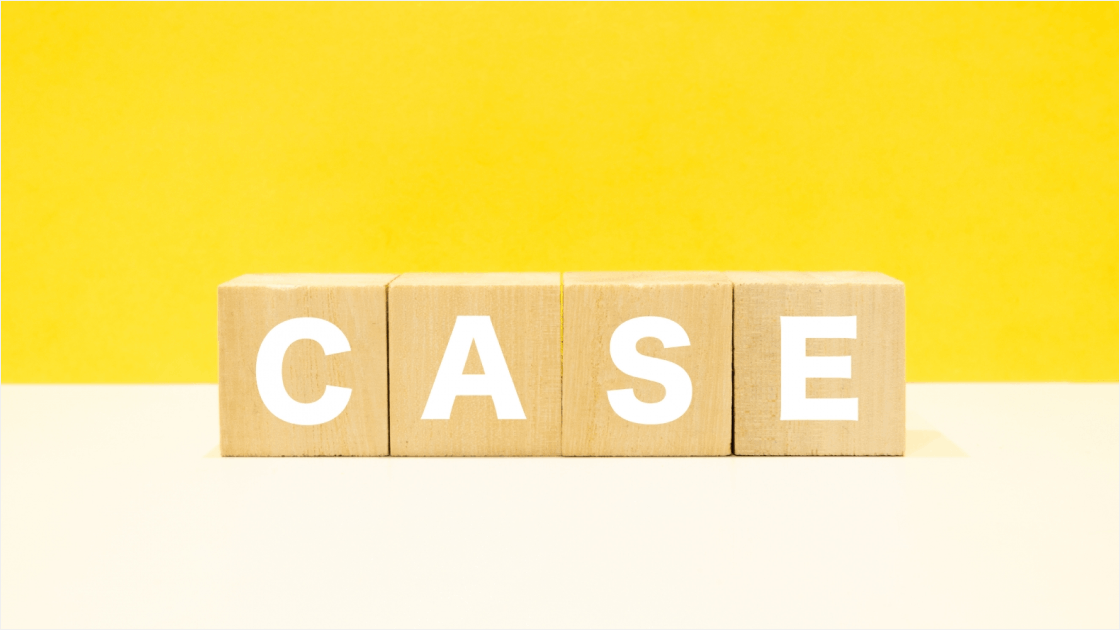
ひとり情シス体制が抱える課題は多岐にわたりますが、そうした状況を乗り越え、IT基盤の安定と業務効率化を実現した企業も少なくありません。ここでは、限られた人的リソースのなかで、BPOの活用やシステム導入により、業務の最適化と経営力強化に成功した事例をご紹介します。
事例1:全国展開する企業がBPOでIT運用を安定化
ペットショップや動物病院を展開するある企業では、全国に拠点を広げる中で、ひとり情シス体制による情報システム部門の人手不足が深刻な課題となっていました。例えば、新店舗の立ち上げやネットワークのトラブル対応、機器の設定など、IT関連業務がすべて一人に集中し、業務が回らない状況に陥っていました。
この課題に対し、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を導入し、ネットワーク設計から現地作業、保守対応までを一括で委託する体制を構築しました。図面作成、資材手配、問い合わせ対応も含めて業務を分担することで、担当者は本来の企画や改善業務に専念できるようになり、全社のIT環境も安定化しました。
事例2:セルフオーダー導入で業務効率と売上が向上
地元の名産を利活用したカフェを運営するある企業では、慢性的な人手不足と回転率の向上が課題となっていました。様々な視点から検討を重ねた結果、周辺の同業者でも導入が進んでいたセルフオーダーシステムを採用しました。
これにより、従業員の業務負担が軽減され、削減できた工数を新たなメニューの開発構想に充てることが可能となりました。さらに、注文から支払いまでをシステムで完結できるため回転率が向上し、導入前と比べて売上は約40%増加しました。また、接客に対して苦手意識を持つ従業員の心理的負担の軽減にもつながり、離職率の低下にも寄与しています。
今後は、経営戦略とIT化を一体的に進め、デジタル技術を業務改善に結びつけていく方針です。
まとめ

この記事では、ひとり情シス化が進む背景とその課題、対策を紹介しました。
ひとり情シス体制が長期化すると、業務の属人化や対応の遅れ、セキュリティリスクの放置に加え、担当者の精神的な孤立や疲弊が深刻化し、組織の安定的な運用に大きな影響を与える恐れがあります。
人材確保が難しい中小企業では、まずは業務を切り分け、内製すべきコアな業務は内製し、ノウハウを社内に残しつつ、それ以外の業務は外部リソースの活用が、実践的な解決策となります。
オプテージの「ITインフラコンサルティング」では、ひとり情シス特有の課題を可視化したうえで、クラウドの活用、業務分担の見直し、運用設計の改善など、企業の実情に即した具体的な解決策をご提案します。これにより、安定的で持続可能なIT運用体制の構築をトータルでサポートすることが可能です。
また、「クライアントセキュリティサービス ESET(イーセット)」は、高性能なウイルス対策機能に加え、集中管理ツールや自動アップデート機能を備えており、情シス担当者の作業負担を大幅に軽減します。中小企業でも導入しやすく、端末のセキュリティ強化と業務効率化を同時に実現できます。
ITに関してお困りのことがありましたら、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





