- 公開日:2025年08月05日
バックキャスティングとは?未来から逆算する思考法をビジネスに取り入れよう
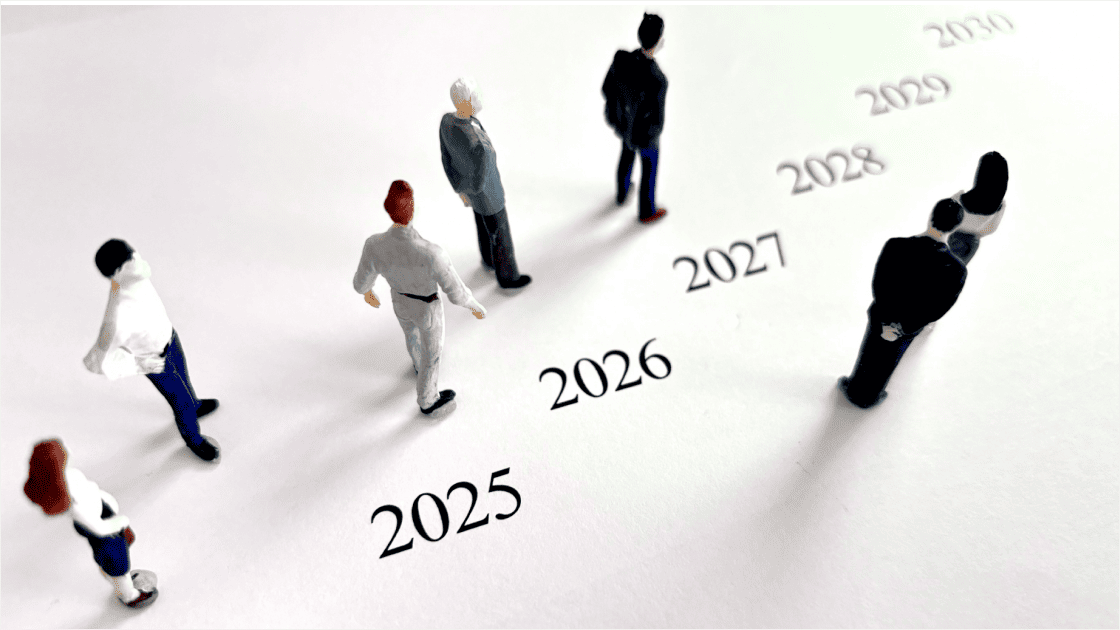
不確実性の高い現代において、理想的な未来から逆算してアプローチをかける「バックキャスティング」に注目が集まっています。SDGsはもちろん、企業の中長期的な戦略策定や組織改革にも役立てられるなど、企業経営にも活用できるのが特徴です。
本記事では、企業が知っておきたい思考法「バックキャスティング」について解説します。フォアキャスティングとの違いやビジネスへの活用メリット、実践手順なども解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
バックキャスティングとは?

バックキャスティングとは、理想とする未来の状態から逆算して「今すべきこと」を導き出す思考法です。設定したゴールに向けて「何年までに」「どのような取り組み」を行うべきかを段階的に設計していきます。
長期視点の国家戦略にもこの手法が活用されています。 例えば国立環境研究所が提案した「日本低炭素社会シナリオ」は、"2050年までに温室効果ガスを1990年比で70%削減し、豊かで誇りのもてる低炭素社会を構築することは可能である"とする未来像を設定し、そこに至る道筋をバックキャスティングによって描いた事例です。
バックキャスティングは、長期視点が求められるSDGs関連の施策や経営戦略との相性が良く、実現可能性の高いアクションを描ける点が特徴です。
フォアキャスティングとの違い
フォアキャスティングは、バックキャスティングと対比的な思考法です。未来を起点とするバックキャスティングとは違い、フォアキャスティングは現在の状況を起点に将来の予測や計画立案を進めていきます。
フォアキャスティングは現時点での環境やトレンドを前提としているため、将来の状態をイメージするのはそれほど難しいことではありません。しかし、斬新な解決策にはつながりにくく、長期的な視点に立ったときには変化の激しい環境や技術を予測できず、適切な対策を講じられない可能性もあります。
一方で、バックキャスティングの場合は実現したい未来を先に描くため、実現に必要な取り組みや選択肢といったアイデアが生まれやすい思考法といえるでしょう。
ビジネスにおけるバックキャスティング活用のメリット
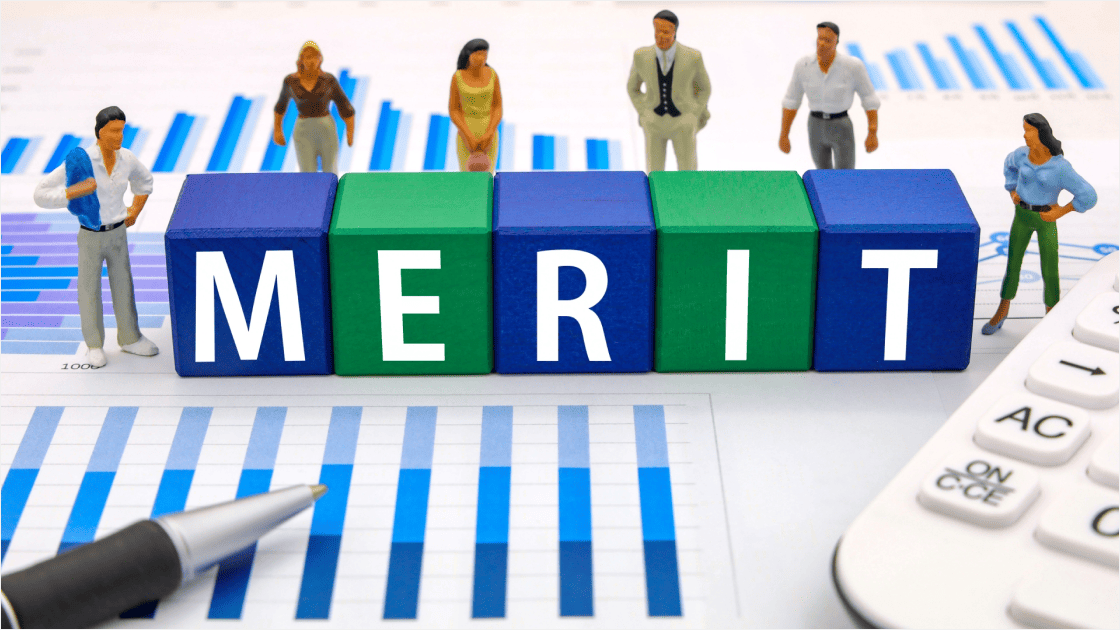
バックキャスティングは長期視点の戦略立案に役立つ思考法ですが、メリットはそれだけではありません。組織内のイノベーションを創出したり、社内外のステークホルダーとの信頼関係を醸成したりといったメリットがあることをご存じでしょうか。
理想的な未来から逆算する思考法によって、どのようなメリットが得られるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
自由で柔軟な発想が生まれやすい
バックキャスティングは「理想の未来」から逆算するため、現状にとらわれず自由な発想を促してくれます。例えば、「働く人全てがウェルビーイングを実感できる職場を作る」という未来像を掲げれば、業務フローや評価制度、オフィス環境まで見直すきっかけになるでしょう。
現状の延長線で考えないために多様な選択肢を検討でき、変化を前提としたアイデアを生み出せるなど、今までにない発想を創出する際に非常に役立つ思考法です。
長期戦略の構築や組織の変革に役立つ
バックキャスティングの実践では、中長期的なビジョンから逆算し、必要なアクションを短期的な行動目標に落とし込んでいきます。例えば、「2030年までに全事業所の再生可能エネルギー化を達成する」といった目標を立てた場合、実現に向けて必要となる新技術の導入や予算の確保、新規パートナーとの連携体制といった具体的な項目を洗い出し、準備することができます。
また、変化の激しい現代においては、環境の変化に柔軟に対応できる組織づくりが求められています。バックキャスティングは、理想の未来から逆算して現在の課題や必要な変化を可視化することで、組織がどのように変わるべきかを明確にし、段階的な変革を促すアプローチです。目指す姿が共有されることで社内の方向性が一致しやすくなり、変革への納得感や実行力も高まるでしょう。
ステークホルダーとの関係を強化できる
バックキャスティングにより設定した理想的な未来を実現するためには、従業員一人ひとりの協力が欠かせません。場合によっては、新しい知識やスキルを学ぶ「リスキリング」や、新規事業の立ち上げが必要になることもあります。バックキャスティングを通じて組織のビジョンと方向性が明確になれば、社内の一体感が生まれ、従業員のエンゲージメント向上も期待できるでしょう。
さらに、企業が未来志向の取り組みを進めていることを対外的に発信することで、顧客や投資家といった社外のステークホルダーからの信頼を得やすくなります。特に、環境・社会・企業統治(ESG)を意識した姿勢を示すことは、持続可能な成長への期待感やブランドへの支持を醸成することにもつながります。こうした信頼関係はESG投資を通じた資金調達や中長期的なパートナーシップ構築を後押しし、ステークホルダーとの関係をより強固なものにしていくでしょう。
バックキャスティングの実践手順
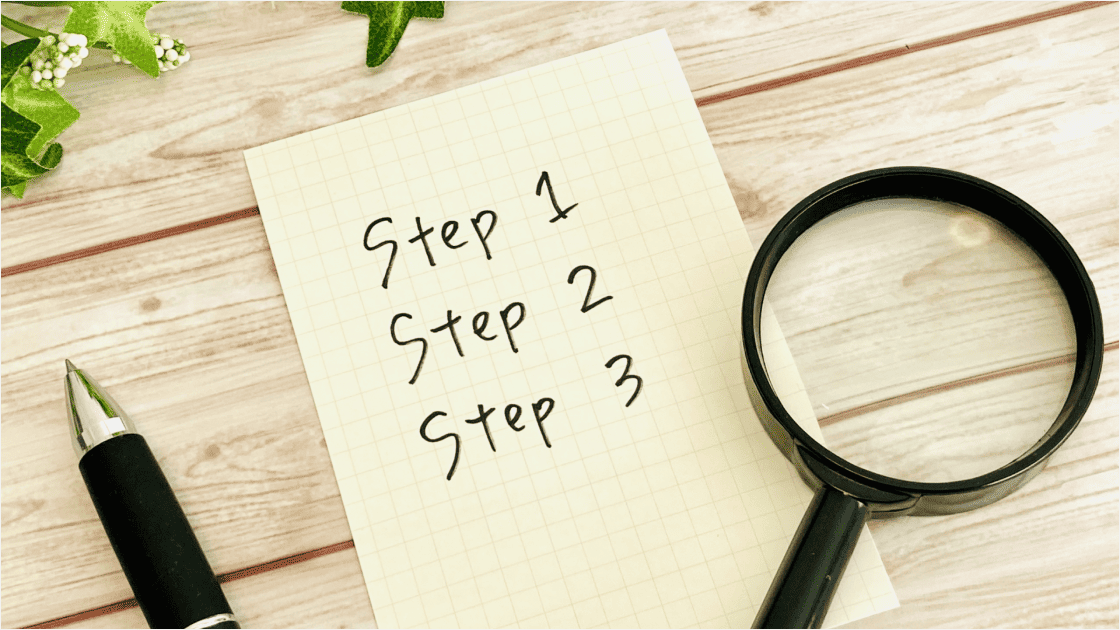
バックキャスティングを取り入れて、計画を進めていくためには、目標の設定をはじめ、計画立案や実施、改善を行っていくのが基本です。それぞれのフェーズを丁寧に行うことで、実現可能性の高い計画を策定できます。以下で詳しく見ていきましょう。
目指す未来像を明確化する
まずはどういった未来を目指していくのかを明確にします。例えば、「2030年に地域貢献度1位の企業になる」など、達成時期と具体的なゴールを設定しましょう。
このフェーズでは、社内外の情報収集や市場動向の調査を積極的に行うことが効果的です。総務省の「未来をつかむTECH戦略」や国土交通省の「2040年、道路の景色が変わる」といった政府機関の情報をはじめ、大手シンクタンクが公開している未来予測のレポートなどを参考に、企業が目指す未来像を明確にしていきましょう。
課題を可視化し、実行戦略を立案する
自分達が目指す未来像を具体的に描いたら、次はその実現に向けて現在の状況を多角的に分析します。具体的には、自社の内部要因(強み・弱み)や外部要因(機会・脅威)を評価し、現時点での課題やボトルネックを明確にしていきます。「SWOT分析」や、問題点・解決策を論理的に分析する「ロジックツリー」などのフレームワークを活用することで、課題の本質や成功を妨げる要因を可視化することが重要です。
そして、理想と現実のギャップを埋めるために、どのような変化・行動が必要なのか、具体的なストーリーを組み立てます。因果関係を整理していくことで実行戦略の精度が高まるため、時間をかけて練り上げていきましょう。
戦略を実行し、継続的に改善を図る
最後に、策定した実行戦略をもとに具体的な行動に移していきます。最初から完璧な実行は難しいため、中長期の視点で計画・実行・評価・改善の順に「PDCAサイクル」を回すのが効果的です。
ただ、技術や社会のあり方など変化の激しい昨今は、現場で早急な対応が求められるケースも少なくありません。そのような場合は、観察・方向づけ・意思決定・行動のループを任意の位置から回す「OODAループ」を活用することも検討しましょう。
OODAループについては、以下の記事で詳しく解説しています。ステップごとの詳細やメリット・デメリットなどもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:OODAループとは?PDCAとの違いやビジネスでの活用方法を解説
国内におけるバックキャスティングの実施事例
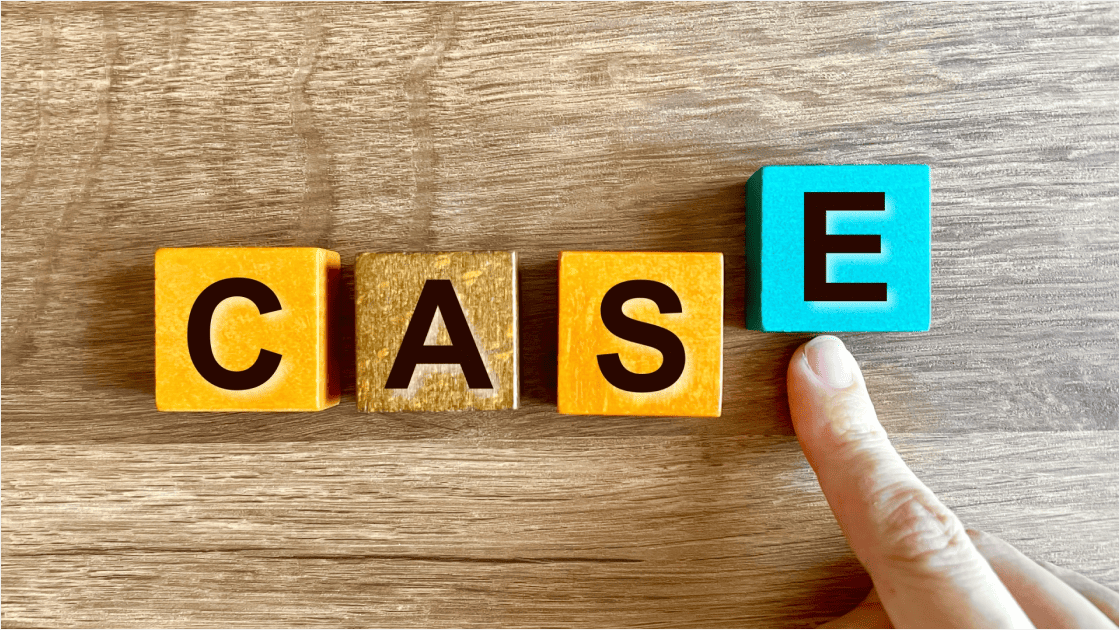
国内ではSDGsへの関心の高まりに伴い、持続可能な未来を見据えた長期ビジョンを掲げて、バックキャスティングのアプローチを取り入れる企業も増えています。
ここでは、実際に企業がどういった取り組みを行っているのか、自動車メーカーや小売流通会社などの事例を紹介します。いずれも理想の未来像を起点に、中長期の戦略や事業を展開しているので、自分達がバックキャスティングを活用して目標や計画に取り組む際の参考にしてみてください。
大手自動車メーカー
国内の大手自動車メーカーでは、2050年に向けた長期ビジョンを掲げ、6つの環境目標に取り組んでいます。例えば、「CO2排出ゼロ」の実現。将来的に製品や事業活動による環境負荷を限りなくゼロに近づけることを目指し、燃料電池自動車や電動車の開発・普及を推進しています。
さらに、生産段階でも、再生可能エネルギーや水素の活用で工場全体のカーボンニュートラル化を促進。こうした未来から逆算した技術革新と体制整備は、まさにバックキャスティングの思考を元にしたアプローチといえるでしょう。
大手小売流通会社
とある大手小売流通会社では、「環境・経済・社会」の観点からサステナビリティ経営を行っており、その中心にはバックキャスティングの考え方が見られます。例えば、再生可能エネルギーをお客様に届ける電力サービスを開始したことがあげられます。これは脱炭素社会の実現に向けた取り組みで、クリーンエネルギーの生産者と生活者をつなぐ新しい仕組みです。
また、同社が発行するクレジットカードの利用金額の一部を、福祉団体や障害者アーティスト支援に還元する制度も導入。こうした社会問題と経済活動の両立を実現する姿勢は、理想の未来から現在を逆算するバックキャスティングの実践といえます。
大手精密化学メーカー
カメラや印刷機器などを手がける大手精密化学メーカーでは、2030年に向けた中長期計画にバックキャスティングの思考を取り入れています。この計画では、健康・生活・働き方・環境などの社会課題を軸に、2030年のあるべき姿から逆算して目標を設定しているのが特徴です。
例えば、再生医療や高齢社会への対応といった未来のニーズを見据え、医療機器やヘルスケア分野の事業を拡大。また、脱炭素への対応として、製造プロセスで生じるCO2の削減やリサイクル素材の開発にも積極的に取り組んでいます。
現在の延長線ではなく、挑戦的な目標を掲げて段階的に取り組んでいる点は、バックキャスティングならではの有効性といえるでしょう。
バックキャスティングの注意点

バックキャスティングは意欲的なビジョンの実現に有効な一方で、実践方法を誤ると現実性に欠けた計画になってしまう恐れがあります。特に短期目標に活用したり、実現可能性を考慮せずに理想像を設定したりすると、求める成果が得られないかもしれません。
ここでは、バックキャスティングの実践にあたって注意しておきたい2つのポイントを解説します。
短期目標の設定には適していない
理想の未来から逆算して今やるべきことを明らかにするバックキャスティングは、長期的な戦略立案に適しています。そのため、数カ月から1年単位といった短期スパンの課題に対しては、必ずしも最適な思考法とはいえません。
例えば、営業目標の数値改善や業務フローの微調整といった課題には、現状から積み上げていくフォアキャスティングのほうが向いています。短期的な意思決定には即応性が求められるので、バックキャスティングでは準備や構想に時間がかかりすぎてしまうこともあるでしょう。
バックキャスティングとフォアキャスティングのどちらを取り入れるかは、目的や時間軸に合わせて選ぶことが大切です。
現実とかけ離れすぎると失敗のリスクが高まる
バックキャスティングでは、あるべき未来像を描くことが出発点です。ただし、その理想像があまりにも現実離れしていると、組織全体に混乱を招き、計画倒れに終わってしまう可能性があります。例えば、「10年以内に国内全ての配送を自動運転で行う」といった目標を掲げても、物流インフラや法規制への対応が整っていない状態では実現可能性は低いでしょう。
未来像を描く際には、社会の動向や企業の経営資源、ステークホルダーとの合意形成などを考慮し、挑戦性と実現可能性のバランスを取ることが重要です。バックキャスティングは企業の成長性を高める可能性を秘めていますが、理想を掲げるだけでなく、戦略の足元を固めることで目標達成に近づくことができます。
バックキャスティングの視点を取り入れ未来のビジネスを考えよう

理想的な未来から逆算することで、現状に縛られず本質的な課題・変化に向き合える思考法「バックキャスティング」。SDGsや脱炭素、ダイバーシティの推進といった持続可能な社会の実現が求められる今こそ、企業経営においても取り入れる価値があります。
実現可能性とのバランスを取りながら企業の理想像を描ければ、組織の方向性が明確になり、社員の共感や社外からの信頼を得ることにもつながるでしょう。また、変化の激しい時代を生き抜くためには、目の前の課題に向き合うだけでなく、柔軟かつ長期的な視点で未来を設計することが重要です。本記事で紹介したバックキャスティングをきっかけに、企業の進むべき道を考えてみてはいかがでしょうか。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。



