- 公開日:2025年04月21日
知らないと危険!サイバー攻撃の手口と企業が実施すべき具体的な対策とは

近年、ランサムウェアやフィッシング詐欺、DDoS攻撃などのサイバー攻撃がますます巧妙化し、金銭的損失や事業の停止といった深刻な被害が相次いでいます。特に、リモートワークの普及やクラウドサービスの利用拡大により、企業のセキュリティ対策の重要性が一層高まっている状況です。
本記事では、代表的なサイバー攻撃の手法や実際の被害事例、企業が今すぐ実施すべきセキュリティ対策について紹介します。
サイバー攻撃の主な種類
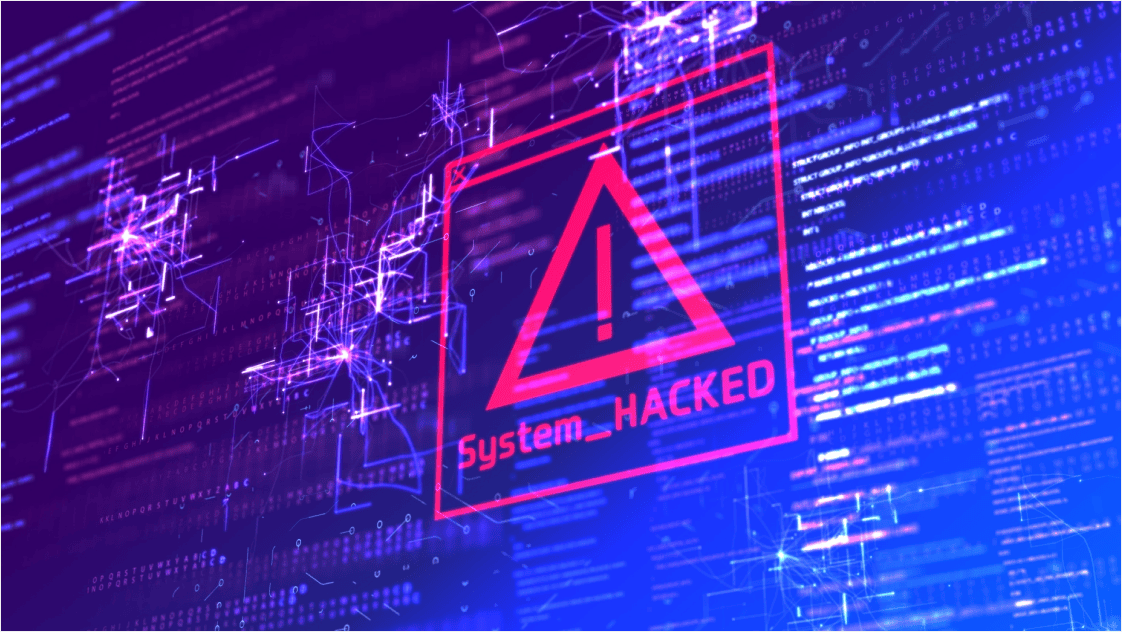
サイバー攻撃とは、ネットワークを通じてパソコンやスマートフォン、サーバなどの情報端末に不正アクセスし、金銭や個人情報の盗難、システムの機能停止などを引き起こす行為です。
ここでは、代表的なサイバー攻撃の種類について紹介します。
ランサムウェア攻撃
ランサムウェアは、感染したデバイスのファイルを暗号化し、解除と引き換えに身代金を要求するマルウェアです。主に企業や組織を標的とし、データ喪失や事業停止といった深刻な被害を引き起こすことがあります。
過去には、国内の大手メーカーがランサムウェアに感染し、工場の操業を一時停止せざるを得なくなった事案も発生しています。
ランサムウェア攻撃については、以下の記事で解説しています。
関連記事:ランサムウェアの脅威|企業が知るべき感染経路と対策方法
標的型攻撃(APT攻撃)
標的型攻撃(APT攻撃)は、特定の企業や組織に狙いを定めて長期間にわたって侵入し、機密情報を窃取するサイバー攻撃です。高度な手法を駆使し、セキュリティ対策を回避しながら不正アクセスを継続するのが特徴です。
より機微な情報を扱う企業や機関ほど、強固なセキュリティ体制を敷いている傾向にあります。攻撃者もそれを見越したうえで、発覚を避けるために長期的な視点で慎重に痕跡を隠しながら侵入を試みます。そのため、たとえ強固な体制であっても、侵入の発覚までに時間を要するケースが少なくありません。その結果、個人情報や機密情報の流出リスクが高まり、深刻な被害につながる恐れがあります。
フィッシング詐欺
フィッシング詐欺は、実在の銀行や企業になりすまし、偽のWebサイトやメールを使って個人情報や認証情報を盗み取る手口です。本物そっくりに作られたWebサイトやメッセージで被害者の信用を得て、パスワードやクレジットカード情報を詐取します。近年では、個人に向けたSMSやSNSを悪用した手法が増えており、身近なサイバー攻撃のひとつになっています。
ビジネスメール詐欺(BEC)
ビジネスメール詐欺(BEC)は、企業の経営者や取引先になりすまし、不正な送金や機密情報の提供を要求する詐欺手法です。場合によっては、実際に使用しているメールアドレスを乗っ取った上で偽メールが送られることがあるため、見極めが非常に困難です。なかには数億円単位の大きな金銭的損失を与えるケースもあります。特に、海外取引の多い企業が狙われやすく、実際のやり取りと見分けがつかない巧妙な手口が用いられます。
ビジネスメール詐欺(BEC)については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ビジネスメール詐欺とは?標的型メールとの違いや手口、対策を解説
DDoS(分散型サービス拒否)攻撃
DDoS攻撃は、複数の端末から大量のリクエストを送信し、サーバやネットワークに過負荷をかけることで、サービスを妨害するサイバー攻撃です。
企業や公的機関が標的になりやすく、Webサイトのダウンや業務の停止など、深刻な影響を及ぼすことがあります。近年では、ボットネットを悪用した大規模な攻撃が増加しており、金融機関や公共交通機関でサービスが停止する事例が確認されています。
SQLインジェクション
SQLインジェクションは、Webサイトの入力フォームなどに不正なSQL文を挿入し、データベースを不正操作するサイバー攻撃です。特に、個人情報や企業の重要データを扱うWebサイトが標的になりやすく、データベース内の機密情報が抜き取られたり、既存のデータが改ざんされたりするといった被害が確認されています。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、企業の取引先や関連企業を経由して標的企業に侵入するサイバー攻撃です。セキュリティ対策が手薄な企業を踏み台にするため、被害者は侵入に気付きにくいのが特徴です。
特に、企業が利用するソフトウェアやサービスのベンダーが狙われるケースが多く、被害が広範囲に及ぶ可能性があります。
サイバー攻撃対策を怠ることによるリスク

サイバー攻撃対策を怠ると、さまざまな被害が発生する恐れがあります。ここでは、代表的な4つのリスクについて紹介します。
金銭的な損失
サイバー攻撃による情報漏えいが発生すると、取引先や顧客から損害賠償を請求され、企業は大きな経済的損失を被る可能性があります。また、インターネットバンキングを悪用した不正送金や、クレジットカード情報の盗難による被害も増加しています。
特に、銀行を装ったフィッシングメールによる詐欺が急増しており、金融庁も注意喚起を行っています。被害が発生すると信用の低下につながり、長期的な経営リスクとなる恐れもあります。
社会的評価の低下
サイバー攻撃によって情報漏えいやシステム障害が発生すると、企業の管理責任が問われ、社会的評価の低下につながります。特に、同業他社と比較されるなかで信頼を失えば、顧客離れや取引先の契約解除といった事態を招く恐れがあります。
一度低下した信用を回復するには時間がかかり、長期的にブランド価値の低下を引き起こす可能性も否定できません。社会的信用が損なわれることで売上が減少し、継続的な受注が途絶えるなど、最悪の場合には事業の存続が危ぶまれるリスクも考えられます。
事業・サービスの停止
デジタル技術の活用が進む現代において、情報システムの障害は企業の業務に深刻な影響を及ぼします。サーバやネットワークにトラブルが発生すると、生産の遅れや営業機会の損失につながり、業務が停滞する恐れがあります。
特に、基幹システムが停止した場合、事業の継続が困難となり、取引先への影響も避けられません。過去には、ランサムウェア感染によってサーバ上のデータが暗号化され、復旧に多大な時間とコストを要した事例もあり、企業の存続を脅かすリスクとなっています。
従業員への影響
サイバー攻撃は、企業だけでなく従業員にも深刻な影響を及ぼします。例えば、個人情報が流出すると、プライバシー侵害や不正利用のリスクが高まり、詐欺やなりすまし被害に巻き込まれる可能性があります。また、こうした事態は精神的な負担を大きくし、従業員の安全や生活にも影響を及ぼしかねません。
近年では、元従業員による情報の持ち出しが原因で発生する漏えいも増えており、社内のセキュリティ管理が厳しく問われるケースが増えています。このような問題は、従業員の士気低下や企業への不信感につながるだけでなく、場合によっては訴訟に発展するケースもあります。
サイバー攻撃による被害事例
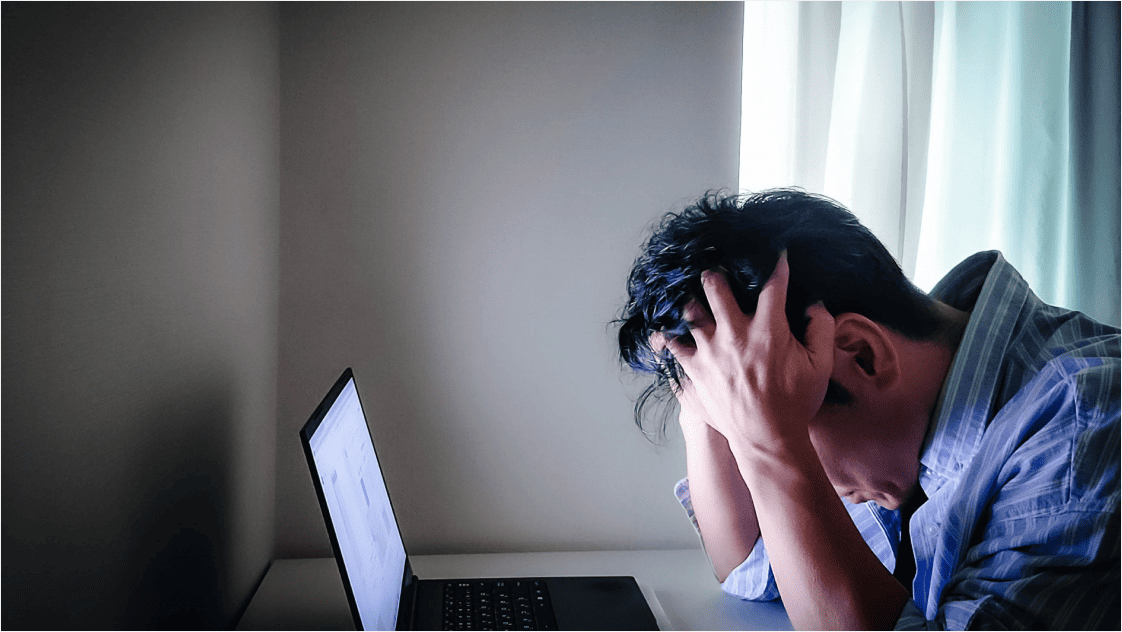
これまでに、サイバー攻撃によってどのような被害が発生したのでしょうか。ここでは、代表的な2つの事例を紹介します。
事例1:アミューズメントパークで約200万件の個人情報漏えい
2025年1月、アミューズメントパークを運営する企業のサーバがランサムウェアに感染し、最大約200万件の電話番号、氏名、住所などの個人情報が外部に漏えいした可能性があると報告されました。これにより、チケット購入や来場予約の取得などの業務が滞り、顧客に影響が発生することとなりました。
事例2:地方医療センターで電子カルテが使用不能に
2024年5月、ある地方医療センターがランサムウェア攻撃を受け、院内システムが停止しました。この影響で電子カルテなどの重要なデータが使用不能となり、最大約4万人分の個人情報が漏えいした可能性があると報告されました。
原因は、ネットワーク機器の脆弱性やパスワード管理の不備とされており、施設側は今後、セキュリティ対策の強化とITガバナンスの向上に取り組む方針を示しています。
企業が実施すべきサイバー攻撃対策

ここまで、サイバー攻撃に関するさまざまな情報を紹介しましたが、被害を防ぐためにはどのような対策を講じるべきなのでしょうか。ここでは、そのポイントを5つに分けて紹介します。
メールセキュリティの強化
メールは、マルウェア感染やビジネスメール詐欺(BEC)などのサイバー攻撃の主な手口として悪用されやすいため、適切な対策が不可欠です。
DMARC(送信ドメイン認証)を導入することで、受信メールの安全性を確認し、なりすましメールによるリスクを軽減できます。また、URLリンクの検査や添付ファイルのマクロ無効化などのセキュリティツールの活用により、被害の抑制につなげられます。
Webブラウザーセキュリティの強化
Webブラウザーは、情報収集や業務に欠かせないツールですが、マルウェア感染やフィッシング詐欺の被害に遭いやすいとされています。
攻撃を防ぐには、ブラウザーを常に最新版にアップデートし、脆弱性を悪用されないような対策が重要です。また、セーフブラウジング機能を有効にすることで、不審なサイトへのアクセスを未然に防げます。
複合的に防げるゼロトラストセキュリティサービスを導入する
ゼロトラストは、ネットワークの内外を問わず、全てのアクセスを検証し、安全性を確保するセキュリティ対策の考え方です。IDaaSやEDR、IAPやCASBなどのツールを組み合わせることで、多層的な防御を実現できます。
自社で適切なツールを選定・導入するのが難しい場合は、専門のマネージドサービスの活用により、運用負担を軽減しながら強固なセキュリティ体制を構築できます。
ゼロトラストについて以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ゼロトラストとは?基本概念からメリット・課題までわかりやすく解説
セキュリティシステムの導入・更新
セキュリティツールやソフトウェアには、常に「脆弱性」が存在し、攻撃者に悪用されるリスクがあります。そのため、メーカーが提供するセキュリティパッチを定期的に適用し、システムの安全性を維持することが不可欠です。
しかし、パッチの配布時期がわかりにくく、適用の遅れがセキュリティリスクを高める要因になることがあります。これを防ぐための対策として、パッチ管理ツールの導入が効果的です。自動更新の仕組みを整えられれば、セキュリティ対策の強化と運用負担の軽減を同時に実現できます。
セキュリティポリシーの策定
セキュリティポリシーは、企業や組織が情報資産の保護のために定める基本方針や行動指針です。企業の規模や運用体制に応じたルールを策定し、適切に運用することが求められます。
サイバー攻撃を防ぐためには、セキュリティツールの導入だけでは十分とはいえません。従業員全員がルールを理解し、継続的に対策を実践することが重要です。そのためには、ポリシーを通じてセキュリティ意識を高め、組織全体でサイバーリスクに備えることで、安全な業務環境を維持することができます。
まとめ

本記事では、サイバー攻撃の種類や被害事例、対策について紹介しました。サイバー攻撃は年々巧妙化しており、被害に遭うと金銭的損失や信用の低下、事業停止など深刻な影響を及ぼすことがあります。
オプテージの「OPTAGE MDR powered by CrowdStrike」は、CrowdStrikeの「Falcon」を活用し、エンドポイントの脅威対策を導入から運用までトータルで提供しています。CrowdStrikeのEDR機能や次世代ウイルス対策機能を活用し、高度なセキュリティ対策を実現します。
また、「どのようなセキュリティ対策が必要かわからない」「何から始めればよいかわからない」という方には、無料の「サイバーセキュリティ自己診断」も提供しております。簡単な20問で診断が可能で、結果はメールですぐ届くため、現状把握や今後のセキュリティ対策検討に速やかに活用いただけます。
サイバー攻撃についてお悩みのことがありましたら、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





