- 公開日:2025年04月21日
ゼロトラストとは?基本概念からメリット・課題までわかりやすく解説

従来の境界型セキュリティは、社内ネットワークを信頼する前提で構築されていました。しかし、サイバー攻撃の高度化やクラウド活用の拡大により、従来の防御手法では十分に対応できなくなっています。
そこで、全てのアクセスを検証し、必要最低限の権限を付与する「ゼロトラスト」の考え方が注目されています。本記事では、ゼロトラストの基本原則や導入メリット、注意点や企業が取り入れるべきポイントを紹介します。
ゼロトラストとは?「信頼しない」セキュリティの考え方

ゼロトラストは、「何も信用しない」(Never Trust, Always Verify)を原則とするセキュリティモデルです。あらゆるユーザーやデバイスのアクセスを逐一検証し、必要最低限の権限のみを付与することで、不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減します。
特に、近年のサイバー攻撃の高度化により、内部ネットワークでも不正な動きを検知する重要性が高まっています。ゼロトラストは、攻撃を未然に防ぐだけでなく、万が一の侵害時にも被害を最小限に抑える仕組みとして注目されています。
従来のセキュリティ対策との違い
従来の境界型セキュリティは、ネットワークの内外を明確に区別し、外部を「危険」、内部を「安全」とみなすことで、不正アクセスやサイバー攻撃を防ぐ仕組みです。しかし、クラウドの活用やリモートワークの普及により、従来の方法では十分な防御が難しくなっています。
ゼロトラストは、ネットワークの内外に関係なく、「全てのアクセスを疑い、検証する」という考え方に基づくアプローチです。これにより、内部ネットワークの脅威にも対応し、より高度なセキュリティを実現できます。
なお、ゼロトラストは境界型セキュリティを完全に置き換えるものではなく、相互に補完する形で活用することが推奨されます。
ゼロトラストの3原則
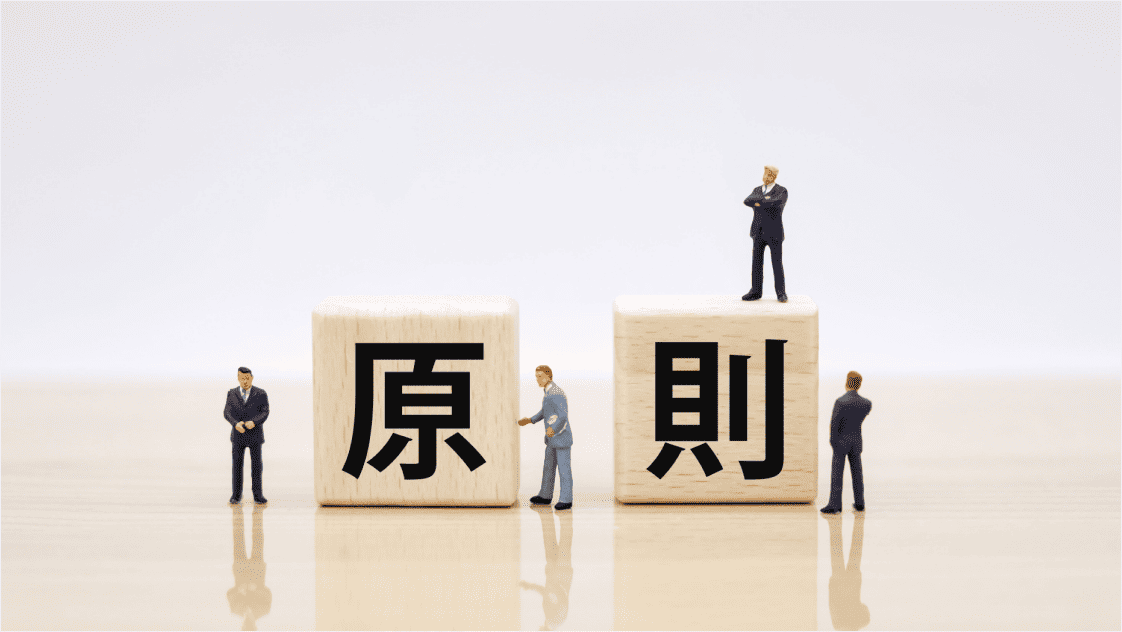
ここでは、ゼロトラストの基本的な考え方である「ゼロトラストの3原則」について紹介します。
1.全てのトラフィックを信用しない
ゼロトラストの基本は「Never Trust, Always Verify(信用せず、常に検証)」という考え方です。社内外を問わず、全てのユーザーやデバイスのアクセスを疑い、その都度、認証・検証を行います。
具体的には、ID情報、端末の状態、アクセス元の位置情報など複数の要素を組み合わせてアクセスの可否を判断します。この仕組みにより、なりすましや不正アクセスを防ぎ、ネットワークの安全性を高めることが可能です。
2.最小特権の原則
ゼロトラストでは、「Least Privilege Access(最小特権の原則)」に基づき、ユーザーやシステムに対して必要最低限のアクセス権限のみを付与します。これにより、本来アクセスすべきデータやリソースのみを利用できるよう制御し、不正アクセスや情報漏えいのリスクを軽減できます。
さらに、多要素認証(MFA)などと組み合わせることで、ユーザーの状況に応じた柔軟なセキュリティ対策が可能です。その結果、ネットワークの安全性が向上し、より強固な環境を構築することが可能となります。
3.侵害を前提とした設計
ゼロトラストでは、「Assume Breach(侵害を前提とした設計)」のもと、常にシステムが攻撃を受けている可能性を想定しながら防御を強化します。サイバー攻撃は巧妙化し続けており、侵入を100%防ぐことは現実的ではありません。そのため、異常なアクセスの兆候を素早く検知し、即座に対応できる環境を整えることが重要です。
例えば、リアルタイム監視ツールやエンドポイントセキュリティツールを導入することで、攻撃の兆候を素早く察知し、被害を最小限に抑えることが可能になります。
ゼロトラストが注目される背景

ここでは、ゼロトラストが注目されている要因について紹介します。
クラウドサービスの普及
近年、多くの企業がITインフラのクラウド移行を進め、業務の効率化やコスト削減を図っています。しかし、クラウド環境では従来の境界型セキュリティでは十分に対応できず、新たなセキュリティ対策が求められています。
また、社内ネットワークとクラウドの境界が曖昧になるなか、クラウド上のデータ保護やアクセス管理を強化する仕組みが不可欠です。サイバー攻撃が高度化するにつれ、従来の防御策では脅威を完全に防ぐことが難しくなっており、クラウド環境に適したゼロトラストの導入が急務となっています。
働く環境の多様化
テレワークやハイブリッドワークの普及に伴い、従業員が社外から業務システムへアクセスする機会が増えています。しかし、従来のVPNを利用したアクセス管理では、一度接続を許可すると広範囲のネットワークにアクセスできるため、不正侵入や情報漏えいのリスクが懸念されます。
さらに、パソコンやスマートフォンなど、多様なデバイスの利用が増えたことで、一律のセキュリティ対策が難しくなっています。このような環境の変化に対応すべく全てのアクセスを検証し、安全性を確保するゼロトラストの導入が求められています。
ゼロトラスト導入のメリット
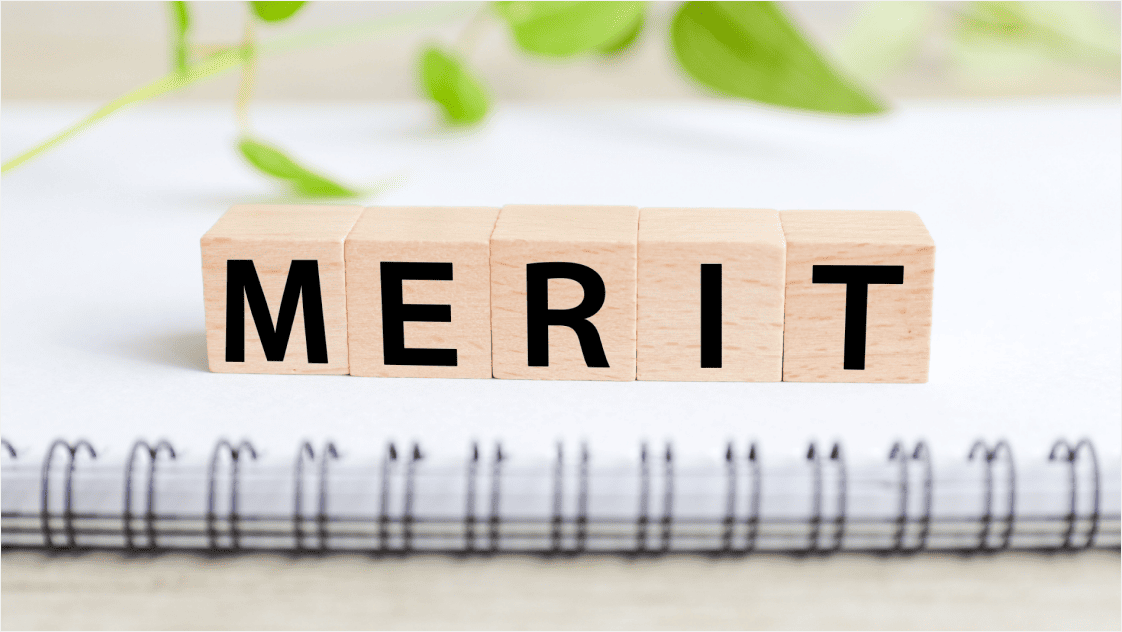
ゼロトラストについて解説してきましたが、導入するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、3つのポイントに分けて紹介します。
セキュリティリスクの軽減
ゼロトラストは、全てのアクセスを検証することで、不正な侵入や内部からの不正行為を防ぎ、セキュリティリスクを大幅に軽減します。
従来の境界型セキュリティでは、社内ネットワークが侵害されると被害が拡大しやすいという課題がありました。しかし、ゼロトラストでは、アクセスのたびに認証・検証を行うため、不審な動きを早期に検知し、サイバー攻撃や情報漏えいのリスクを最小限に抑えられます。
リモートワーク環境でも安全なアクセスを確保
リモートワークの普及に伴い、従業員が場所を問わず業務システムへアクセスできる環境の整備が求められています。しかし、従来のセキュリティ対策では、社外からのアクセスを完全に管理することが難しく、不正アクセスのリスクが懸念されていました。
ゼロトラストでは、アクセスを試みるユーザーやデバイスを都度検証し、状況に応じた認証を行うことで、不正アクセスを未然に防ぐことが可能です。これにより、従業員はどこからでも安全に業務を遂行できる環境を確立できます。
権限管理が明確になる
ゼロトラストでは、ユーザーやデバイスごとに必要最低限のアクセス権を設定するため、不必要なデータやシステムへのアクセスを防ぐことができます。これにより、内部不正や誤操作による情報漏えいのリスクを軽減し、より厳格なセキュリティ管理が可能になります。
また、アクセス権限を細かく設定することで、どのユーザーがどの情報にアクセスできるのかが明確になり、監査やコンプライアンス対応の負担も軽減されます。
ゼロトラスト導入の課題と注意点
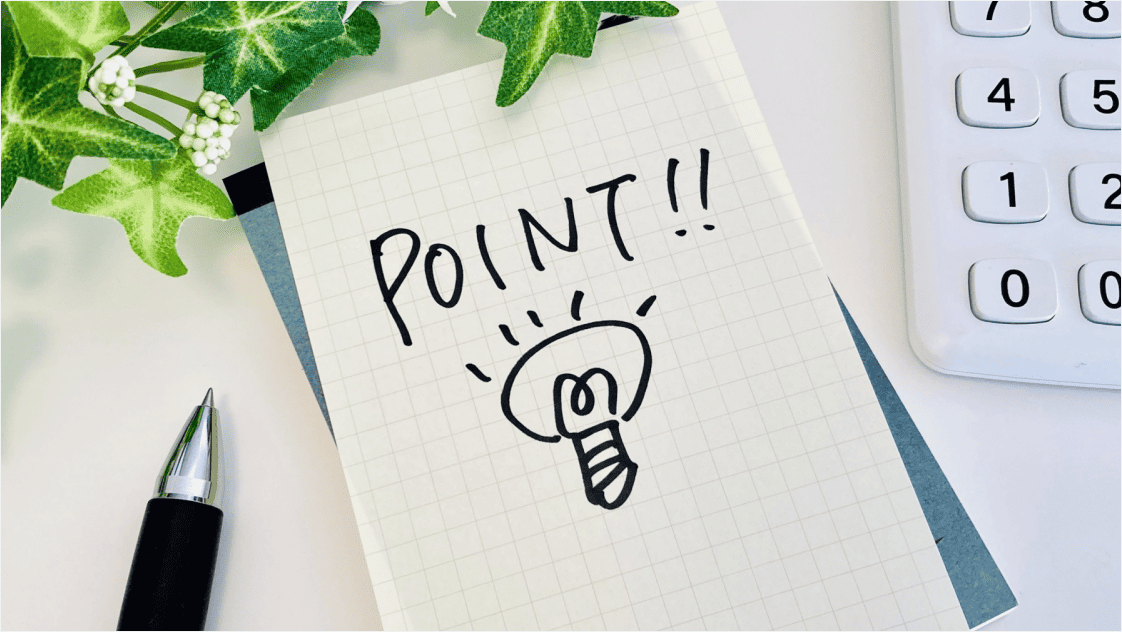
ゼロトラストにはメリットがある一方で、注意すべきポイントも存在します。ここでは、ゼロトラストを導入するうえで知るべき課題と注意点について紹介します。
導入に時間とコストがかかる
ゼロトラストを導入するには、既存のネットワークやセキュリティ体制を見直す必要があり、構築や運用に時間とコストがかかります。
特に、アクセス管理や認証システムの整備には慎重な設計が求められます。そのため、全社的な導入を一度に行うのではなく、段階的に計画を立てて実施することが重要です。
従業員の理解・運用の負担
ゼロトラストは、全てのアクセスを検証するため、従来よりも厳格な認証プロセスが必要になります。その結果、従業員の手間が増え、業務効率が低下するおそれがあります。
これを防ぐには、使いやすい認証システムの導入や、ルール設定の最適化が重要です。また、従業員への教育を徹底し、ゼロトラストの必要性を理解してもらうことも大事なポイントです。
既存システムとの統合が必要
ゼロトラストを導入するには、既存のセキュリティシステムや業務アプリケーションとの連携が欠かせません。しかし、システムの互換性や運用負荷の増加といった課題が生じる可能性があります。
そのため、現行のIT環境を整理し、影響を最小限に抑えながら段階的に導入を進めることが重要です。計画的に統合を進めることで、円滑な移行とセキュリティ強化を両立できます。
ゼロトラストを導入するための4つのポイント

ゼロトラストを導入する際、どのようなポイントを考慮するとよいのでしょうか。ここでは、4つのポイントに分けて紹介します。
安全なインターネットアクセスの確保
ネットワークの安全性を維持するために、ゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)の活用がおすすめです。
ゼロトラストネットワークアクセスは、ユーザーの接続元や端末の状態を検証し、状況に応じたアクセス制御を実施することで、不正アクセスを未然に防ぐ仕組みです。また、クラウド型セキュリティを導入することで、フィルタリングを強化し、不正サイトやマルウェア感染のリスクを軽減できます。
これにより、企業のデータ保護やシステムの安全性向上を実現しつつ、柔軟なアクセス環境を提供できるようになります。
ゼロトラストネットワークアクセスについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)とは?|導入課題やメリット、課題について解説
エンドポイントの強化
ゼロトラストにおいては、全てのデバイスを信頼せず、リアルタイムでセキュリティ状態を監視することが重要です。そのため、EDRなどのエンドポイント監視ツールを活用し、デバイスの異常な動きを素早く検知できるようにする必要があります。
さらに、デバイスのセキュリティ状態を常にチェックし、対策が不十分なデバイスにはアクセスを制限する対応も欠かせません。こうした対策により、企業のシステムやデータをサイバー攻撃から守ることができます。
EDRについては、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:EDRとは|サイバー攻撃対策で注目されるエンドポイント対策について
ID・アクセス管理
セキュリティを強化するためには、ユーザーがアクセスする際の認証を徹底し、なりすましや不正利用を防ぐことが求められます。そのため、多要素認証(MFA)などのセキュリティの高い認証方式を導入し、パスワードが漏えいした場合でもリスクを減らすことのできる対策が求められます。
また、ユーザーの行動を分析し、通常とは異なるアクセスが検出された場合には追加認証を求めることで、より強固なセキュリティを確保できます。
監視・可視化
導入後も効果的にゼロトラストを推進するには、継続的な監視と改善が重要です。SIEMなどの相関分析が可能なセキュリティ監視技術の導入により、異常な挙動をリアルタイムで検知し、セキュリティインシデントへの早期対応が可能になります。
また、社内ネットワークやクラウド、デバイスの可視化を強化することで、リスクを即座に把握し、被害を最小限に抑えられます。
まとめ

本記事では、ゼロトラストの基本原則や、導入時のメリット、注意点、ポイントを紹介しました。
従来の境界型セキュリティでは対応が難しくなった現代において、ゼロトラストは効果的なセキュリティモデルとして注目されています。しかし、導入には運用や管理の負担、人材不足など、さまざまな課題が伴います。
オプテージでは、企業のセキュリティ強化を支援する「ゼロトラスト・セキュリティ対策」サービスを提供しています。企業ごとのさまざまな課題に応じた最適な対策を提案し、安全なIT環境の構築をサポートします。セキュリティ、クラウド、ネットワークを総合的に支援し、設計から運用・管理まで幅広く対応が可能です。
ゼロトラストの導入に関してお悩みの際は、ぜひオプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




