- 公開日:2025年11月19日
医療ICTとは?活用事例・導入メリットと課題を解説

医療現場では、診療や事務作業が複雑化する一方で、少子高齢化や人材不足により、限られた人員で効率的に業務を進める仕組みづくりが求められています。こうした課題の解決策として注目されているのが「医療ICT」です。電子カルテやオンライン診療、AI診断支援などを活用することで、情報共有や業務の自動化が進み、医療の質と安全性を両立できます。
本記事では、医療ICTの概要や活用事例、導入メリットと課題をわかりやすく紹介します。
医療ICTとは

医療ICTとは、情報通信技術(ICT)を活用して、医療現場の業務効率化や情報共有を推進する取り組みを指します。電子カルテの共有、オンライン診療、遠隔医療などがその代表例で、医師や看護師、薬剤師、さらには患者との間で診療データを円滑にやり取りできるようにします。これにより、診療のスピードや正確性が向上し、医療ミスの防止や患者負担の軽減にもつながります。
近年では、ICTの活用を通じて医療提供体制全体を変革する「医療DX」の一環としても注目されており、地域医療や在宅医療、介護との連携を支える基盤として欠かせない存在です。限られた人員で質の高い医療を実現するうえで、こうした取り組みの重要性は今後さらに高まっていくと考えられます。医療ICTの理解を深めるために、まずはITとの違いを見ていきましょう。
ITとICTの違い
ITとICTはいずれも情報技術を指す言葉ですが、ICTはそこに「情報を共有し、活用する」という視点を加えた概念です。ITが技術そのものを意味するのに対し、ICTはその技術を人や組織のつながりに活かすことを重視します。
医療の現場では、このICTを用いて医師・看護師・薬剤師・患者などが必要な情報を共有し、診療の質を高める取り組みが進んでいます。例えば電子カルテや遠隔診療などがその代表例で、医療従事者間の連携をスムーズにし、チーム医療や患者中心のケアを実現するための重要な仕組みとなっています。
こうしたICTの考え方は、実際の医療現場でも幅広く応用されています。
医療ICTの活用シーン

近年、医療現場では人手不足や情報共有の遅れなどが課題とされています。こうした課題の解消に向けて、医療ICTの導入が進められています。医療ICTは、院内の業務効率化から地域医療の連携強化まで、さまざまな場面で活用が進んでいます。ここでは、病院内や在宅医療などで実際に導入されている主なツールと、その活用効果を紹介します。
院内での活用例
院内で医療ICTを活用する例として、次のようなものがあります。
- 電子カルテの共有:患者の既往歴や検査結果を院内スタッフ間で迅速に共有でき、紙カルテに比べ業務効率と安全性が向上します。
- モバイル端末の活用:医師や看護師、薬剤師が現場でリアルタイムに情報を確認でき、チーム医療を円滑に進められます。
- AI診断支援システム:最新鋭のAIを活用して画像や問診データを解析・診断の補助を行い、医師の負担を軽減しながら診療の精度を高めます。
- リアルタイムデータ分析:患者のバイタル情報を自動収集・リアルタイムに解析し、異常を早期に検知して迅速な対応を可能にします。
これらのツール活用により、医療現場の効率化と診療の質向上が同時に進んでいます。
院外・地域連携での活用例
院外や地域で医療ICTを活用する例として、次のようなものがあります。
- オンライン診療システム:通院が難しい高齢者や遠隔地の患者でも、自宅から専門医の診察や指導を受けられます。
- 地域医療連携システム:病院・診療所・薬局が電子カルテや検査画像を共有し、重複検査を防ぎながら切れ目のない医療を提供します。
- 遠隔モニタリングツール:患者のバイタルデータを自動で収集・解析し、異常を早期に検知します。これにより迅速な治療判断を支援できるようになります。
- AI診断支援システム:AIを使って画像や問診データを解析・診断を補助することで、医師の負担軽減と地域医療の質向上に貢献します。
これらの仕組みは、地域全体で医療を支える新しい連携体制の構築に役立っています。
医療ICTによるメリット

医療ICTの導入は、業務効率の向上や診療の質の改善など、医療現場に多くのメリットをもたらします。電子カルテやAIなどの活用により、情報共有や判断の迅速化が進み、医療データの分析を通じた研究や治療の高度化にもつながっています。ここでは、医療ICT導入によって得られる主なメリットを紹介します。
業務の効率化
電子カルテや医療ソフトを活用すれば、カルテ作成や患者情報の入力・共有を電子化でき、紙や手作業に比べて処理速度と正確性が大幅に向上します。情報を一元管理することで、必要なデータをすぐに検索・参照でき、スタッフ間の連携もスムーズになります。
こうした仕組みは業務の属人化を防ぎ、チーム全体で効率的に動ける体制づくりに役立ちます。さらに、センサーを使った入院患者の見守りや、オンライン問診による受付・予診の自動化なども、ICTによる自動化の好例です。
限られた人員でも質の高い医療サービスを継続的に提供でき、現場の生産性と働きやすさの両立が可能になります。
診療の質向上と迅速化
電子カルテを中心とした診療データの一元管理により、記録や検査結果を効率的に取り込み、必要な情報をすぐに確認できます。これにより、患者一人ひとりに最適な治療を迅速に提供でき、診療の質が向上します。
また、医療機関間の情報共有システムにより、転院時の引き継ぎや外部機関との連携もスムーズに進み、切れ目のない医療を実現できます。さらに、ICT化によるデータ検索や分析機能の強化により、診断や治療判断の迅速化、記録ミスの削減が進み、医療の正確性と安全性が高まります。
効果的な医療データの収集と解析
医療ICTでは、患者の病歴や診断結果、検査データ、処方内容などを体系的に収集・管理することが可能です。こうして蓄積された医療データを解析することで、疾患の進行パターンや治療効果の傾向を把握でき、より精度の高い診療方針の策定に役立ちます。
また、分析結果を臨床現場に反映すれば、症状に応じた治療法の選択や薬剤の最適化が可能になり、患者一人ひとりに適した医療の提供を実現します。さらに、ICTで整理されたデータは研究にも応用され、疾患メカニズムの解明や新薬開発を加速させます。
データの有効活用は、医療の質を高めるだけでなく、医療技術そのものの進化にも寄与します。
医療ICTが抱える課題
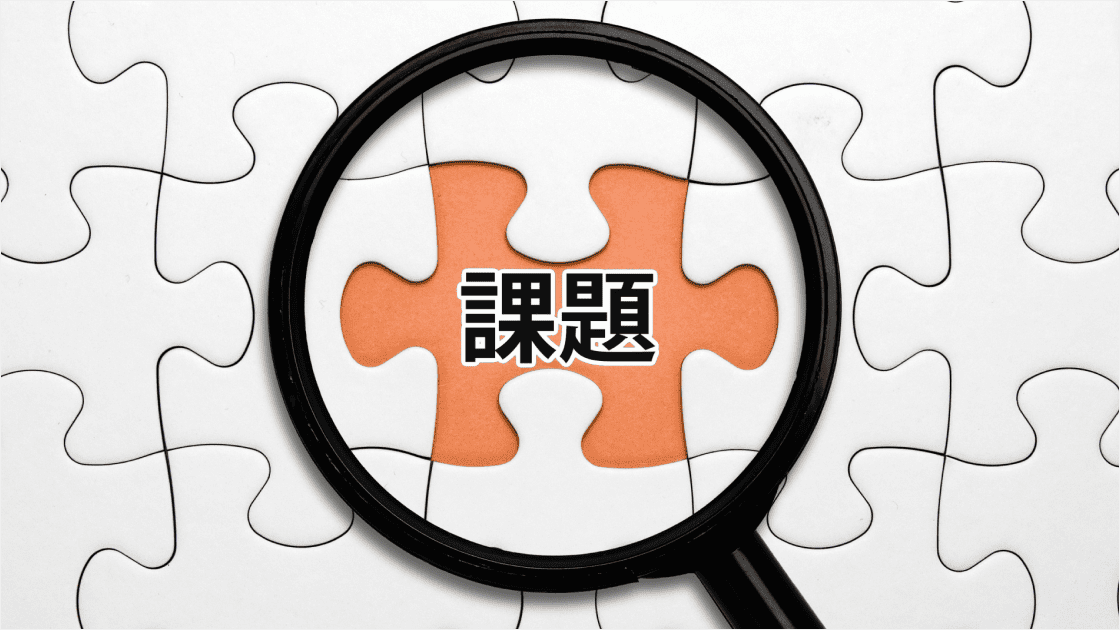
医療ICTの導入が進む一方で、現場ではセキュリティ対策や導入コスト、人材不足といった課題も浮き彫りになっています。これらの課題を正しく理解し、段階的な改善や支援制度の活用を進めることが、持続的なICT活用の鍵となります。ここでは、その課題と解決策を紹介します。
セキュリティリスクの高まり
医療ICTの普及に伴い、患者データの漏えいや不正アクセスなど、セキュリティリスクへの懸念が高まっています。警察庁の報告によると、国内の医療機関を狙ったランサムウェア被害が増加しており、院内システムの停止やカルテの閲覧不能といった深刻な影響も確認されています。
こうした脅威を防ぐためには、アクセス権限の厳格化や通信データの暗号化、ネットワーク監視の強化が欠かせません。また、患者の個人情報を含む医療情報を安全に管理・運用するために、国や自治体などが策定したガイドラインを参考にし、自院の状況に合わせたセキュリティ対策を整備することも推奨されます。
コスト面のハードル
医療ICTの導入では、電子カルテやオンライン診療、請求システムなど複数のツールが必要となり、初期投資が大きな課題となります。
特にICT化が進んでいない医療機関では、端末やネットワーク環境の整備費用も発生し、経営への影響が懸念されます。さらに、保守や運用にかかるランニングコストも無視できず、導入後の費用負担が継続する点も慎重な検討を要します。
こうした課題を軽減するには、必要な機能から段階的に導入を進めることや、クラウド型システムを活用して初期費用を抑える方法が効果的です。また、IT導入補助金などの公的支援制度を活用することで、費用対効果を高めながらICT化を実現できます。
人材不足がもたらすICT導入の壁
医療ICTの導入が進むなかで、大きな課題となっているのがIT人材の不足です。医療機関では電子カルテやオンライン診療など、多様なICTツールを扱う機会が増えていますが、それらを運用・管理できる専門人材の確保が難しい状況にあります。
IT部門を持たない中小規模の医療機関も多く、システムの導入後にトラブル対応や運用改善を担う人材が不足している点も課題となっています。今後もIT人材の不足は拡大すると見込まれており、ICT化を進めるうえで大きな壁となっています。
医療職中心の人員構成や多忙な業務環境のなかで、IT教育に時間や人員を割くことが難しく、新システムを導入しても十分に活用できないケースも見られます。
こうした課題を解消するためには、外部ベンダーやマネージドサービスを活用し、導入から運用まで専門的なサポートを受けることが有効です。さらに、職員向けの研修やOJTを通じて、医療とITの両面を理解する人材を育成することで、持続的なICT活用が可能になります。
ただし、こうしたIT人材の不足は、医療業界に限らず日本企業全体でも深刻化しており、デジタル化を進める上で共通の課題といえます。
背景や具体的な対策事例については、関連記事でも詳しく紹介しています。
関連記事:深刻化するIT人材不足の背景とは?企業が取るべき対策についても紹介
医療ICTの導入事例
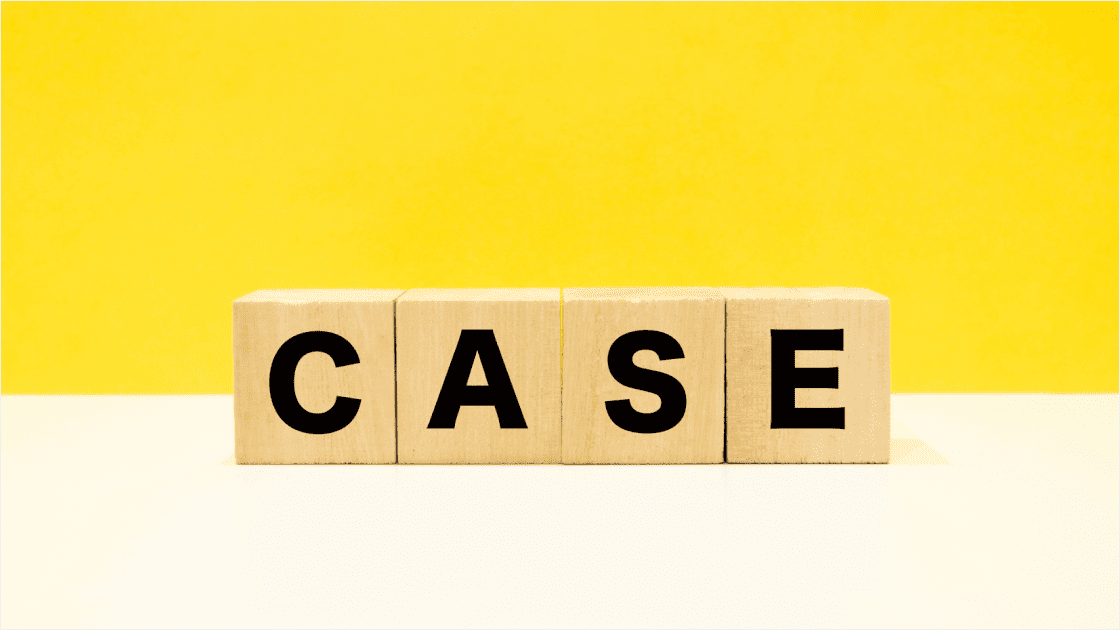
実際に医療ICTを導入した医療機関では、現場の課題解決につながるさまざまな成果が生まれています。ここでは、いくつかの導入事例を見ていきましょう。
事例1:紙からデータ管理へ、意識改革と効率化を同時に実現
ある医療機関では、医師の勤務時間を紙の出勤簿で手書き管理していたため、出退勤や時間外労働を正確に把握できず、長時間労働が常態化するという問題がありました。また、申請書による自己申告制では実態との乖離が生じ、勤務環境の改善にも限界がありました。
そこで、ICカードを用いた勤怠管理システムを導入し、出退勤を自動で記録できる仕組みを構築しました。これにより、打刻データはネットワークを通じて人事部門に集約され、全職員の勤務情報を一元的に管理できるようになりました。その結果、勤務時間の「見える化」が進み、医師の早朝出勤や長時間勤務の是正に効果を発揮しています。
さらに、労働時間管理業務の効率化に加えて、職員の働き方や健康への意識も高まり、ICTの活用が業務改善だけでなく、組織全体の意識改革にもつながるようになりました。
事例2:専門病院に最適化したICT導入 地域医療における連携の強化
がん治療を専門とするある医療機関では、業務効率化やセキュリティ強化、さらに災害時の事業継続体制(BCP)の整備が急務となっていました。ところが、汎用的な病院システムでは不要な機能が多く、必要な放射線治療関連の機能が不足していたため、運用の最適化が難しい状況にありました。
そこで、電子カルテや部門別システムを個別に選定し、柔軟に統合できる情報基盤を構築しました。またWeb方式を採用することで、端末数の増加にも対応しながらコストを抑制できる仕組みを整えました。
さらに、院内ヘルプデスクを設け、迅速なサポート体制を実現したことで、業務の安定稼働と効率化が進み、地域医療機関との情報共有も円滑になりました。これにより、患者への情報提供の充実にもつながっています。
事例3:カルテの長期保管を電子化で解決 外部移行で職員負担ゼロ
入所者を生涯にわたって支援するある医療福祉施設では、紙カルテが年々増え続け、文書庫が限界に達していました。また、必要な記録を探すのにも時間がかかっており、職員の残業や業務負担が深刻化していました。
こうした課題を解消するため、紙カルテをすべて電子化し、記録の検索性と共有性を高めるシステムを導入しました。データ移行は専門業者に委託し、職員に負担をかけることなくスムーズな稼働を実現しました。
導入後は、医事会計など他のシステムとも連携し、業務全体の効率化を促進しました。カルテ保管スペースの問題も解消され、看護スタッフの残業時間も減少しました。さらに、記録の共有が円滑になり、チーム間の連携が強化されました。
まとめ

本記事では、医療ICTの概要から活用事例、導入によるメリット・課題、そして現場の課題解決を支援するソリューションまでを解説しました。
医療ICTは、医療現場の効率化や診療の質の向上に加え、地域医療連携やデータ活用を通じて、医療全体の発展を支える重要な基盤です。電子カルテやAI、遠隔診療といった技術の導入により、現場の負担を軽減しながら患者中心の医療を実現できます。
オプテージでは、医療機関の課題解決を支援するさまざまなICTソリューションを提供しています。
いずれのソリューションも、医療現場の課題解決と業務効率化を目的に設計されています。ICT基盤の強化を通じて、医療機関がより効率的で安心な医療提供環境を実現できるよう支援します。
医療ICTの導入や運用についてお悩みの点がございましたら、お気軽にオプテージまでご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




