- 公開日:2025年03月25日
シャドーITとは?企業としてのセキュリティリスクや対策について解説
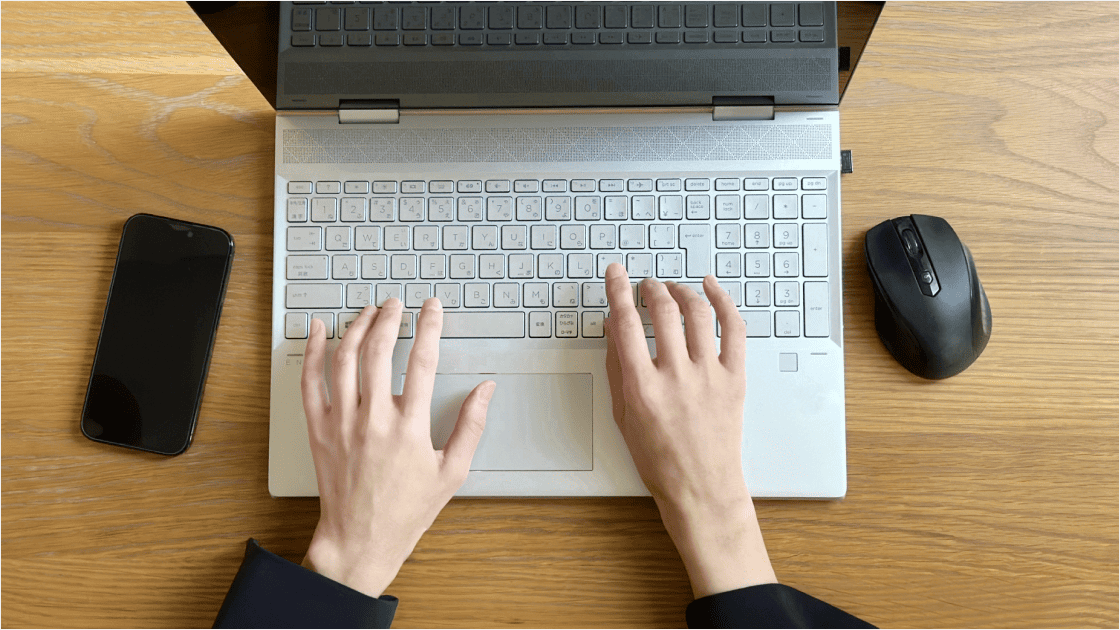
近年、企業の管理外で利用されるITツールが増加し、セキュリティリスクが深刻化しています。その代表例が「シャドーIT」です。
本記事では、シャドーITの実態や拡大の背景、もたらすリスク、効果的な対策について紹介します。
シャドーITとは

シャドーITとは、企業の許可を得ずに業務で利用される個人のデバイスや外部のクラウドサービスを指します。
近年、スマートフォンやタブレットの普及、テレワークの増加などに伴い、社外での業務が一般的になりました。その結果、利便性を求めて個人のITツールを活用する動きが増え、新たなITリスクとして注目されています。企業にとっては、情報漏えいや不正アクセスなどの問題を引き起こすとされており、適切な対策が求められています。
シャドーITが拡大した理由
シャドーITが拡大した背景には、ITツールの進化や業務環境の変化が深く関係しています。近年、クラウドストレージやチャットツール、タスク管理アプリなど、個人でも簡単に使用できる高機能なサービスが増えました。特に、大手クラウド企業が無料で提供するツールやサービスは利便性が高く、インストールの手間もほとんどないため、業務に活用する人が増えています。
さらに、新型コロナウイルスの影響でテレワークが普及したことにより、シャドーITの利用は一層加速しました。オフィス外でも効率的に業務を進められるため、社員が独自の判断でITツールを使用するケースが増え、それがシャドーITの拡大につながっています。
シャドーITとして利用される主なツール・サービス
シャドーITにつながりやすいツールやサービスとしては、以下のようなものが挙げられます。
- プライベートデバイス(スマートフォン・パソコン・USBメモリーなど)
- チャットツール(LINE・Facebookメッセンジャーなど)
- 無料メールサービス(Gmail・Yahoo!メールなど)
- オンラインストレージサービス(Dropbox・Google ドライブなど)
- クラウドオフィスアプリケーション(Google ドキュメント・Office Onlineなど)
特に、無料で手軽に利用できるツールやサービスは導入のハードルが低く、企業の許可なく使用されやすいことからシャドーITになりやすい傾向があります。
BYODとの違い
シャドーITと混同されやすい用語に「BYOD(Bring Your Own Device)」があります。両者の大きな違いは企業の承認の有無です。BYODは、個人のスマートフォンやノートパソコンなどを企業が許可したうえで業務に使用する仕組みを指します。
一方、シャドーITは企業の許可を得ずに個人のデバイスやクラウドサービスを業務に利用するため、適切なセキュリティ対応が難しくなります。BYODは、企業が適切に管理していれば問題視されませんが、シャドーITは情報漏えいや不正アクセスの原因となるケースがあります。そのため、企業はシャドーITに対して対策を講じることが推奨されます。
シャドーITが引き起こすリスク
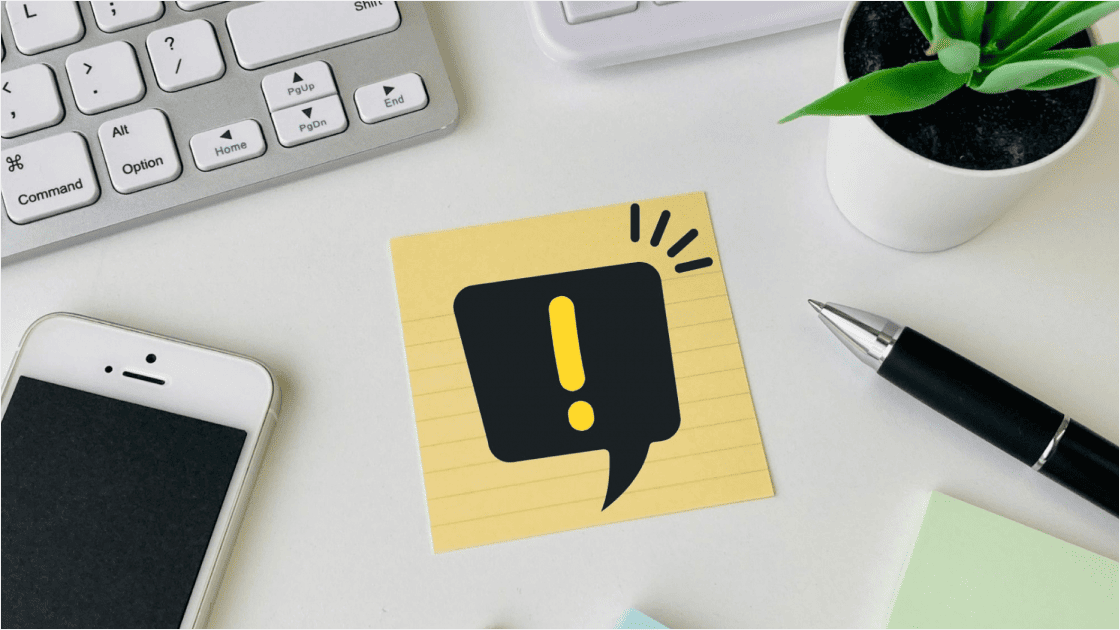
企業がシャドーITに対して対策を行わない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。ここでは、シャドーITによって引き起こされるリスクを3つ紹介します。
外部への情報漏えい
シャドーITの利用により、企業の重要な情報が外部に漏えいするリスクがあります。例えば業務で個人向けのコミュニケーションツールを使用すると、通信内容が外部のサーバに保存されるため、そのサーバがサイバー攻撃を受けると、情報が流出する危険性があります。
また、個人向けのコミュニケーションツールにはプライベートな知人の連絡先が含まれることがあり、誤送信による情報漏えいのリスクも無視できません。さらに、シャドーITとしてクラウドストレージを無断利用し、そこに機密ファイルを保存すると、保存先のサーバが不正アクセスなどのサイバー攻撃を受けたとき、情報の流出だけにとどまらず、企業の信用が大きく損なわれる恐れがあります。
アカウントの乗っ取り
シャドーITの利用によって、チャットツールやクラウドストレージで使用しているアカウントが乗っ取られるリスクもあります。個人が業務で使用している外部サービスは企業の管理外であるため、不正アクセスやパスワード流出による被害を受けやすくなります。
万が一、業務用データが保存されたアカウントを乗っ取られると、機密情報が流出し企業の法的責任が問われる可能性があります。さらに、企業の管理下にないため、乗っ取りが発生しても迅速な対応が難しく、被害が拡大しやすい点も大きなリスクとなっています。シャドーITの利用は、企業のセキュリティ体制を脆弱にする要因にもなるため、十分な注意が必要です。
外部から社内ネットワークへの侵入
企業が管理していないデバイスを社内ネットワークに接続すると、企業のシステム全体がサイバー攻撃の標的になる可能性があります。例えば、個人のノートパソコンがマルウェアに感染していることに気づかず社内LANに接続すると、そのマルウェアがネットワーク内に拡散し、業務システムや機密情報などに影響を及ぼす状況となることが考えられます。
さらに、一度ネットワーク内に侵入を許すと、データの盗難や改ざん、システム障害などの深刻な被害につながってしまうかもしれません。企業のセキュリティを守るためには、無断でのデバイス接続を防ぎ、安全なネットワーク環境を維持することが不可欠です。
シャドーITをなくすための対策とは?

ここまで、シャドーITの危険性について紹介しましたが、シャドーITをなくすためにはどのような対策があるのでしょうか。ここではその方法を4つ紹介します。
シャドーITを使わなくてもいい環境づくり
シャドーITを防ぐには、社員が会社で正式に許可されたITツールを快適に利用できる環境を整えることが重要です。社内勤務・テレワークを問わず、業務で必要なデバイスやクラウドサービスを企業側が適切に選定し、提供することで、社員は非承認のツールを使う必要がなくなります。
また、企業が BYOD(私用デバイスの業務利用)の管理を適切に行えれば、利便性を確保しつつ生産性の向上につなげることができます。ただし、BYODには管理負担の増加やセキュリティ面のリスクがあるため、導入時にはセキュリティ対策やガイドラインの策定を徹底し、社員が安心して業務に取り組める環境を作ることが大切です。
BYODについて以下の記事でくわしく解説しています。
関連記事:BYODとは?COBOとの違いや導入企業のメリット・デメリットを解説
要領やガイドラインの策定
シャドーITのリスクを抑えるには、業務でのデバイスやクラウドサービスの利用に関する明確な要領やガイドラインを策定し、定期的に更新することが重要です。単にシャドーITを禁止するだけでは実効性が低いため、「なぜ使用してはならないのか」「どのような行為がシャドーITに該当するのか」を具体的に示すことで、社員の理解を促進できます。
また、業務の都合上どうしても私物のデバイスや外部サービスを利用する必要がある場合には、システム管理者の許可を得るワークフローを設定するなど、例外対応のルールの整備も大切です。こうした要領やガイドラインの遵守を徹底することで、企業のセキュリティリスクを最小限に抑えられます。
従業員への教育や周知の徹底
シャドーITの抑制には、従業員に正しい理解を深めてもらうことも重要です。多くの社員は、業務効率を優先するあまり、非承認のツールやデバイスを使用するリスクを意識していません。そのため、シャドーITが情報漏えいやサイバー攻撃を招く原因になることを正しく認識してもらうことが必要です。
また、シャドーITによって企業が被る損害を具体的な事例とともに伝えることで、ITリテラシーの向上につなげられます。定期的な研修や社内ポリシーの共有を行い、企業全体で適切なIT環境を維持するための意識を高めることが、シャドーIT対策の第一歩となります。
CASBの導入
CASB(Cloud Access Security Broker)は、企業内のクラウド利用を可視化し、外部サービスの利用を監視・制御するセキュリティ対策のひとつです。社員が利用するクラウドサービスとの通信を監視することで、未承認のツールが業務で使われていないかを把握し、リスクを軽減できます。
CASBの主な機能には、可視化・コンプライアンス管理・データセキュリティ・脅威防御の4つがあり、これによりシャドーITの早期発見や不正アクセスの防止が可能になります。ただし、CASB製品によって対応範囲が異なるため、自社の課題に合ったソリューションを選ぶことが重要です。
まとめ

本記事では、シャドーITについて、拡大の背景や主なツール、引き起こすリスクや対策について紹介しました。シャドーITは利便性の向上と引き換えに、情報漏えいやアカウント乗っ取り、ネットワーク侵入などの重大なリスクをもたらすことがあります。企業がセキュリティを強化するためには、適切なIT環境の整備やガイドライン策定、従業員教育、CASBの導入などの対策が不可欠です。
オプテージでは、総務省の「 国民のためのサイバーセキュリティサイト」にある「システムを"管理"する人向けの対策」をもとに、独自に作成した無料の簡易セキュリティ診断「サイバーセキュリティ自己診断」を提供しています。
また、テレワークやクラウドサービスの利用増加に伴い、場所や端末にとらわれずにセキュリティを確保する「ゼロトラスト・セキュリティ対策」をはじめ、セキュリティ・クラウド・ネットワークをトータルで提供可能です。
シャドーITについてお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。





