- 公開日:2025年08月21日
Web3とは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説
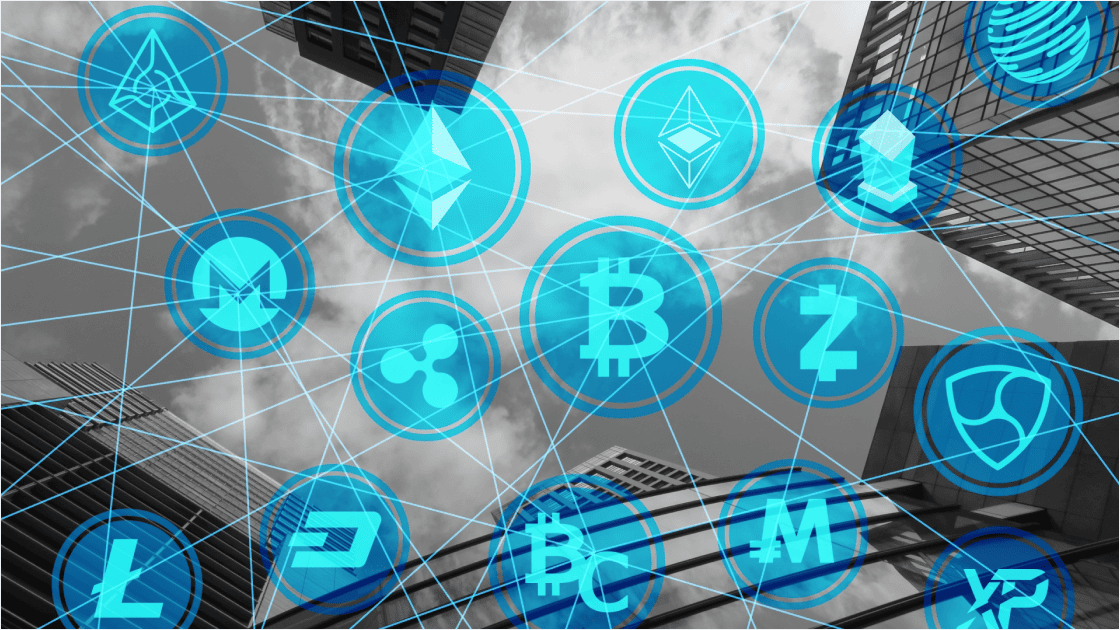
仮想通貨やNFTといったキーワードとともに話題にのぼる「Web3(ウェブスリー)」。次世代のインターネットとして注目を集めていますが、Web3が実際にどのような仕組みで、何を変えるのかについては、いまだ十分に理解されているとは言えません。
本記事では、Web3の基本的な概念からその背景、ビジネスへの影響、活用の可能性までをわかりやすく解説します。Web3を正しく理解することで、今後の事業戦略やマーケティング施策において、新たな視点やチャンスを見つけるヒントになるはずです。
Web3とは何か?
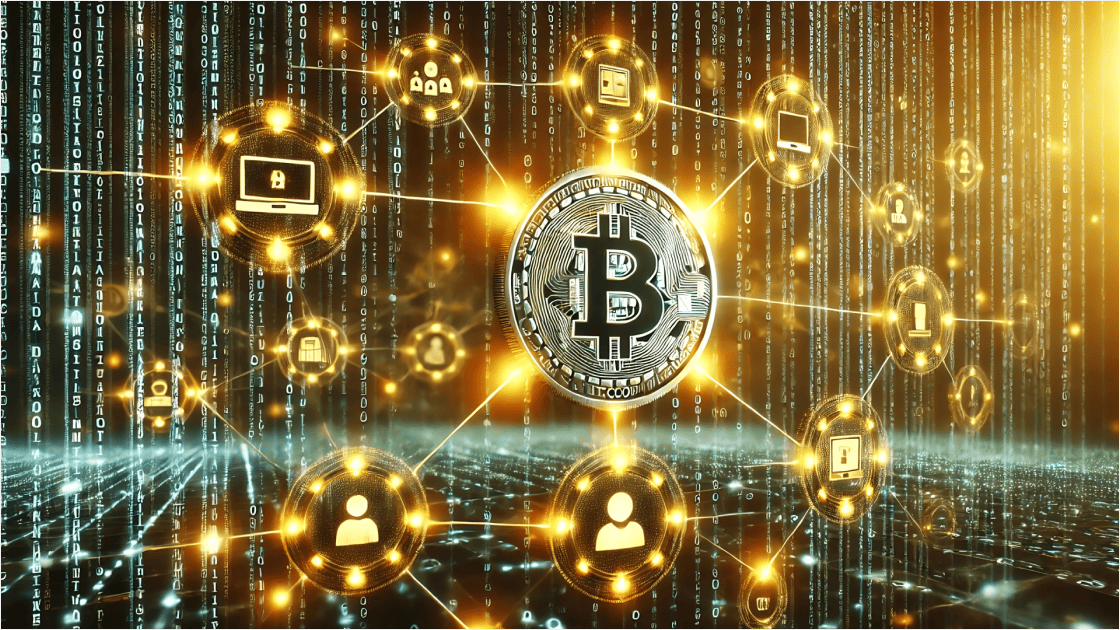
Web3とは、次世代のインターネットの形を指す概念です。
従来のインターネットでは大手プラットフォームがデータやお金の流れを一元管理しており、その利便性から多くのサービスが集中してきました。これらのプラットフォームの普及により、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が容易になり、企業活動にも大きなメリットをもたらしたのです。
一方で、そのようなプラットフォームは海外の巨大IT企業によって運営されていることが多いため、サーバのある国の法律や制度の影響を受けてしまったり、海外の事業者に利用料を払い続けたりしなければならない問題があります。
このような問題を踏まえて、Web3では、個人や企業がデータを自分自身で管理し、直接やり取りできる世界を目指しています。ここからは今までのインターネットとの違いや注目されている背景、Web3を支える基礎技術について見ていきましょう。
Web1・Web2・Web3の違い
インターネットの進化は3つの段階で理解できます。それがWeb1・Web2・Web3です。
Web1は1990年代半ばから2000年代半ばにかけて普及した初期のインターネットを指します。当時、インターネットによる情報発信は専門知識が必要な難しい技術で、主に企業や専門家だけが一方向で情報を発信し、ユーザーは閲覧するだけでした。Web1は「読むだけのWeb」といえます。
Web2は現在のインターネットのことを指します。2000年代に入り、SNSやブログなどが普及し始め、これらのプラットフォームを通じて誰もが情報を発信できるようになりました。この頃から分散型のプラットフォームも存在していましたが、多くは巨大IT企業が提供するものが中心でした。
そして現在注目されているWeb3は、こうしたプラットフォームを運営する一部企業による集中的な管理を見直し、分散化を進めることを目的として登場しました。「所有するWeb」とも呼ばれ、データや資産を中央集権的なプラットフォームに依存せずに所有・管理できる可能性に期待が寄せられています。
Web1が「読む」、Web2が「読み書きする」なら、Web3は「読み書きし、所有する」インターネットといえるでしょう。
なぜ今Web3が注目されているのか
Web3が注目を集める背景には、海外のプラットフォームを運営する企業による中央集権的な影響力への懸念があります。日本企業のデータが海外事業者のサーバに保存されていると、海外事業者の運営方針や、海外の法律、政治情勢などの影響を受けるかもしれません。
例えば、海外のプラットフォーム運営事業者が現地当局から強制捜査を受けた場合、日本企業の機密データが当局に開示されてしまったり、アクセス不能になってしまったりするリスクがあります。日本の司法権が及ばない環境では、企業が適切に対処するのが難しいケースも少なくありません。
また、クラウドやアプリ課金などの「サービス輸入」が「サービス輸出」を上回る状況が続き、日本のデジタル産業は海外プラットフォームへの依存度を高めています。月額課金など少額のサービスであっても、契約者数と利用期間が増えれば、海外への支出額は膨大になります。こうした構造は「デジタル赤字」として懸念されています。
さらに、NFTアートの高額取引やメタバース不動産への投資など、新たな経済圏の形成も注目の理由です。NFTアートとは、デジタルデータで作られたアート作品で、自分が所有者であることを証明できる特徴があります。メタバース不動産は、インターネット上に作られた3次元の仮想空間(メタバース)の中にある土地や建物のことで、広告出稿やイベント開催に使えるため、デジタルな資産としての価値が高まりつつあります。大手金融機関や有名アパレルブランドなど、従来型の企業もWeb3領域への関心を示しており、さまざまな実証実験や新サービスの開発が進んでいます。
このように、Web3には海外プラットフォームへの依存などの懸念もある一方で、新たな経済圏の創出や、企業の実証実験の広がりなどから、今後の発展が期待されている技術でもあります。
Web3の基本技術「ブロックチェーン」とは?
Web3の基盤となるブロックチェーンは、データを複数の参加者で共同管理する仕組みです。
従来のシステムでは、中央にあるサーバがデータを一括管理していました。ここでいう「中央のサーバ」とは、プラットフォームを運営する企業が所有するコンピュータのことで、ユーザーのデータが集約されているものです。一方、ブロックチェーンではネットワークに参加するすべてのユーザーがデータのコピーを持ち、相互にデータの正当性を検証し合います。
この仕組みにより、データの改ざんが難しくなり、高いセキュリティと透明性が確保されるのです。
ユーザーにとっては、第三者を介さずに直接取引ができ、自分のデータやデジタル資産を自分自身で管理できるようになります。
オンライン上での所有権をより強く主張できる仕組みが提供され、デジタル経済に新たな可能性をもたらしているのです。
ブロックチェーンについては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:ブロックチェーンとは?仕組みや特徴、活用事例やメリット・課題について紹介
Web3を使用した代表的な技術
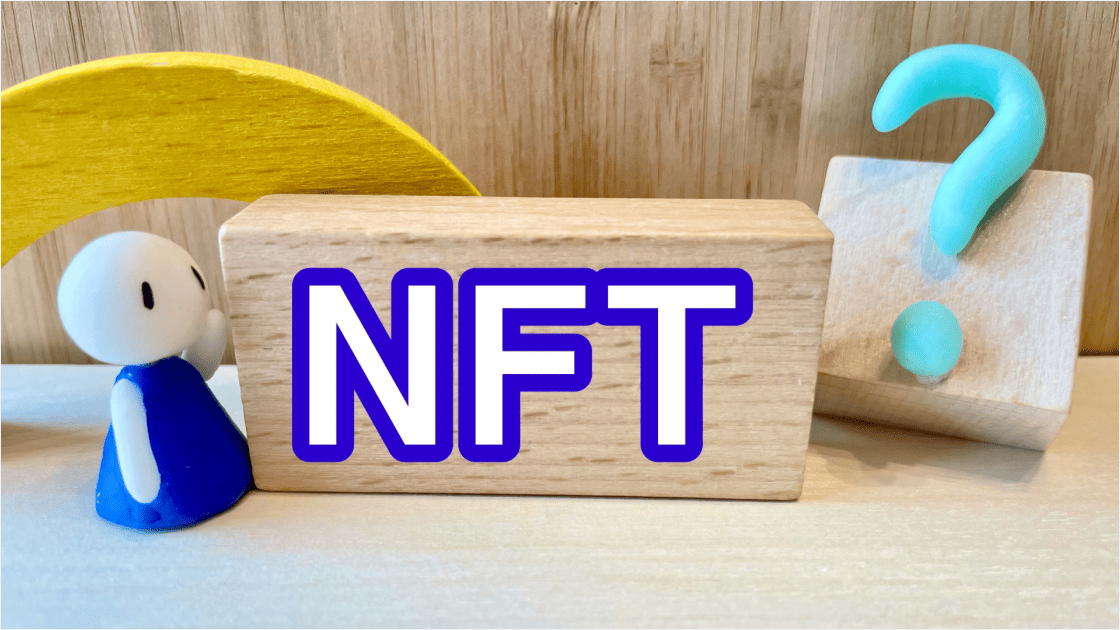
Web3の世界では、革新的な技術が次々と登場しています。特に注目すべきなのは、NFT、暗号資産、DAO、DeFiといった技術です。以下では、これら4つの代表的な技術について詳しく見ていきます。
NFT(非代替性トークン)
NFT(Non-Fungible Token)とは、デジタルコンテンツの「所有者が誰か」を証明できる技術です。
NFTにおける「トークン」とは、ブロックチェーン上で取引履歴や所有情報を時系列に記録する固有の識別子です。ブロックチェーンは、ブロック(データの単位)を鎖のように連結する構造になっており、新しいブロックを末尾に追加するのは容易ですが、途中のブロックを改ざんすると前後との整合性が崩れるため、不正が非常に困難です。この高い耐改ざん性により、NFTの取引履歴や所有者情報は信頼性の高い形で保たれます。
トークンは「ウォレット」と呼ばれるアドレスに紐づけられ、ウォレットを操作するには対応する秘密鍵による署名が必要です。つまり、その秘密鍵を保持する人物が、ブロックチェーン上での「正規の所有者」として扱われます。ただし、ウォレットは匿名性が高いため、誰が操作しているのか(=実世界の個人)は特定できない場合もあります。
このようにNFTでは、「誰がそのトークンを所有しているか」「コンテンツがオリジナルであるか」を技術的・客観的に証明することが可能です。例えば、デジタルアートにNFTを発行することで、その作品が正規の所有者による"オリジナル"であることを示すことができます。画像や動画などのデジタルコンテンツ自体は複製可能ですが、正規のトークンが付いていないコピーは「本物ではない」と識別されます。
アートワーク、音楽、動画、ゲーム内アイテムなど、あらゆるデジタルコンテンツをNFT化することで、そのオリジナル性と所有権の証明の提供が可能です。クリエイターにとっては新たな収益モデルとなり、コレクターには確かな所有権が提供されます。
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)はWeb3から生まれた代表的な投資対象のひとつであり、ブロックチェーン技術を応用したデジタルなお金です。ビットコインやイーサリアムに代表されるこれらのお金は、多くの場合、中央銀行や政府から直接的な管理をされていません。
従来のお金と異なり、国境を越えた送金が可能で、通常は手数料が低いとされます。
Web3から生まれた他のサービスでも決済手段として利用されており、DeFiやNFTなど、さまざまなWeb3サービスが暗号資産を利用して購入可能です。
また、その活用範囲は決済だけでなく、一部では組織の投票権の役割をするトークン(ガバナンストークン)としての利用など多様化しています。
DAO(分散型自律組織)
DAO(分散型自律組織)は、Web3の概念を採り入れた新しい組織モデルとして注目されています。
特徴は、従来のピラミッド型組織のようにリーダーが指示を出すのではなく、参加者全員の投票によって意思決定が行われる点にあります。メンバーは「ガバナンストークン」と呼ばれる投票権を持ち、プロジェクトの方針や資金の使い道などを共同で決定します。
例えば、ある暗号資産の取引所は特定の管理者ではなくDAOによって運営されており、数十万人ものトークン保有者たちの投票によって運営方針を決めています。従来の株式会社においても株主や取締役による意思決定は行われますが、実務上は経営陣が多くの判断を担う構造が一般的です。一方、DAOの場合は手数料の金額や新機能の追加などの具体的議案についても、トークン保有者の投票で決定されるため民主的な意思決定が可能となります。
DAOの魅力は、地理的な制約なく世界中の人々が平等に投票に参加できることにあります。共通の目的や価値観を持つ人々が国境を越えて協力できるのです。すでに投資ファンドやクリエイターコミュニティなど、さまざまな分野でDAOの実装が進んでおり、組織運営の新たな可能性を示しています。
DeFi(分散型金融)
DeFi(ディーファイ、分散型金融)とは、銀行や証券会社などの仲介機関を介さずに、金融サービスを提供する仕組みです。ブロックチェーン技術を活用することで、誰でも貸付・借入・送金・資産運用などをオンラインで行うことができます。
従来の銀行とは異なり、24時間365日、世界中どこからでもアクセスでき、仲介者がいない分、手数料を抑えられるのもメリットです。特に、銀行口座を持たない人々にとっては、スマートフォンとインターネット環境さえあれば利用可能な金融手段として注目されています。
ただし、DeFiはまだ発展段階にあり、セキュリティの脆弱性や詐欺的なプロジェクトも存在します。また、規制が未整備な国や地域も多く、利用にあたってはリスクをよく理解することが大切です。今後は、従来の金融システムを補完・変革する技術として期待されています。
Web3のメリット
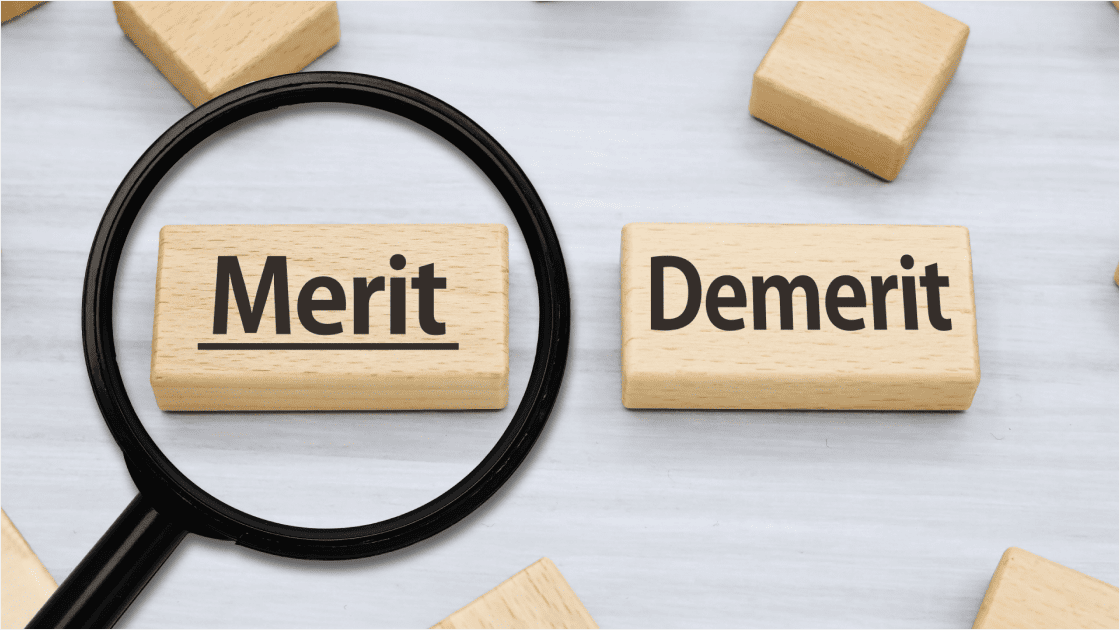
Web3には、さまざまなメリットがあります。代表的なメリットは以下の2つです。
- データを自分で管理できる
- 中間業者が減りコストが下がる
ここからは各メリットについて詳しく解説していきます。
データを自分で管理できる
Web3の主要なメリットのひとつは、自社のデータやデジタル資産を自社で管理できる点です。
従来のWeb2の世界では、企業が利用しているプラットフォームのサーバにデータやデジタル資産を保存していました。プラットフォームを運営している大手IT企業の技術によって安全に管理されるメリットはありましたが、運営企業のポリシーやサーバのある国の法律、政治情勢などに日本企業のデータが影響を受けてしまう懸念もありました。
しかし、Web3ではブロックチェーン技術によってデータを自社で管理することが可能になりました。これにより、従来のプラットフォームに依存せずに済むため、自社のビジネスが外部の影響を受けにくくなります。
中間業者が減りコストが下がる
Web3の大きな特徴は、従来のビジネスモデルで必須だった中間業者の役割が大幅に縮小される点です。現在のWeb2の世界では、銀行、決済代行業者、プラットフォーム運営会社など、さまざまな仲介業者や運営業者がサービスの提供過程で介在し、その都度手数料を徴収しています。
しかしWeb3では、ブロックチェーン技術の活用により、これらの業者の役割が減少し、より直接的な取引が可能です。
例えば、クリエイターが作品を販売する際、大手プラットフォームを利用すると売上の30%もの手数料を支払う必要がありました。しかしWeb3では、仲介業者を介さずに直接販売できるため、こうした手数料が発生しないケースもあります。また、国際送金においても、銀行を介さずに低コストで即時に完了できる点は大きなメリットです。このように中間マージンの削減は、最終的に消費者にとっては価格の低下を、クリエイターや提供者にとっては利益の向上をもたらす可能性があります。
Web3のデメリット
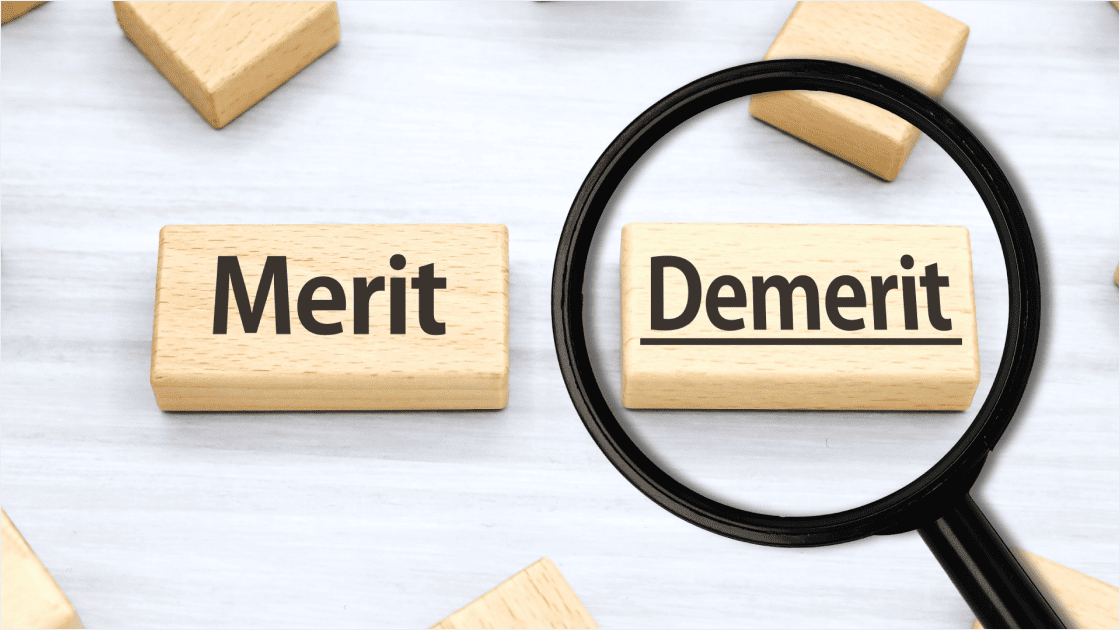
Web3は革新的な技術ですが、いくつかの重要なデメリットも存在します。ここからはデメリットについて見ていきましょう。
管理者が不在
Web3の世界では中央の管理者が存在しないことが多く、トラブルが発生しても頼れる相手が見つからない場合があります。例えば、暗号資産にアクセスするには秘密鍵と呼ばれる固有の文字列を入力する必要がありますが、この秘密鍵を紛失した場合は復旧する手段がなく、資産にアクセスできなくなる可能性もあります。従来のWebサービスでは運営会社に問い合わせれば解決できた問題も、Web3では自己責任となるのです。
また、システムのバグやセキュリティ上の欠陥を修正する速度はプロジェクトにより異なります。ユーザーコミュニティによるサポートしかない場合も多く、初心者にはハードルが高いと感じられることも少なくありません。
自分自身がデータや資産の所有者となる自由を得る一方で、その管理責任も全て自分で負うことになるのです。この「管理者不在」という特性は、Web3の大きなメリットであると同時に、普及における課題でもあります。
詐欺や犯罪のリスクが高い
Web3の世界は匿名性が高く、多くの国や地域ではWeb3関連の法規制がまだ追いついていません。そのため、詐欺や犯罪行為が横行するリスクを常に抱えています。
特に仮想通貨やNFTの分野では、開発者による出資金持ち逃げや、価格操作、フィッシング詐欺などのトラブルが頻発しています。また、システムの脆弱性を突いたハッキング被害もあとを絶ちません。
例えば2022年には、DeFiプロジェクトから多額の資産が盗まれる事件が発生しました。こうした被害に遭っても、分散型システムの特性上、取引の取り消しや資産の回収は極めて困難です。さらに、国際的な取引が容易なため、犯罪者は法の網をかいくぐりやすく、国や地域によっては被害者救済の仕組みが不十分な場合もあります。
Web3の可能性を享受するためには、これらのリスクを十分理解し、セキュリティ対策を万全にすることが不可欠です。
操作が難しく、一般ユーザーには不親切
Web3テクノロジーは革新的な可能性を秘めているものの、現状では操作性に大きな課題があります。「ウォレット」「秘密鍵」「ガス代」など、初心者には理解しにくい専門用語や手続きが多く存在し、エラーが発生した際の解決方法も複雑です。
公式のサポート体制はプロジェクトによって異なります。充実している場合もありますが、多くのユーザーはDiscordやRedditなどのユーザーコミュニティに質問して解決策を探っています。
こうした技術的ハードルが、Web3の普及を妨げる要因ともなっているのです。
ビジネスでのWeb3活用例

Web3技術はビジネスのさまざまな分野で革新的な活用が進んでいます。ここからは実際にどのような活用方法が考えられるのか具体的に見ていきましょう。
クリエイター・コンテンツ制作者による活用例
Web3はクリエイターやコンテンツ制作者に革命的な可能性をもたらしています。従来のプラットフォームでは、作品の収益のかなり大きな部分が手数料として徴収されていました。しかし、NFTなどのWeb3技術を活用することで、アーティストは自分の作品を直接ファンに販売でき、二次流通からもロイヤリティを得ることが可能です。
また、コミュニティトークンの発行により、ファンとの新しい関係性を構築し、支援者に特典を提供することもできます。
Web3は透明性と分散化を通じて所有権の管理を変革し、デジタルコンテンツにおける創作者の権利をより強化する新たなエコシステムを生み出しているのです。
マーケター・広報担当者による活用例
Web3技術はマーケティングや広報活動にも革新をもたらしています。特にNFTを活用したキャンペーンは、単なる販促ではなく、顧客との新たな関係構築が可能です。
例えば、限定NFTの配布によるロイヤルティプログラムは、ブランドのファンとの絆を強める効果的な手段となっています。さらに、DAOの仕組みを取り入れたブランドコミュニティでは、ファンは製品開発や意思決定に関与する機会を得るため、エンゲージメントが飛躍的に向上するでしょう。
先進的な企業では、Web3技術を活用したファンマーケティングの可能性が探求されており、顧客との共創による新たなマーケティングの形が生まれています。
起業家・新規事業担当者による活用例
Web3は、新たに事業を立ち上げる起業家や、新規事業を担当する人にとって、大きな可能性を秘めています。
例えば、従来のように法人を設立して資本金を集めるのではなく、DAOを立ち上げ、事業に参画する人たちの投票によって事業の意思決定を行うスタイルを選ぶこともできます。透明性の高い経営が可能になり、参画する仲間を集めやすくなるでしょう。
また、DeFiを活用すれば、金融機関を介さずに資金の貸し借りや運用が可能となり、従来よりも低コストでスピーディーな資金調達ができます。
このように、DAOやDeFiを活用することで、従来の組織や金融の枠にとらわれない、新しいビジネスモデルを構想することが可能になっているのです。
まとめ

Web3は、インターネットの次世代形態として私たちのデジタルライフを大きく変えようとしています。ブロックチェーン技術を基盤に、NFT、暗号資産、DAO、DeFiなどが発展し、多様な形態の革新的サービスが生まれています。
Web3の世界は発展途上ですが、その可能性を理解し、適切に活用することで、競争優位性の確立や新規事業の創出といったビジネス面での新たな展望が開けるはずです。今後の動向に注視しつつ、自社の戦略や目的に応じた具体的な検討を進めていくことが求められます。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




