- 公開日:2025年10月10日
DAO(分散型自律組織)とは?Web3時代における新たな組織のあり方を紹介
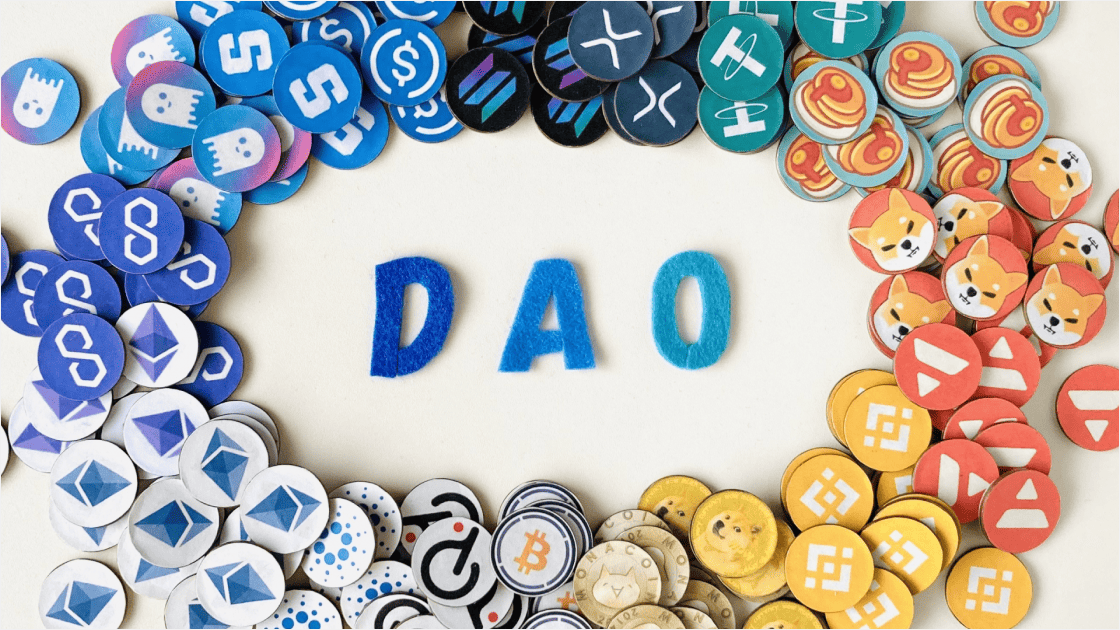
近年、中央管理者を持たない分散型自律組織「DAO」が世界中で注目を集めています。これは、ブロックチェーン技術とともに発展してきた新しい組織の形であり、透明性や効率性を重視した運営手法を実現できる仕組みです。特にWeb3の普及が進むなか、企業から自治体やNPOに至るまで、DAOの可能性に期待が寄せられています。
本記事では、DAOの仕組みや特徴、メリットや課題、そして国内での活用事例をわかりやすく解説し、Web3時代における新たな組織のあり方について考察します。
DAOとは
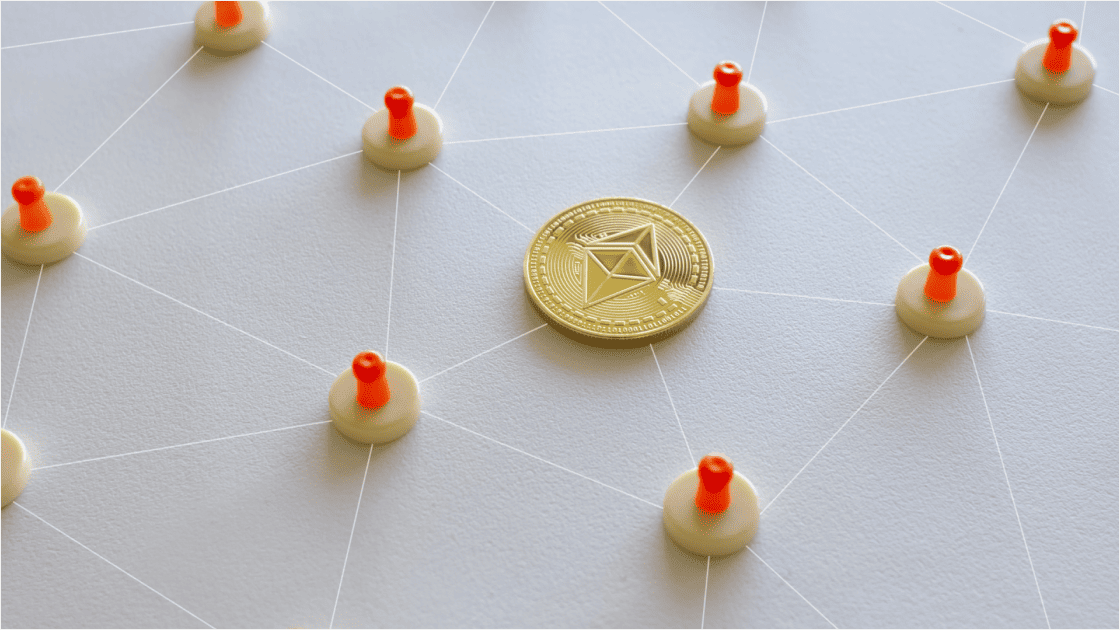
DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の略称で、日本語では「分散型自律組織」と訳されます。従来の企業や団体のように経営者や管理部門のような「中央管理者」が存在せず、インターネット上で分散的に参加する人々によって成り立つ組織形態です。
DAOはブロックチェーン技術を基盤とし、スマートコントラクト✳︎1が意思決定や資金管理を担います。従来の組織が会議や承認手続きを通じて意思決定するのに対し、DAOではトークンを用いた投票によってルールが自律的に執行されるのが特徴です。例えば、分散型金融「DeFi」のサービスを運営するDAOや、NFTアートの共同購入を目的としたDAOなど、さまざまな形で活用されています。
✳︎1スマートコントラクトとは、設定されたルールにしたがって自動で実行される契約プログラムのこと。人の手を介さないため、改ざんや不正の防止につながる。
DAOに注目が集まる背景
DAOが注目される背景には、Web3関連サービスの普及や、グローバルに協力できる分散型組織への需要の高まりがあります。特に、近年は中央集権型の組織やプラットフォームに対する不信感も広がっており、より透明で公平な意思決定を可能にする仕組みが求められてきました。
また、変化のスピードが速い現代では、従来の中央集権型組織は意思決定に時間がかかり、環境の変化に対応しにくいという課題があります。DAOはトークンを活用した合意形成や自動化されたルールによって、迅速かつ柔軟な意思決定を可能にします。こうした仕組みにより、組織は競争力を維持しやすくなり、国境を越えて人材や資金を集めながら世界規模で協働できる点が注目されています。
なお、以下の記事では分散型インターネット「Web3」について解説しています。詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
関連記事:Web3とは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説
DAOの仕組みとブロックチェーン技術の関係
DAOが機能するためには、ブロックチェーン技術が欠かせません。特に以下に挙げた3点は、DAOの基盤となる技術・仕組みといえます。
【分散型データ管理】
ブロックチェーン上に全ての取引や意思決定が記録され、参加者は誰でも確認することが可能。改ざんが難しいため、高い透明性が確保される。
【スマートコントラクトによる自動化】
契約内容をプログラムとして書き込み、条件が満たされると自動的に実行される仕組み。例えば、「投票で過半数が賛成したら資金を配分する」といったルールが自律的に働くため、会議や承認フローを待つ必要がなくなる。
【トークンを活用したガバナンス】
DAOの参加者はガバナンストークンを保有し、その数に応じて投票権を持つ。これにより、意思決定や報酬分配が公平に行われる。
このように、ブロックチェーン技術を活用した仕組みによってDAOは人の介在を最小限に抑え、透明で効率的な組織運営を実現しています。
DAOの基盤となるブロックチェーンの理解をより深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事:ブロックチェーンとは?仕組みや特徴、活用事例やメリット・課題について紹介
DAOと従来型組織との違い

DAOは従来の企業や団体とどのように異なるのでしょうか。以下の表に整理しました。
| 従来型組織 | DAO | |
|---|---|---|
| 管理体制 | 中央集権型(階層構造) | 自律分散型 |
| 存在形態 | 物理的拠点が中心 | オンライン上 |
| 意思決定の方式 | トップダウン | トークンによる投票 |
| 社員/メンバーとの関係 | 雇用関係 | オープン参加 |
| 責任の所在 | 明確 | 曖昧になる場合もある |
従来の組織では社長や取締役といった明確な意思決定権者が存在し、物理的な拠点やオフィスを中心に運営されていました。それに対し、DAOは基本的にオンライン上で存在し、トークン保有者による合意形成で方針が決まります。この仕組みは柔軟性とスピード感に優れている一方で、責任の所在が曖昧になりやすい点はデメリットといえるでしょう。
また、DAOは国境や雇用契約に縛られず、多様な人材が参加できる点で大きな可能性を持っています。グローバル展開を検討している企業や、社外の専門人材と協業したい企業にとっては、有効な組織運営のモデルです。
DAOのメリット
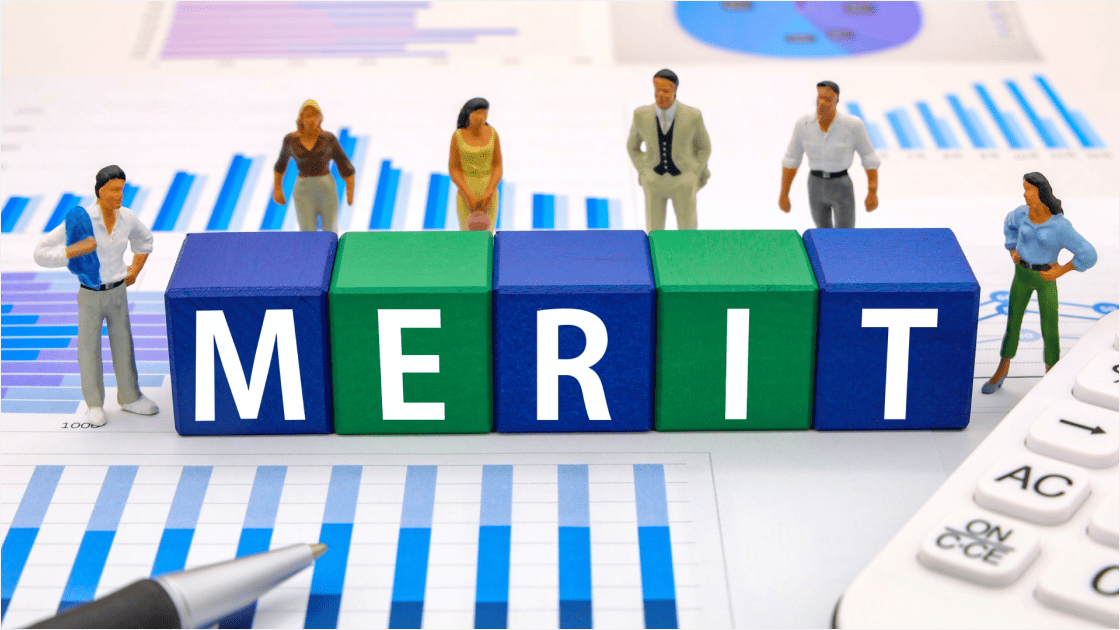
最新技術が取り入れられた組織「DAO」には、従来型の組織にはないメリットがあります。DAOがどのようなメリットをもたらすのか詳しく見ていきましょう。
組織の透明性や柔軟性を高められる
DAOには中央管理者が存在せず、全ての意思決定や資金の流れをブロックチェーン上で確認することが可能です。参加者全員が平等にルールを理解し、意思決定に関われることから、不透明さや不公平感が少なくなります。これにより、プロジェクトの変更や資金配分の見直しなど、従来型組織では時間や承認手続きなどの制約により難しかった柔軟な対応も可能になります。
組織運営の効率化が図れる
スマートコントラクトによって事務処理や承認手続きが自動化され、迅速で効率的な運営を行えます。例えば、資金調達や報酬分配のルールを事前に設定しておけば、DAOに参加しているメンバーの投票結果に応じて自動的に実行され、結果として、運営コストの削減や不正防止にもつながります。
参加者のモチベーションを向上させられる
DAOでは、貢献度に応じてトークンを報酬として受け取る仕組みが導入されることがあります。トークンの価値はプロジェクトや組織の成長とともに高まるため、参加者にとっては「自らの活動が組織の価値を高める」という実感が得られやすく、モチベーション向上につながる点もメリットです。
雇用に縛られず優秀な人材を世界中から集められる
DAOは、インターネットとブロックチェーンを基盤としているため、国籍や居住地に関係なく誰でも参加が可能です。従来のように雇用契約を前提としてオフィスや組織体制を中心に運営される企業では出会えなかった専門人材やクリエイターも、DAOではスキルや貢献度を基準に評価される仕組みにより参画しやすくなります。その結果、組織全体の革新力や競争力の向上につながります。
DAOが抱える課題

従来の組織にはない柔軟な対応力や、国籍に関係なく優秀な人材を集められる点など、組織を運営するうえで魅力的な特徴を持つDAOですが、課題点もあります。
将来的には改善される可能性も十分に考えられますが、DAOを取り入れた組織運営を検討されている方は、現状の課題点についても把握しておきましょう。
セキュリティ面でのリスク
DAOはブロックチェーン上で運営されるため、ハッキングや不正アクセスといったリスクを完全に排除することはできません。特にスマートコントラクトのコードに脆弱性がある場合、攻撃者に悪用されて大きな損失につながる可能性があります。
従来の組織であれば管理者が即時対応できますが、DAOでは投票や合意形成を必要とするため、迅速な対応が難しい場合がある点に注意が必要です。
法整備が追いついていない
日本を含む多くの国では、DAOに関する法的な定義や保護はまだ十分に整備されていません。法人格を持たないため、契約や責任の所在が曖昧になり、トラブル発生時の対応も不透明です。特にハッキングなどの悪意ある第三者による被害が起きた場合、従来の法律では対応が難しいという課題があります。
意思決定が遅くなる場合がある
DAOではスマートコントラクトによって承認フローの短縮が可能で、通常はスピーディな意思決定が期待できます。しかし、投票率が低い場合や緊急対応が必要な場合には合意形成に時間がかかることもあります。
DAOを活用する前にルールを整備することである程度は緩和できますが、こうしたケースでは意思決定が遅れる可能性がある点に留意しておく必要があります。
DAOの活用事例

DAOの概念は海外から広まりましたが、近年は日本でも多様な取り組みが進んでいます。ここで紹介する国内の代表的な事例を確認し、自社での活用を考えるヒントにしてみてください。
地域活性化に活かすDAO
過疎化が進むある地域では自治体と地域団体が連携し、地域の課題や資金調達を目的としたDAOを立ち上げました。最大の特徴は、行政が一方的に主導するのではなく、住民や支援者が主体的に関われる点です。オンライン上にコミュニティを形成するため、地域住民だけでなく外部の人も参画でき、全国・海外からも支援の輪を広げられます。
参加者はトークンを通じて意思決定に関与し、観光資源の活用や新規イベントの企画、地域産品のブランディングなどをボトムアップ型で進めることが可能です。従来の「行政主導・住民は受け手」という関係性とは異なり、DAOを通じて多様な人材やアイデアを取り込みながら、より柔軟で透明性のある地域活性化を目指す取り組みが広がりつつあります。
この仕組みは企業の地域プロジェクトやCSR活動にも応用できます。例えば、地域イベントや社会課題解決型プロジェクトにDAO型の運営を取り入れ、社内外の関係者やパートナー企業が意思決定やアイデア出しに参加する形で、透明性の高い協働体制を作ることもできるでしょう。
DAOによるWeb3スタートアップ支援
スタートアップ支援を目的としたDAOでは、クラウドファンディングの仕組みを基盤に、資金調達から運営までをコミュニティ主導で進めています。参加者はトークンを通じて投票や意思決定に関わり、資金の配分や支援対象の選定を協議しながら進める点が特徴です。
さらに、メタバース上での共同作業や、NFTを活用した報酬分配などのWeb3技術を積極的に導入することで、単なる資金援助にとどまらず、事業そのものをデジタルコミュニティと共に成長させる仕組みを整えています。従来型のベンチャーキャピタルが少数の投資家によって意思決定されるのに対し、DAOでは参加者全員が関与できるボトムアップ型の支援が可能です。多様なバックグラウンドを持つ人材が意思決定に加わることで、事業は特定の地域や投資家の視点に偏らず、国際的なニーズや市場動向を取り込みやすくなります。このため、DAOは多様性を強みにしたグローバル市場を見据えた事業成長の支援にも適しています。
こうした取り組みを参考にすれば、企業は社内プロジェクトをDAO型で運営し、関係部署や外部パートナーも意思決定に加わったり、社外の専門人材やスタートアップとの協業に活かしたりといったことが可能です。
DAO型クリエイターコミュニティ
NFTやアニメ、ゲームなどクリエイティブ領域に特化したDAOも活発に運営されています。ここではイラストレーターやアニメーター、エンジニアなど多様なクリエイターが参加し、共同で作品を制作・販売することができます。収益はコミュニティに再分配され、個々のクリエイターに還元される仕組みが整っている点も特徴です。
また、初心者向けの教育コンテンツや日本語で交流できる環境も提供されているため、DAOやWeb3に不慣れな人でも安心して参加できます。従来のクリエイター活動が個人や小規模チームに限定されがちだったのに対し、DAOでは分散的な協働が可能となり、スキルやアイデアを持ち寄ることで新たな創作の場が広がっています。
この仕組みを応用すれば、社内のクリエイティブプロジェクトや外部パートナーとの共同開発にDAO型の運営を取り入れ、参加者全員が意思決定や成果分配に関わる形で、透明性の高い協働体制を構築することもできるでしょう。
DAOの今後の展望

Web3の拡大とともに、DAOの活用領域は今後ますます広がっていくと考えられます。企業だけでなく、自治体やNPOにおいてもDAOの仕組みが導入されれば、従来にない形での住民参加や協働が可能になります。
内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針2022 について」にも示されているように、日本政府もDAOを含むWeb3の環境整備に取り組んでおり、今後法整備や制度面でのサポートが進めば、国内での活用が一層加速するでしょう。特に、企業にとっては「オープンな人材活用」や「透明性の高い資金運用」といった観点から導入を検討する価値があります。
まとめ

DAOは、従来の中央集権的な組織とは異なる新しい仕組みであり、透明性・効率性・柔軟性を兼ね備えています。国内でも地域活性化やスタートアップ支援、クリエイティブ分野などの幅広い分野で取り入れられており、今後さらに注目が集まっていくでしょう。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




