- 公開日:2025年07月16日
クラウドインフラとは?知っておくべき構成要素やメリット、導入時の注意点を紹介
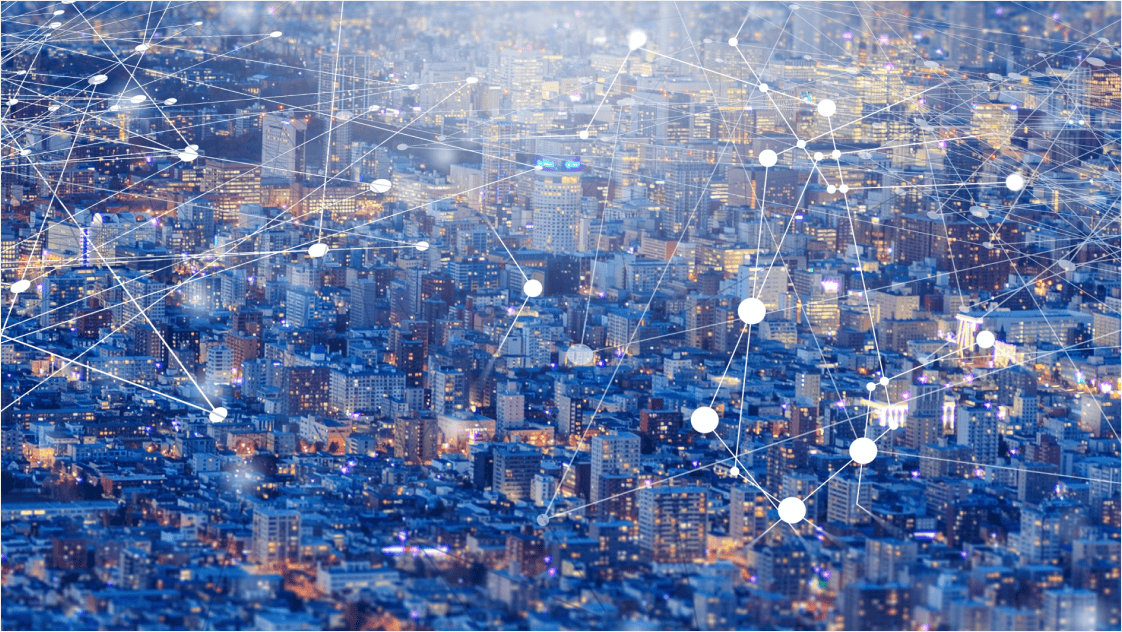
近年、多くの企業でクラウドサービスの活用が広がるにつれて、その基盤となる「クラウドインフラ」の重要性が高まっています。
本記事では、クラウドインフラの定義やクラウドコンピューティングとの違い、主な構成要素や導入によるメリット、利用における注意点について紹介します。
クラウドインフラとは

クラウドインフラとは、クラウドサービスを支えるハードウェアやソフトウェアなどのITリソース全体を指します。サーバやストレージ、ネットワーク機器といった物理的な装置に加え、仮想化技術や自動化ツール、管理ソフトウェアなども含まれます。
これらのリソースは、インターネットを介してデータセンターに接続し、オンデマンドで利用することが可能です。企業は自前で機器を持たずに柔軟かつ効率的な運用ができるため、ビジネスの拡張性とコスト削減の両立が期待されます。
クラウドコンピューティングとの違い
クラウドコンピューティングは、インターネットを通じて処理能力やストレージ、ネットワークなどを必要なときに必要な分だけ利用できるサービスです。このサービスの基盤となるのがクラウドインフラで、物理機器や仮想化技術などで構成されています。
クラウドコンピューティングには「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3種類があり、用途に応じて柔軟に選択可能です。利用者は従量課金制でサービスを利用できるため、初期投資を抑えつつ効率的な運用が実現でき、IT部門の負担軽減にもつながります。
SaaS、PaaS、IaaSについては以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:SaaS/PaaS/IaaSの違いとは? 特徴やメリット・デメリットを解説
クラウドインフラの主な構成要素とは

クラウドインフラは、仮想サーバやストレージ、ネットワーク、仮想化技術などで構成されています。ここでは、それぞれの役割や特徴についてわかりやすく紹介していきます。
サーバ
クラウドインフラにおけるサーバとは、インターネット上に構築された仮想的なサーバリソースのことです。物理サーバと同様に、リクエストの処理やタスクの実行などを担当します。用途に応じて、Webサーバやデータベースサーバ、ファイルサーバなどさまざまな種類があります。
さらにクラウド環境では、複数のサーバをソフトウェアで統合的に管理することで、運用効率や自動化を実現できます。加えて、アクセス状況や負荷に応じてリソースを柔軟に調整できるのも大きな利点です。
ストレージ
クラウドインフラのストレージとは、ネットワークを通じてデータの保存や取得が可能な、オンライン上の記憶領域を指します。業務ファイルを一元的に管理し、必要に応じて柔軟に共有できるため、部門間の連携や社外とのやりとりにも活用でき、業務の効率化を図ることができます。
また、物理的なストレージ機器を自社で購入・管理する必要がなく、初期導入コストや運用負担を大幅に削減できるのも大きな利点です。さらに、データを地理的に離れたデータセンターに保存することで、災害時におけるデータ損失のリスクを最小限に抑えることが可能です。こうした特徴は、BCP(事業継続計画)対策にも有効に活用できます。
BCP(事業継続計画)については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:BCPを考慮したネットワークを構築しよう!方法やポイントを解説
ネットワーク
クラウドインフラにおけるネットワークは、ユーザーやアプリケーションがクラウド上のリソースにアクセスするための仮想的な接続基盤です。ネットワークインフラには、物理的なスイッチやルータ、ロードバランサーなども含まれ、クラウド環境全体を安定して機能させる重要な役割を担います。
仮想ネットワークにより、複数の拠点や端末からの遠隔アクセスが可能となり、リソースの共有や連携もスムーズに行えます。さらに、スケーラビリティに優れており、ネットワークの拡張や構成変更にも柔軟に対応できるのが特徴です。
仮想化
クラウドインフラでは、仮想化技術を活用することで、CPU・メモリー・ストレージといったハードウェア資源を仮想的なリソースプールとして抽象化し、統合的に管理しています。この仮想化を支えるのが「ハイパーバイザー」と呼ばれるソフトウェアです。これにより、1台の物理サーバ上に複数の仮想マシンを独立して稼働させることが可能です。
ユーザーは必要なコンピューティング資源をオンデマンドで選択・利用できるため、無駄のない効率的なインフラ運用が実現され、クラウドサービスの基盤として重要な役割を果たしています。
クラウドインフラのメリット

クラウドインフラには、必要なときにリソースを柔軟に拡張できる高い拡張性に加え、初期投資を抑えやすいコスト面での利点や、高度なセキュリティ対策といったメリットがあります。
ここでは、従来のオンプレミス環境と比較しながら、クラウドの利点について紹介します。
オンプレミスとクラウドの比較については以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:オンプレミスとは?クラウドとの違いや比較ポイント、選び方を解説
拡張性が高い
クラウドインフラは、CPUやメモリー、ストレージやネットワークなどのリソースを必要に応じて柔軟に拡張・縮小できる点が大きな特徴です。
さらに、従量課金制を採用しており、使った分だけ料金が発生するため、無駄なコストを抑えることが可能です。オンプレミスのように将来を見越して高額な設備を事前に用意する必要がなく、成長段階の企業やスタートアップにとって、IT戦略の柔軟性と経済性を両立できる大きな利点となります。
初期投資の負担が少ない
クラウドインフラは、オンプレミス環境のように物理機器や専用ソフトを自社で購入・保有する必要がないため、初期投資を大幅に削減できます。将来的な需要増加を見越して高額な設備をあらかじめ用意するといったことも不要で、必要なときに必要な分だけリソースを柔軟に利用可能です。
また、機器の調達や設置も必要ないことから、短期間でのシステム立ち上げと早期の事業展開を実現できます。ただし、利用量が増えるとランニングコストが高くなる場合もあるため、導入前にTCO(総所有コスト)を見極めることが重要です。
セキュリティ対策が強化されている
クラウドインフラでは、セキュリティに特化した専門家が常駐し、サイバー攻撃やマルウェアなど日々進化する脅威に対して高度な防御策を講じています。ユーザー側の対策に加えて、クラウドプロバイダーが提供する監視機能や脆弱性テストなどを併用することで、セキュリティリスクの大幅な軽減が可能です。
また、クラウドではデータの自動バックアップや複製が行われており、ハードウェアの障害や自然災害が発生した場合でも、重要なデータを安全に保護できる仕組みが整っています。
クラウドインフラの注意点

クラウドインフラは多くの利点を持つ一方で、適切に活用するにはいくつかの注意点があります。
ここでは、リソースの可視化が難しい点や、責任共有モデルの理解、安定したインターネット環境の整備やクラウド人材の確保の難しさといった留意すべきポイントを解説します。
リソースの可視化
クラウドインフラでは、ユーザーが実際に処理を行っている物理サーバやネットワーク機器の状況を、直接把握するのは困難です。これは、クラウドプロバイダーが提供する仮想マシンや仮想ネットワークが高度に抽象化されているからです。そのため、オンプレミス環境に比べて障害対応やトラブルシュートが複雑になる場合があります。
こうした背景から、モニタリングツールやログ管理、ダッシュボードなどを活用し、リソースの状態を可視化することが求められます。加えて、アクセス権限や利用ルールを明確に定め、透明性を確保するためのポリシー運用も不可欠です。
責任範囲の明確化
クラウドサービスでは、セキュリティの運用責任をクラウドプロバイダーと利用者(企業)が分担する「責任共有モデル」が採用されています。例えばAWSの場合、物理サーバの保守やデータセンターの出入り管理、OSのセキュリティ設定などはプロバイダー側が担当し、アプリケーションやデータの暗号化、アクセス管理などは利用者の責任範囲とされています。
この分担を正しく理解していないと、設定ミスや監視不足によって重大なセキュリティリスクを招く恐れがあります。クラウドインフラを導入する際は、機能性やコストだけでなく、「責任共有モデル」に基づく責任の範囲を明確にしたうえで自社が担うべき管理項目を把握しておくことが重要です。
インターネット環境の整備
クラウドサービスは基本的にインターネット経由でアクセスするため、通信環境さえ整っていれば、場所を問わずに利用できるという点は大きなメリットです。しかし、インターネット回線が遅かったり、不安定だったり、停電が発生した場合には、クラウドの応答速度の低下やアクセスできなくなるリスクもあります。
そのため、クラウドの性能を最大限に引き出すには、高速かつ安定したネットワーク回線の整備が不可欠です。導入時には、回線の帯域や冗長性、通信の優先制御(QoS)などネットワーク面での準備も同時に検討しましょう。
人材の確保
企業のIT化やDXの推進に伴い、クラウドに精通した人材の確保がますます困難になっています。特にクラウドインフラは、利用目的や構成によって推奨される機器やサービスが異なるため、導入段階から高度な専門知識が求められます。
自社にこうしたスキルを持つ人材がいない場合には、育成や採用を検討する必要がありますが、IT人材の不足が深刻化するなかで、それも容易ではありません。そこで、運用管理や保守を専門に担う「マネージドサービス」の導入を視野に入れることで、社内の負担を抑えつつ、クラウド活用を円滑に進めることが可能になります。
IT人材の不足については以下の記事でさらに詳しく解説しています。
関連記事:IT人材不足の深刻化にどう立ち向かう?企業が直面する課題と解決策
まとめ

本記事では、クラウドインフラの定義やクラウドコンピューティングとの違い、主な構成要素、導入によるメリット、そして利用時の注意点について解説しました。
クラウドインフラは、コスト削減や柔軟な拡張性、高度なセキュリティ対策を実現する一方で、リソースの可視化や責任分担、インターネット環境の整備、人材確保といった課題もあります。これらを正しく理解し、自社の課題や目的に応じたクラウド基盤を選定することが重要です。
オプテージが提供する「Neutrix Cloud」は、国内データセンターで構築された高信頼なクラウドインフラで、閉域網接続や24時間365日のサポート、マネージドサービスなども充実しています。
多くのお客さまが展開する自社でのプライベートクラウドとも親和性があり、シームレスに連携できるため、大規模なデータ移行を行わずに導入することも可能です。
クラウドインフラについてお悩みの点がありましたら、オプテージまでお気軽にご相談ください。
◎製品名、会社名等は、各社の商標または登録商標です。




